愛知県弁護士会トップページ>
愛知県弁護士会とは
>
ライブラリー >
連載
今、改めて「人権」について考えてみる
第6回 再審法改正への道を切り開く
連載
今、改めて「人権」について考えてみる
第6回 再審法改正への道を切り開く
会報「SOPHIA」令和7年2月号より
会報編集委員会
会報編集委員会では、昨年度より【今、改めて「人権」について考えてみる】と題して「人権」にフォーカスした特集に取り組んでいます。今回は、国家による最大の人権侵害「えん罪」を救済するための制度である刑事訴訟法第4編の再審に関する規定(以下「再審法」)の問題を取り上げます。
9月26日の袴田事件再審無罪判決や、10月23日の福井女子中学生殺人事件再審開始決定等、今年度は再審に関する注目すべき判断が相次ぎ、再審法改正に向けた社会の関心はかつてないほど高まっています。1月23日には、超党派の議員連盟が再審制度の見直しに向け本格的に動き出し、今国会に議員立法による法案を提出し、法改正を目指すとの報道があり、また、2月7日には、法務大臣が再審制度見直しについて法制審議会への諮問を正式表明しており、検察側の証拠開示のルールや、再審開始決定に対する検察の不服申立のあり方等、幅広い論点で議論が行われる見通しとなっています。
このように、再審法改正の動きは現実的なものとなっています。そこで、本特集では、再審法の概要や問題点等基本的な事項を押さえた上で、再審法改正に向けた当会や日弁連の活動状況を紹介します。これまで再審法改正になじみがなかった会員も、今回の特集をきっかけとして関心を持っていただけたら幸いです。
1 再審法の概要
(1)再審手続
刑事訴訟法上、再審に関する規定は435条から453条に置かれています。
再審手続は、再審理由があるかどうかを審理する再審請求審と、再審決定確定後、有罪か無罪かを審理する再審公判に分かれます。
(2)再審請求の管轄
再審請求の管轄は、有罪の確定判決をした裁判所です。第一審で有罪が言い渡され、控訴・上告とも棄却されて第一審判決が確定した場合には、第一審判決を行った裁判所が管轄裁判所となります。これに対し、第一審判決が取り消され、控訴審判決が確定した場合には、控訴審判決を行った裁判所が管轄裁判所となります。福井女子中学生殺人事件を例にとると、第一審の福井地裁は無罪でしたが、控訴審の名古屋高裁金沢支部で逆転有罪判決が宣告され、最高裁が上告を棄却したため控訴審の有罪判決が確定しています。そのため、再審請求は名古屋高裁金沢支部に申し立てられています。
(3)再審請求人
再審請求権が認められているのは、有罪の言渡を受けた者や、有罪の言渡を受けた者が死亡した場合の配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹等です。再審請求中に本人が死亡した場合は、受継の手続を定めた規定がないため、当該再審請求手続は終了します。死後再審を行うためには、あらたに再審手続を行う必要があります。名張毒ぶどう酒事件では、第9次再審請求中に本人である奥西勝氏が死亡したため訴訟手続の終了決定がなされ、その後、奥西氏の妹が請求人となって第10次再審請求(死後再審)が申し立てられました。
(4)再審理由
再審請求を行うためには、刑事訴訟法435条、436条に定められた再審事由が必要です。多くの場合、435条6号に規定された、有罪の言渡を受けた者に対し無罪等を言い渡すべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき」を理由としています。同要件に該当するためには、証拠の「新規性」と「明白性」が必要となります。
(5)即時抗告等
再審請求棄却決定または再審開始決定に対しては、即時抗告(その決定を高裁がした場合には、異議申立)をすることができます。いずれも申立期間は3日です。
即時抗告審・異議審の決定に対する特別抗告の申立期間は5日です。特別抗告理由は、憲法違反、判例違反(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、重大な事実の誤認等(同411条)が準用されます。
(6)再審公判
再審開始決定が確定すると、再審公判が開かれます。審理は、確定判決の言渡がなされた審級の裁判所で行われます。
第一審の場合は、全手続をやり直すので、人定質問、起訴状の朗読から開始されます。
再審公判の審理の進め方については刑事訴訟法451条にしか規定がありません。多くの事件では、再審公判の審理は「公判手続の更新」に準じて行われており、その場合、確定記録中の証拠については公判手続更新の手続に準じて取調べを行った上で審理が続行されます。
再審の判決が確定すると、原判決は当然に失効します。
2 再審法の問題点
再審に関する規定は、全体でわずか19条しかなく、詳細な手続規定はありません。このことから、審理の進行が裁判所の訴訟指揮に委ねられており、裁判所の姿勢如何によって結論が大きく異なる「再審格差」が生じています。
現行再審法の問題点を袴田事件に即して見てみましょう。
(1)袴田事件の推移
1966年6月30日 事件発生
1980年12月12日 死刑確定
1981年4月20日 第1次再審請求
2008年3月24日 特別抗告棄却
2008年4月25日 第2次再審請求
2010年12月6日 重要証拠の開示
2014年3月27日 地裁、再審開始
2018年6月11日 高裁、再審開始決定取消
2020年12月12日 最高裁、高裁決定取消差戻し
2023年3月13日 高裁、地裁の再審開始決定を支持
2023年10月27日 地裁再審公判開始
2024年9月26日 無罪判決
2024年10月9日 検察上訴権放棄により無罪判決確定
(2)審理期間の長期化
袴田事件は、事件発生から無罪確定まで実に58年もの時間がかかっています。その間、第1次再審請求手続は約27年、第2次再審請求手続は約15年を要しています。その原因は、現在の再審法に再審請求審をどのように進めるかという手続規定が定められていないことにあるといえます。
(3)証拠開示制度の不備
袴田事件では、再審段階で約600点もの証拠が新たに検察側から開示され、それらが再審開始及び再審無罪の判断に大きく影響を与えました。しかし、これらの証拠が開示されたのは、最初の再審請求から約30年もの時間が経ってからのことです。これほどまでに時間を要した原因は、現行法に再審における証拠開示の制度が定められていないことにあるといえます。
(4)検察官による不服申立
袴田事件では、2014年に再審開始決定がなされましたが、再審公判が開かれるまでにはさらに9年以上もの期間を要しています。その原因は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることにあるといえます。検察官は、再審開始後の公判において有罪立証を行えば足りるところ、再審開始決定に不服申立てが禁止されていないため、再審公判が開かれるまでの間に、同じ論点について、数次にわたって裁判所の判断を経ることになっており、このことも手続が長期化した原因となっています。
3 改正に向けた動き
こうした問題は、他の再審請求事件でも同様にみられる制度的・構造的な問題です。日弁連は、2023年2月17日に刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書を公表し、再審法の速やかな改正を求めています。当会でも、再審法改正に向けたシンポジウムを精力的に開催し、また、国会議員や地方議員に対する働きかけを行ってきています。
日弁連の活動については、日弁連ホームページでも確認することができます。
これまでの活動から見えてきたもの
再審法改正実現本部 本部長代行 後 藤 昌 弘
一昨年から当会でも再審法制改正に向けて幾つかのシンポジウム等を開催してきた。その過程で現状の再審法における様々な問題点が明らかになった。既に本紙面上で紹介した記事と重複する点はあるが、一連の活動内容を振り返りつつ再審法の問題点を改めて紹介してみたい。
【湖東記念病院事件】
2023年7月22日に、マスコミの立場でこの事件を取り上げてきた当時中日新聞編集局長の秦融氏・えん罪被害者の西山美香氏・弁護団長の井戸謙一弁護士(滋賀)を招いてシンポジウムを開催した。詳細は会報第750号(2023年8月号)14頁以下を参照されたい。
この事件は、端的に言えば、人工呼吸器で生命を維持していた患者が死亡していたことについて、自分の責任となることを懸念した西山氏とは別の看護師が、人工呼吸器のチューブが外れていたとの事実に反する説明をしたことがきっかけとなり、単なる病死が殺人事件として起訴され、懲役12年の実刑判決に至った事案である。西山氏は満期出所後二度目の再審請求でようやく再審が認められて最終的に無罪が確定したが、この間西山氏は12年間服役を強いられた。
このシンポジウムで印象に残ったのは2点ある。第二次再審請求で大阪高裁が致死性不整脈の可能性を指摘して再審開始決定を下した後、検察官が特別抗告をしたのである。この特別抗告がされたときは西山氏は本当に落ち込んだそうである。高裁が慎重に判断して確定判決に疑いがあるとして再審開始を決定した以上再審で再度有罪を立証すれば良いはずであるのに、何故検察はそこまで結論を引っ張ろうとするのか、これが被害者にどれだけの苦痛を与えるのか。結果的に特別抗告は西山氏の苦痛を倍加させたのみであった。正に検察官の抗告権が如何に過酷な結果をもたらすかが明らかになったと言えよう。
今1つ、弁護団長の井戸弁護士によれば、再審の審理の過程で開示された証拠が確定審で提出されていれば、そもそも有罪判決に至ることは無かったと言える事件だったとのことである。再審請求審における証拠開示の重要性もさることながら、無罪を明らかにする証拠が手元にありながら、敢えてそれを「隠蔽」するという検察官の行為は、後に述べる福井女子中学生殺人事件での検察官の対応にも通じるところである。
【袴田事件と大崎事件】
2024年9月22日に、元判事の村山浩昭弁護士(東京)と鴨志田祐美弁護士(京都)をお招きしてシンポジウムを開催した。詳細は会報第763号(2024年9月号)42頁以下を参照されたい。
元判事の村山弁護士のお話で印象に残ったのは、裁判官の立場から法整備の必要性や検察官の不服申立ての制限の必要性が語られたことである。規定が整備されていないため、裁判官は再審請求を放置しても咎められることはないし、逆に通常事件を抱えながら再審請求事件に前向きに対処しようとすると陪席を含め裁判官には大変な負荷がかかる。また、袴田事件では味噌漬け実験が弁護側・検察側で行われたが、検察官の抗告審での再度の実験のために9年間を要したという。再審事件については、心ある裁判官に当たるか否かという、いわゆる裁判官格差の存在が指摘されているが、その背景として審理に関する規定が無いことがあるのが理解できた。今更ながら規定の整備が望まれるところである。
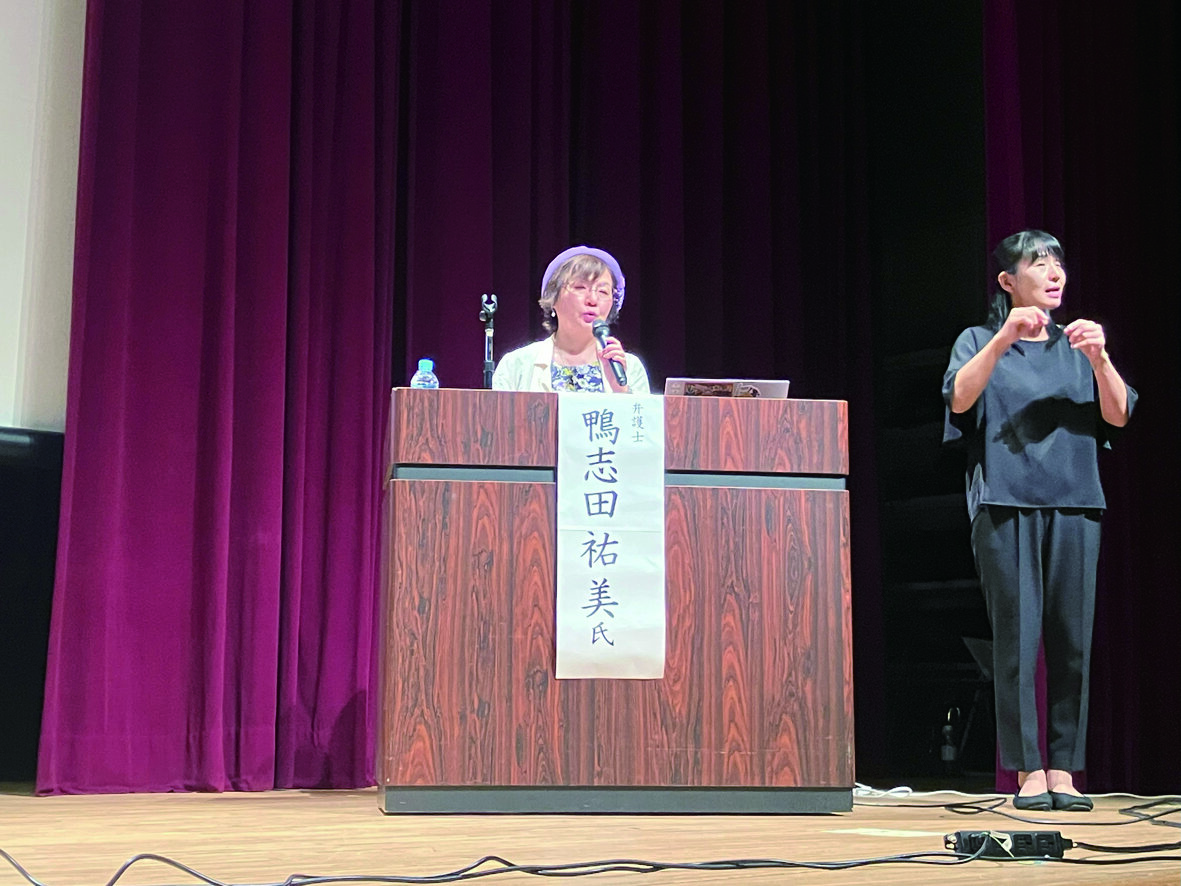
引き続いて鴨志田弁護士から大崎事件について講演いただいた。大崎事件は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である。供述弱者である共犯者の自白と法医学鑑定の結果により主犯とされた原口アヤ子氏は10年間服役した後再審を請求し、この第一次再審請求については2002年3月に再審開始決定が出たものの検察官の即時抗告により開始決定が取り消されており、第三次請求でも地裁・高裁が再審開始を認めたが最高裁が再審開始を覆したという異例の事件である。再審の過程で一定の証拠開示はなされたが、当初「無い」と検察官が答えていた証拠について、後日「警察の写真室のつり棚にあった」として証拠が開示されたこともあったという。
袴田事件は再審で無罪が確定したが、大崎事件は再審開始には至っていない。特に大崎事件は、地裁・高裁のハードルをクリアしたにも関わらず、最高裁が覆している。再審の扉は重いと言われるが、三重になっているとは思わなかった。
【名張毒ぶどう酒事件と飯塚事件】
2024年11月27日に、飯塚事件を取り上げたノンフィクション『正義の行方』の著者である木寺一孝氏と名張毒ぶどう酒事件弁護団の夏目武志会員、そして日弁連再審法改正実現本部の本部長代行である鴨志田弁護士をお招きして、愛知大学の講堂にて愛知大学の学生と一般市民を対象とし、名張毒ぶどう酒事件と飯塚事件から再審請求を考える集いを開催した。
名張毒ぶどう酒事件は、1961年3月28日に起きた大量殺人事件である。集落の懇親会の酒席で振る舞われたぶどう酒に農薬が混入され、ぶどう酒を飲んだ女性17人が中毒症状を起こし、内5人が死亡している。この事件では閉ざされた山奥の集落で外部犯行の可能性が無く、物的証拠も乏しい中でぶどう酒の入った一升瓶に農薬を入れる機会があったのは誰かという点が大きな問題となったようである。この点について、当初は奥西勝氏以外の人物の可能性もあったものの、その後関係者の供述が変遷し、最後は奥西氏以外にはあり得ないとの供述に収斂されたという経緯があった。第一審の津地裁は、①奥西氏以外の者にも犯行機会がある、②ぶどう酒の王冠上の傷痕は奥西氏の歯牙によって印象されたか不明である、③奥西氏の捜査段階の自白は信用できない、として無罪判決を言い渡したが、控訴審の逆転有罪判決で死刑とされ、最高裁で確定している。その後数度にわたって再審が請求され、一度は名古屋高裁で開始決定が下されたものの異議審で取り消された。しかし、かねてよりえん罪の疑いが指摘され、奥西氏は死刑が執行されないまま獄中で死亡している。この事件では関係者の大量の供述調書が存在しているはずであるが、未だに証拠開示はされていない。
また飯塚事件は、1992年2月20日に福岡県飯塚市で発生した誘拐殺人事件である。小学校1年生の女児2人が登校中に行方不明になり、翌21日に山中で2人とも他殺死体となって発見されたという事件である。容疑者として久間三千年氏が逮捕されたが、一貫して否認し続けたものの第一審・控訴審ともに死刑の判決を受け、2006年10月8日に最高裁で死刑が確定した。なお、久間氏はえん罪を訴え続けたが、判決確定から僅か2年後の2008年10月28日に死刑が執行されている。この事件では、初期段階でのDNA型鑑定結果が証拠採用され、被害者に付着していた犯人の体液のDNA型と被告人のDNA型が一致した点が有罪の1つの根拠となっている。ただ問題なのは、同時期に起きたいわゆる足利事件において、飯塚事件と同じ手法で、かつ同じ技官によるDNA型鑑定の結果について、確定審段階では有罪の根拠とされたものの、再審請求審段階で再度最新の技術でDNA型鑑定されたところ、別人の物であることが判明した点である。
足利事件について付言すると、足利事件は1990年5月12日、栃木県足利市にあるパチンコ店の駐車場から当時4歳の幼女が行方不明となり、翌日に渡良瀬川の河川敷で死体が発見された事件である。菅家利和氏は1993年7月7日に宇都宮地裁で無期懲役の判決を受け、確定した。そして再審請求審での証拠開示により容疑者の体液が提出され、再度の鑑定で別人と判明し菅家氏は晴れて無罪となっている。
この点で、飯塚事件においても再度DNA型鑑定を行えばえん罪か否か容易に明らかになるはずであるが、検察官は一貫して資料が無いと主張している。捜査機関において最も重要な証拠資料について鑑定段階で残った資料が廃棄されていたとすれば論外の極みというべきであるし、足利事件では残っていた資料が飯塚事件では無いというのも不自然な話である。飯塚事件について仮にえん罪が明らかになれば死刑制度の存廃に関わることであり、それが検察が開示を渋る理由ではないかとゲスの勘ぐりをしたくなる。
【福井女子中学生殺人事件】
2024年10月23日に再審請求が認められ、同年10月28日に再審請求を認める決定が確定したことを受けて、急遽2024年12月8日に当会会館に上記事件の弁護団長である吉村悟弁護士(福井)をお招きして再審請求にかかる苦労話を伺った。日曜ではあったが、相当数のマスコミの参加も得た。
福井女子中学生殺人事件は、1986年3月19日に福井市の市営住宅で留守番中の女子中学生が何者かに殺害された事件である。当初は非行グループによるリンチや怨恨犯を想定して捜査がすすめられたが、捜査は難航した。そうした中で、1986年10月頃、覚せい剤取締法違反で勾留されていた暴力団員Aが前川彰司氏の犯行をほのめかす供述を始め、それによって前川氏は1987年3月29日に逮捕され、一貫して無罪を主張したものの同年7月13日に起訴された。第一審の福井地裁は1990年9月に無罪判決を言い渡したが、名古屋高裁金沢支部は1995年2月に懲役7年の逆転有罪判決を下し、1997年11月に上告も棄却されている。
その後再審請求が申し立てられ、2011年11月30日に名古屋高裁金沢支部で一旦は再審開始決定が出されたが、検察官の異議申立てを受けた名古屋高裁が2013年3月6日に開始決定を取り消し、最高裁も高裁の決定を支持した。更に2022年10月14日に第二次再審請求が申し立てられ、2024年10月23日に名古屋高裁金沢支部は再び再審開始を認める決定を出し、同月28日に検察官が異議申し立てを断念したため、再審開始決定が確定したのである。
この事件は指紋等の直接証拠が無い中で、覚醒剤事犯で勾留されていたAが「犯人を知っている」と警察官に匂わせたことが発端となっている。そしてAの供述を元に、Aの友人のIとTもAの供述に沿った供述をし、この3名の「事件当日に被告人の着衣に血が付いているのを見た」との警察官調書が作られ、控訴審の法廷でも各自が調書に沿った証言をしたことが有罪の柱となったそうである。
ちなみにIは控訴審で複数回の証言をしているが、検察側の証人としての尋問(第一次供述)では調書通りの証言をし、弁護側の証人としての尋問(第二次供述)では当日の被告人との関係を否定する、矛盾した証言をしていた。控訴審は、Iが犯行日とされる3月19日にAの家でテレビ番組「夜のヒットスタジオ」を見ていたら、アン・ルイスが歌う後ろで吉川晃司が腰を振るいやらしい場面(本件場面)があり、その場面を見た後で被告人と会った際に被告人の胸の辺りに血がついているのを見た等の供述をしていることに着目し、また、警察官作成の捜査報告書にも本件場面がテレビで放映されたと記載されていたことからIの第一次供述の信用性を認め、被告人との関係を否定したIの第二次供述は信用できないと認定し、Iの第一次供述がA供述の信用性を裏付けるとして被告人を有罪とした。
ところが、その後再審請求の過程で弁護団がテレビ局に照会したところ、本件場面は3月19日には放映されていないことが明らかになった。また、第二次再審請求審で開示された証拠の中には、起訴後に検察官が補充捜査として警察に指示して放送局に照会し、この時点で3月19日には本件場面が放映されていないことが明らかになっており、捜査報告書が事実に反することを検察官が知っていたことも明らかになったのである。にもかかわらず、検察官はこの事実を裁判では一切明らかにせず、裁判では3月19日に本件場面が放映されたことを客観的事実として扱い続けた。要は、検察官は被告人を有罪とするために、嘘の事実を主張し続けたことが明らかになっている。
この点について名古屋高裁金沢支部は、再審開始決定において、「確定審検察官の訴訟活動は、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為といわざるを得ず、適正手続確保の観点からして、到底容認することはできない」と断じている。またIは再審請求審で、第一審無罪判決の後の検察側控訴による控訴審で、自己の記憶に反する捜査段階の供述調書通りに証言する見返りに、自首した覚醒剤事犯を見逃してもらうとの闇取引に応じ供述を変えた等とも証言しているし、確定審の控訴審裁判所での検察側の主張に沿う証言をした後に、担当警察官から結婚祝として現金が交付されていた事実も明らかになっている。まさに、事実に反する証言をさせるために警察官が証人を買収していたと言われても仕方ない事実である。

【各行事から明らかになったこと】
一昨年から計4回のシンポジウムや勉強会を開催してきたが、今更ながら我が国においてかくも多くのえん罪事件があることに驚かされた。そこで共通するのは、警察・検察による証拠の『隠蔽』である。現行刑事訴訟法では当事者主義が採用されており、建て付け上は検察側は有罪を立証する証拠のみを裁判所に提出すればよく、無罪の証拠は被告人・弁護側の責務とされている。しかし、この制度の背景には、少なくとも検察官に対する公益の代表者として、明らかな無罪を裏付ける証拠があれば起訴を取り下げる、虚偽の言辞を弄しないなどという信頼があるはずである。ところが現実には、検察官がそうした信頼を裏切る行為が頻発している。郵政汚職事件で大阪地検特捜部の検察官が証拠となるフロッピーディスクの日付を改ざんしたことが明らかになっているし、福井女子中学生殺人事件では客観的事実に反することを知りながら検察官が虚偽の主張を展開してえん罪を発生させている。大崎事件では、検察官が「無い」と言った証拠が後日存在することが明らかになっている。全ての検察官とは言わないが、少なからぬ検察官がこうした不誠実な対応をしているのが実状である。また鹿児島では、検察官に送致していない捜査資料については廃棄を促す内部通達が出されたとも耳にする。こうした実状がある以上、捜査資料の保存・管理について法律で定める必要がある。また、裁判員裁判が始まって以降一定範囲の証拠について弁護人が開示を請求することが認められるようにはなったが、これとても法律上の要件に従って弁護人が請求し、検察官がこれを受けて開示する建て付けとなっており、検察官より「不見当」との回答がされれば弁護人としてはその真偽を確認する術はない。その意味では、今以上に広く弁護人に証拠にアクセスする権利が認められて然るべきではないかと思う。この点は刑事訴訟手続の抜本的改正が必要なことであり、将来に期待することになるが、少なくとも再審請求の手続においては、検察側に未提出証拠のリストを弁護人に開示させる程度の必要はあると思われる。この点で、証拠開示の勧告はおろか3者協議の要請にすら応じない裁判官がいる現状では、最低限裁判官に対して証拠開示を勧告する義務だけは当座の措置として必要であろう。
また、湖東記念病院事件でも指摘されている通り、検察官による再審開始決定に対する不服申立ての権利も認める必要はない。疑義があると裁判所が認めた以上、再審公判で改めて有罪の立証ができるのだから、再審を速やかに始めるべきであろう。
ちなみに、再審開始決定が続いたことを受けてか、法務省は法制審に対して再審法改正を検討する方向になったと聞く。しかし、袴田事件を受けての最高検の検証結果報告を見ても、組織維持の要素が多く、真にえん罪を防止しようとする姿勢はみられない。この点で法務省の提案する改正案が十分なものとなることは期待できないし、また法制審での議論となれば改正までに何年かかるか分からない。こうした点を考えれば、議員立法によるべきではないかと思う。本国会での早期の審議に期待したい。
再審法改正実現本部の活動(ロビイングの実践?)
再審法改正実現本部 担当副会長 舩 野 徹
1 再審法改正実現本部の活動
再審法改正実現本部(当本部)の目標は、刑事訴訟法の再審規定の改正(再審法改正)である。目標到達のために二つの活動をしている。一つはシンポジウム等を通じて市民へ再審法の問題点を訴え理解して貰うことである。二つ目は再審法改正をするよう国に働きかけることである。本稿ではこの二つ目について本年度の活動内容を報告する。
2 国会議員に対する働きかけ
法律改正は国会の専権事項であり、立法過程に働きかける必要がある。一つは、担当官庁による検討を経て内閣から法案を提出するもの(閣法)、もう一つは、国会議員から法案提出をするものである(議員立法)。
再審法改正について、法務省は消極的であるため、当本部は議員立法による改正を目指し、国会議員に対する働きかけを行ってきた。
令和6年3月11日、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が設立された(再審議連)。再審議連は、役員名簿をみれば超党派であることは明らかであるのみならず、大臣経験者等錚々たる顔ぶれであった。
再審議連は、令和6年4月時点では308名であったが、令和7年1月時点では363名になった。国会議員の過半数に達し、議員立法が可能な人数にまで達した。
愛知県内の国会議員は、衆参両院合わせて35名である。当本部は、全員の再審議連への加入等を目指し活動している。
国会議員は、会期中は東京にいることが多いため、日弁連副会長でもある伊藤倫文会長、日弁連理事である奧村哲司会員及び川合伸子会員らが議員会館を訪問した。この成果もあり、複数名の国会議員に議連に加入いただいた。
また、国会休会中は、愛知県内での面談を実現すべく活動した。副会長になると、年度当初から挨拶回りをしたり、受けたりすることが多い。また、各士業の総会に来賓として出席することが多数あり、国会議員又は秘書の方々と名刺交換をすることになる。ここで得たつながりを最大限に活用し国会議員の事務所に赴き、議連に加入いただいたこともあった。
3 地方議会に対する働きかけ
(1)活動方針
法律改正は、世論の支持なくしては困難である。本年度は、袴田事件再審無罪判決や福井女子中学生殺人事件再審開始決定確定等の世論に前向きな影響を与える事件があった。これに加え、地方議会において国に再審法改正を求める旨の意見書採択を求める活動も行った。地方から追い風を生じさせる活動である。
前年度来、まずは、愛知県議会に採択を求め、それが叶えば県下一斉に採択に進むであろうとの見立てであった。本年度も、年度当初はその方針で臨んだが、県議会の都合上、なかなか思い通りにならないようであった。
そこで、本年度は方針を変えて、県下の地方自治体に回り、採択を積み上げていくことになった。採択の機会は年4回である(6月、9月、12月、3月)。
(2)議員への積極的な働きかけ
当本部委員の個人的な伝手を頼りに地方議会に接触した結果、当本部の活動による意見書採択第1号は、本年度6月の江南市となった。福井秀剛会員による活動の成果であった。
当職も担当副会長として地方議会に接触することになった。いままで政治家にお願い事をするなど全く無かったが、地元市会議員に名古屋市議会での採択を陳情し、10月採択に至った。
他の地方議会へも広げようと、上記市会議員から大府市議会議長の紹介を受けた。同議長からは、意見書採択に前向きに応じるに止まらず、複数の地方議員へつないでいただいた。そのうち長久手市、碧南市、知多市が採択に至った。
地方議員と会うたびに、遠慮無く他市町村の議員の紹介を依頼し、次々と面談を進めて行った。地方議員の多くは、「お願い事を聞くのが仕事」と言って、初対面の私に親身になって他市町村の議員にその場で電話をかけるなどして紹介していただいた。このようにして面談した地方議員は、増えていった。
愛知県内には県議会含め55議会ある。うち19議会が採択済みであり、そのうち13議会が当本部から働きかけの結果採択に至ったものである。
(3)地方議会の反応等
袴田事件等の具体的事件の存在は認知されているものの、再審法の何が問題なのか、改正が必要とされる理由については十分に認知されていなかった。
議会によっては、多数会派議員を集めて、レクチャーをすることもあった。その際には、意図していなかったような質問が寄せられ、ハッとさせられることも多く、意見書採択がされる過程では議員が熱心に研究されていることがわかった。
意見書採択に至るまでのルートは、各自治体によって異なる。自治体の数だけ流儀があるといっても過言ではないが、大まかには、ア)議会内の議員の手配によって意見書採択に至るもの、イ)請願書を提出し、委員会で趣旨説明及び質問・討論を経て、採択のうえ本会議で採択に至るもの、ウ)議会を構成する全会派、全議員に説明のうえ、上記と同じく委員会での採択のうえ、本会議で採択に至るもの等がある。
議会での意見書採択は、基本的に全会一致でされることになっている。ゆえに、多数会派の理解を得ることが必須であり、この手順を怠ると、意見書の内容にかかわらず不採択になる。この点は今後こうした活動を進めるうえで留意する必要があると感じた。
4 地方首長に対する働きかけ
当本部では、地方首長からも再審法改正の賛同署名を得る活動をしている。年度当初、みよし市長が、単身、理事者室に挨拶に来られ、その際に名刺交換していた縁を頼りに面談をお願いした。趣旨への賛同にとどまらず、愛知県下の市長全員が集う市長会で説明のうえ、賛同署名への協力を呼びかけていただいた。また、シンポジウムにも参加いただいた。その効果もあってか、愛知県下54市町村のうち、39名の首長から賛同署名を頂戴した。
また、面談した市長が、その日に議会へつないでいただき、議会での意見書採択へつながる場合もあった。
5 ロビイングの必要性
当本部にとどまらず、弁護士会の活動には立法による解決が必要なものが多数ある(例:給費制問題、選択的夫婦別姓問題、取調べの可視化及び弁護人の立会い、手錠・腰縄問題等)。弁護士会は、権力から距離を置くことを是としてきたが、やはり、一定の政策目標を達成するためには、立法過程への働きかけは不可避である。そのためのロビイング等の方法論を研究及び実践する必要があると思われる。
また、働きかけは国会議員のみならず、地方議員も必須と考える。国会議員と地方議員は連携し合っていること、そして、地方議員はより身近に民意を背負って活動されていることを、活動を通じて痛感したからである。
| 自治体 | 議会採択 | 首長賛同書 | |
| 1 | 愛知県 | ○ | |
| 2 | 名古屋市 | ○ | |
| 3 | 豊明市 | ○ | ○ |
| 4 | 日進市 | ○ | |
| 5 | 清須市 | ○ | |
| 6 | 北名古屋市 | ○ | |
| 7 | 豊山町 | ○ | |
| 8 | 東郷町 | ○ | |
| 9 | 瀬戸市 | ○ | |
| 10 | 尾張旭市 | ○ | |
| 11 | 長久手市 | ○ | ○ |
| 12 | 津島市 | ||
| 13 | 愛西市 | ○ | |
| 14 | 弥富市 | ○ | |
| 15 | あま市 | ○ | |
| 16 | 半田市 | ○ | ○ |
| 17 | 常滑市 | ○ | ○ |
| 18 | 東海市 | ○ | ○ |
| 19 | 大府市 | ○ | ○ |
| 20 | 知多市 | ○ | ○ |
| 21 | 一宮市 | ○ | ○ |
| 22 | 稲沢市 | ○ | |
| 23 | 安城市 | ○ | ○ |
| 24 | 碧南市 | ○ | ○ |
| 25 | 刈谷市 | ○ | |
| 26 | 西尾市 | ○ | |
| 27 | 知立市 | ○ | |
| 28 | 高浜市 | ○ | |
| 29 | 豊田市 | ○ | ○ |
| 30 | みよし市 | ○ | ○ |
| 31 | 豊橋市 | ||
| 32 | 岡崎市 | ○ | |
| 33 | 春日井市 | ○ | |
| 34 | 豊川市 | ||
| 35 | 犬山市 | ○ | |
| 36 | 江南市 | ○ | ○ |
| 37 | 小牧市 | ○ | |
| 38 | 新城市 | ||
| 39 | 岩倉市 | ○ | ○ |
| 40 | 田原市 | ||
| 41 | 蒲郡市 | ||
| 42 | 大口町 | ○ | ○ |
| 43 | 扶桑町 | ○ | |
| 44 | 大治町 | ||
| 45 | 蟹江町 | ||
| 46 | 飛島村 | ○ | |
| 47 | 阿久比町 | ○ | |
| 48 | 東浦町 | ○ | |
| 49 | 南知多町 | ||
| 50 | 美浜町 | ○ | ○ |
| 51 | 武豊町 | ||
| 52 | 幸田町 | ○ | |
| 53 | 設楽町 | ||
| 54 | 東栄町 | ||
| 55 | 豊根村 | ||
| 令和7年2月10日時点 | |||



