愛知県弁護士会トップページ>
愛知県弁護士会とは
>
ライブラリー >
連載 弁護士とプロボノ活動(11) 憲法と平和を守るために
~鈴木秀幸会員
連載 弁護士とプロボノ活動(11) 憲法と平和を守るために
~鈴木秀幸会員
会報「SOPHIA」令和6年9月号より
会報編集委員会
皆さん、「ピースあいち」をご存じでしょうか?
ピースあいちは、2007年5月に名古屋市名東区に開設された、戦争と平和の資料館です。
弁護士の情熱と信念が開設を実現させ、現在も多くの弁護士がその運営に協力しています。
今回、ピースあいちを運営するNPO法人「平和のための戦争メモリアルセンター」の理事長であられる鈴木秀幸会員(27期)をお訪ねし、ピースあいちに関すること、鈴木会員の憲法や平和に対する想いについてお話をお聴きしました。
胸が熱くなるエピソードの数々をどうぞお楽しみください。
■本日は取材に応じていただきありがとうございます。私たちは先日ピースあいちに見学に行きました。数ある戦争に関する施設の中でも、戦時中の市民の暮らしにスポットを当てたコーナーがあることは特に印象的でした。鈴木会員は、ピースあいちはどのような施設であるべきだと考えられていますか。
鈴木:ピースあいちの目的は、アジア・太平洋地域への加害と我が国の惨禍という「戦争の実相」を伝えることです。あの戦争は、間違いなく日本にとって有史以来の出来事であり、それを忘れないように資料を集め、記憶をつなぎ、それらを展示している資料館で、博物館相当施設(博物館法第31条)に指定されている施設です。戦争の実相には、加害と被害があり、ピースあいちでは、両方とも「歴史的な客観性と統合性」をもって展示されています。
これは、熱心で優れた研究者の協力を得られたことで実現できました。
■それは戦争を理解する上でとても重要なことですね。他にも何かありますか。
鈴木:人類の紛争と平和の歩みと「現代の戦争と平和」の問題も表現されています。
ピースあいちの設立にあたり中心となって活動された野間美喜子先生が、「ピースあいちの原動力は80年代の護憲運動であった」と述べられていますが、護憲のための研究と広報も大切だと思います。平和憲法を守るためにも、戦争の実相を今の世代の人たちに知ってもらうことができる施設であると考えています。
■なるほど。ところで、鈴木会員はピースあいちの設立にも関与しておられるとお聞きしております。鈴木会員は終戦直後のお生まれですが、終戦間もない時期を過ごされて、戦争についてどのような体験や思いがありますか。
鈴木:私は昭和20年に生まれました。この年に生まれた私達は、父親が出兵しなかったから生まれてこられた子供達です。小中学校の生徒数は極端に少ない学年で、親の戦争被害者は少なく、アメリカから援助された脱脂粉乳で育った世代です。
私は三河山間部足助の田舎で生まれ育ったため、戦災孤児に会っていません。ただ、お祭り等のとき、傷痍軍人の生活費の募金をよく見かけましたし、戦災で行方不明となった人の消息を尋ねるラジオ放送を耳にしたりもしていました。蒲郡に海水浴か潮干狩りに行ったとき、進駐軍の兵隊がホテルのプールで若い日本人の女性と遊んでいるのを見た記憶があります。「二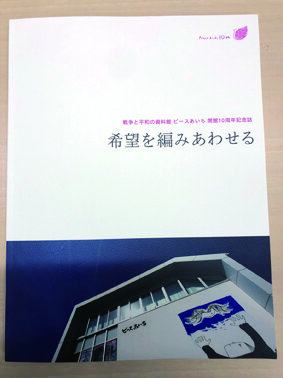 等兵物語」シリーズという映画があって、軍隊の階級制が滑稽に描かれていてとても面白く見ていましたが、軍隊内部はひどく非人間的だなあと感じ、つくづく徴兵制がない時代に生まれてよかったと思った記憶があります。また、「原爆の子」という映画を見に行ったときに、気持ちが悪くなり、見ていられなくなったことを覚えています。私の幼少期は、周囲から、二度と戦争は繰り返さないという風潮や平和への強い願いを感じていました。敗戦で打ちひしがれていたというよりは、新しい社会を築いていくという希望に満ちていた感じがしていました。そのような環境が、私の不戦、反戦の思想に与えた影響は大きかったと思います。
等兵物語」シリーズという映画があって、軍隊の階級制が滑稽に描かれていてとても面白く見ていましたが、軍隊内部はひどく非人間的だなあと感じ、つくづく徴兵制がない時代に生まれてよかったと思った記憶があります。また、「原爆の子」という映画を見に行ったときに、気持ちが悪くなり、見ていられなくなったことを覚えています。私の幼少期は、周囲から、二度と戦争は繰り返さないという風潮や平和への強い願いを感じていました。敗戦で打ちひしがれていたというよりは、新しい社会を築いていくという希望に満ちていた感じがしていました。そのような環境が、私の不戦、反戦の思想に与えた影響は大きかったと思います。
■鈴木会員が東京大学に在学中のときは学生運動等が盛んな時期だったようですが、鈴木会員はどのようなことをされていましたか。
鈴木:大学生だった昭和40年代は、政治の季節でした。私立大学では学費値上げ反対の学生運動が盛んでした。ベトナム反戦、紀元節復活反対や沖縄返還に多くの学生が強い関心を寄せて行動しました。世界中で学生運動が燃え盛っていました。アメリカでも反戦フォークが流行り、モハメッド・アリの兵役拒否が喝采を浴びました。
東大紛争は、無給制反対の医学部の学生が安田講堂を占拠した昭和43年5月に始まり、翌年1月の機動隊導入で占拠学生(ほとんど他大学の学生)の排除まで続きました。加えて、司法修習生7名の懲戒処分、宮本康昭裁判官の再任拒否、裁判介入の平賀書簡、最高裁の青法協裁判官の脱会勧告等が起きて司法反動の時代と言われ、日弁連も強い反対運動を展開していました。
私自身は、過激な活動をした新左翼ではありませんでしたが、学生自治会のクラス代表に選ばれたため、学生運動に関わらざるを得ない立場でした。
また、大学の頃から先輩の指導で憲法裁判の研究会等をやり、再任拒否をされた宮本裁判官を呼んだり、学園祭で職業病の研究発表をやったりしました。
いずれにしても、昭和40年代の反戦平和と司法反動の問題が、その後の私の弁護士生活に大きく影響を与えていると思います。
■司法修習生や弁護士になってから、戦争や平和といった面での取組はどういったことをされてきましたか。
鈴木:司法修習生のときから、護憲平和と人権擁護の活動を行う青法協の会員でした。
弁護士になって司法問題特別対策委員会に入りました。委員長は鶴見恒夫先生でした。
また、昭和48年の司法修習生のときに新幹線公害訴訟の準備に関わり、第1審の終わりごろまで弁護団の一員でした。塵肺訴訟の名古屋弁護団の代表もやり、野間先生と一緒に金大中氏の救出運動もやりました。
1982年の中曽根内閣でにわかに改憲の動きが強まったのですが、その改憲に向けた動きが出始めた1981年には、野間先生、冨島照男先生、加藤隆一郎会員、花井増實先生を中心に183人の弁護士と護憲の研究会を作りました(名古屋憲法問題研究会)。学者も数多く加わり支援してくれ、頻繁に講師を呼んで勉強会を行いました。その成果が「平和と憲法を考える」(日本評論社1982年出版)、「負けるな日本国憲法」(同時代社1984年出版)でした。演劇版日本国憲法「今日私はリンゴの木を植える」の上演(1983年)、「五月の歌」市民合唱の上演(1985年)、「原爆の図展」の開催(1986年)、国連に向けた原水爆禁止運動にも関わりました。
■後にピースあいち創設のキーパーソンとなる野間先生との関わりはどういったものでしょうか。
鈴木:野間先生は、公害事件や医療過誤事件のほか、金大中救出運動(名古屋の弁護士214名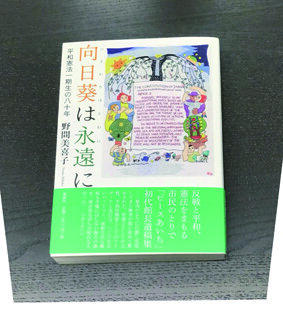 が賛同)等も行っていました。また、青法協や国際法律家協会の世界大会に参加され、護憲平和と核兵器禁止の運動にも力を入れてこられました。1990年代には「司法改革」批判の運動を担ってこられました。
が賛同)等も行っていました。また、青法協や国際法律家協会の世界大会に参加され、護憲平和と核兵器禁止の運動にも力を入れてこられました。1990年代には「司法改革」批判の運動を担ってこられました。
野間先生は昭和20年の津の空襲を経験され、その戦争体験が護憲と平和に対する強力な原動力となっていたように思います。野間先生は純粋で情熱の人でした。私は、昭和48年の司法修習生のとき、新幹線訴訟弁護団で野間先生を知るようになり、以後、活動をともにするようになりました。野間先生の平和運動のほとんどに付き合ってきました。「同志」だったということかなと思います。
■ピースあいちの設立や運営に携わるようになった経緯や、ピースあいちの設立にあたっての思い出や苦労話等あれば、ご教示ください。
鈴木:野間先生は、戦没者の追悼と、再び戦争をしない、そういったことを訴える施設を、公的な機関が責任をもって作るべきだという信念をお持ちでした。それを、どうしても自分が生きている間に実現しなければならないとおっしゃっていました。その信念の下、たくさんの著名人に働きかけましたし、私財を使って未来に残すべき戦争にまつわる資料を収集されていました。
1993年8月に名古屋の多くの著名人が呼びかけ人となり、「戦争メモリアルセンター建設を呼びかける会」を発足させ、愛知県・名古屋市に請願する運動を展開しました。私も呼びかけ人となりましたが、活動は、野間先生が中心でした。「苦労」は全て野間先生が背負い、私は「歴史的、理論的、精神的な支え」を務めたのかなと思います。
1994年に県議会、1995年に市議会が請願を採択し、「戦争に関する資料館調査検討委員会」が設けられました。しかし、2000年に入ると、県市の財政難を理由に、「戦争資料館建設」は目途が立たなくなりました。仕方なく、1年に1回、戦争に関する展示会(戦争展)を行うことになりました。
そうしたところ、2005年4月に突如、戦争展を見たという当時86歳の加藤たづさんという方から、名東区の土地90坪と1億円の寄付の申し出を受けたのです。加藤さんは、結婚して間もなく夫を亡くし、定年まで会社勤めをしながら、助産師や看護師の資格を取って、昼夜働いて資産を蓄えました。彼女は、その人生をかけて貯めた資産を寄付してくれるというのです。
県市に対し、加藤さんの寄付を県市が受け取って、その寄付金で戦争資料館を建設することを申し出ましたが、断られたため、民間で資料館を作ることにしました。そして2007年5月にピースあいち開館にこぎつけました。
■ピースあいちは、野間先生の情熱と、それに賛同されたたくさんの人の協力と、そのような活動に胸を打たれて寄付された加藤さんの資産があって設立に至ったのですね。設立後の運営についての苦労もおありですか。 鈴木:ピースあいちは、開館準備のときから、様々な人のボランティア活動で支えられ、理事や運営委員の他、100人近いスタッフと語り手の協力により運営されています。これはとても貴重なことです。ピースあいちの経費は年間1000万円程度ですが、人件費は全てボランティアなのでゼロです。収入は、入場料は年間250万円程度、あとは会費、賛助金、寄付金等で賄われています。会員は、本年3月現在、正会員334人、賛助会員412人です。
鈴木:ピースあいちは、開館準備のときから、様々な人のボランティア活動で支えられ、理事や運営委員の他、100人近いスタッフと語り手の協力により運営されています。これはとても貴重なことです。ピースあいちの経費は年間1000万円程度ですが、人件費は全てボランティアなのでゼロです。収入は、入場料は年間250万円程度、あとは会費、賛助金、寄付金等で賄われています。会員は、本年3月現在、正会員334人、賛助会員412人です。
ですが、ボランティア活動や寄付等に頼っているので、今と同じものを将来につなげられるかどうかは分かりません。
■ボランティアの方の中には、将来を担う若者もいらっしゃるのですか。
鈴木:若い人の参加も一定数存在します。大学の先生が学生を見学に連れてきてくれるのをきっかけに参加してくれたりします。また、東邦高校は学徒動員先の工場で罹災し、約20人が犠牲になっているという経緯からピースあいちと提携関係にあり、ボランティアに参加してくれる学生もいます。
■ピースあいちでは過去の戦争を単に振り返るのみでなく、「現代の戦争と平和」も展示の主軸に掲げていらっしゃいますが、鈴木会員のこれまでの問題意識との関わりで、現在の世界情勢について、どのような所見をお持ちでしょうか。
鈴木:ロシアとウクライナの問題、イスラエルとパレスチナの問題、中国と台湾の問題等色々ありますが、根底には領土拡張問題があると思います。そういう意味では19世紀と同じようなことが起きていますが、今は覇権主義との対立構造という新しい時代に来ているようにも思います。日本の護憲が、一国平和主義と言われ、トランプのアメリカ第一主義と似ている感じになります。これにどう答えるかは難しい問題です。自衛権や軍事費を否定できない状況ですが、どうやって歯止めをかけるかということが問題です。私は、たとえ一国平和主義だと言われても、軍事費にお金を使わないことのほうが逆に現実路線だと思っています。中国や北朝鮮が、平和憲法を持つ日本を本当に占領するとは思わないし、中国が本気で日本と戦争するとも思えません。
■鈴木会員がNPO法人の理事長に就任することになった経緯を教えてください。
鈴木:理事長は、満州からの引き揚げを経験された森嶌昭夫先生(名古屋大学と上智大学の民法学者)が、初代として長い間務めて下さいました。次に野間先生が館長から理事長になられました。野間先生がとても惜しまれつつも2020年3月に亡くなられ、理事や運営委員をやって来た私におはちが回ってきました。
私が理事長になったのは、著名な人の多くが亡くなられたり、老齢であったりしたからです。野間先生の遺言のようなこともありました。今の館長の宮原さんと事務局長の赤澤さんからも頼まれ、引き受けることとしました。
■鈴木会員のNPO法人での役割はどのようなものですか。
鈴木:私は長い間、理事だけでなく運営委員にもなっていました。会合が月に2回開催され、各種の企画や、展示のチェック等を行います。現在も理事長兼運営委員として、運営委員の活動も行っています。
■NPO法人が当会から人権賞(令和元年度(R2.2))を授与されたことは、どのような意義があったでしょうか。
鈴木:当会の人権賞は、野間先生と多くのスタッフに与えられたものと考えています。励みにもなりましたし、当会が平和と憲法の問題に力を入れていることのアピールにもなったと思います。受賞が決まったときには野間先生は体調を崩されており、私が授賞式に出席しましたが、野間先生が授賞式に出られるタイミングで授賞できていたらなおよかったと思います。
■ピースあいちの運営・あり方について、今後の展望をご教示ください。
鈴木:ピースあいちには、多くの弁護士が会員になってくれています(正会員22人)。纐纈和義会員には理事になって貰い、イラク支援をしている小野万里子会員や引き揚げ経験のある那須國宏会員の支援も受け、杉浦宇子会員や松本篤周会員には研究会の講師になって貰っています。今後とも、弁護士の皆さんの経済的援助と護憲・人権の専門家としての知識をもって協力をお願いしたいと思います。
ピースあいちは、県や市の正式行事として、学校に呼ばれて戦争体験談の語り手の派遣をしています。戦争体験者が次第に減っていき、やがていなくなってしまうので、語り手の承継も行っています。本当はもう少し憲法擁護と軍拡反対のための活動もするべきだとも思っていますが、手一杯というのが本音のところです。
■NPO法人の理事長として、弁護士として、会員にどういったことを伝えたいですか。
鈴木:今の若い人たちが憲法や平和についてどう思っているかを聞きたいです。聞いたうえで、私自身も考えたり話したりしたいと思っています。
私は、憲法前文と第9条は、崇高な目標であり、軍拡を抑制する力があるので、掲げ続けるべきだと思います。護憲と軍事費を削減し国民の生活に回すことを訴えることが、この時代に生まれ、恵まれて生きられた者の「譲れない信条と信念」ということです。
■平和の恩恵を受けている我々は、憲法と平和について真剣に考えなければならないと思いました。本日は大変貴重なお話をお聞かせいただき本当にありがとうございました。
----------------------------------------------
ピースあいちでは、現在ご入会、ご寄付を受け付けています。詳細はこちらから。


