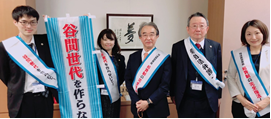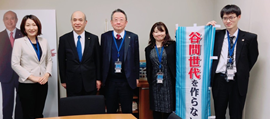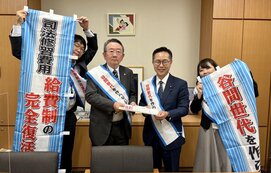司法修習生への経済的保証
司法試験の合格後、裁判官、検察官、弁護士になるために行う約1年間の研修を司法修習といいます。
この司法修習を行っている「司法修習生」は約1年間、平日の午前9時頃から午後5時頃まで研修を受けており、通常の会社員同様の生活を送っています。そして、「修習専念義務」といういわゆる兼業の禁止が義務付けられており、休日や平日の時間外のアルバイトについても原則禁止されています。
そのため、司法修習生は、かつては準公務員として給料が支払われていましたが(給費制度)、2011年度にこの制度が廃止され、無給となりました。
2017年4月に再び裁判所法が改正され、司法修習生に対して一定の給付がなされるようになりましたが、月額13万5000円と、以前の給付水準には達していないばかりか、毎日スーツを着て裁判所、検察庁、法律事務所においてフルタイムの修習に専念しながら生活するには給付が不十分な状況です。
また、2017年に一定の給付がなされるまでの6年間(新65期から70期)の司法修習生(この間に司法修習を行った世代を「谷間世代」といいます)は、無給で司法修習を受けなければなりませんでした。当然無給では生活できないため、谷間世代の多くの司法修習生は国から年間約300万円を借金して生活しなければならず、何らかの給付を受けている他の世代の司法修習生に比べて、明らかに経済的な負担が大きく、不平等な状態でしたが、谷間世代に対する是正措置は未だに実現していません。
当対策本部では、院内集会(東京の永田町にある衆議院又は参議院議員会館の講堂等で行う集会)や市民集会を開催したり、議員に法律の改正を求める要請をするなどして、この問題に積極的に取り組んでいます。
谷間世代救済に向けた「基金制度」創設を!骨太の方針2025に基金構想の明記へ!
当委員会でも、給費制が廃止された2011年以降、途切れることなく議員要請を続け、この問題の是正を訴えてきました。
現在では多くの国会議員の方々にこの問題が認知され、過半数を大きく超える国会議員から、谷間世代の是正について応援のメッセージが寄せられる状態になっております。また、昨年には、日本弁護士連合会から、谷間世代是正策として、基金制度の構想が提案されました。
この基金構想とは、①国の補助金等を原資とし、谷間世代を中心とした弁護士の法律業務、公益的活動等を経済的に支援するための基金を日弁連の下に設ける。②総額約200億円。③この世代の弁護士が行う様々な法律業務、公益的活動等に対し、支援金(年間40万円×5年間を上限)を給付する。④支援金は、日弁連が対象となる会員からの申請を受け、審査を行い支給する、という内容となっています。
令和7年5月21日には、この基金制度の創設を喫緊の課題として、「谷間世代の解消のための基金制度創設を!骨太の方針2025に基金構想の明記!」と題した院内意見交換会が開催されました。
昨年開催した院内意見交換会同様、日弁連の掲げた基金構想に賛同する意見が多く寄せられましたが、今回の院内意見交換会では、与党の政策責任者である自民党の稲田朋美衆議院議員が、「骨太の方針2025に基金構想の明記しなければならない」と明言されました。
以上のような活動の結果、6月13日に閣議決定された2025年の骨太の方針には、実際に『「第二次再犯防止推進計画」に基づき、拘禁刑下の処遇拡充、保護司への支援の充実等を推進する。2025年度内に策定予定の次期犯罪被害者等基本計画に基づき、施策を強化する。内外の予防司法支援機能や総合法律支援の充実、インターネット上の人権侵害への対策強化、法曹人材の確保等の人的・物的基盤の整備を進める。(注172)外交一元化の下で法制度整備支援等の国際協力・司法外交を推進するほか、再犯防止国連準則の活用、国際仲裁の活性化、国際法務人材の育成、法令外国語訳の加速に取り組む。』『注172 法教育の推進、公益的活動を担う若手・中堅法曹の活動領域の拡大に向けた必要な支援の検討を含む。』(33頁下部~34頁)と、上記基金構想を想定した記載がなされました。これにより谷間世代の救済の実現が大きく前進したことを確信しています。
(院内集会の様子)


(安江伸夫議員と) (伊藤孝恵議員と)
(大嶽理恵議員と) (工藤彰三議員と)
(近藤昭一議員と) (丹野みどり議員と)
(柘植芳文議員と) (藤原規真議員と)
(古川元久議員と) (松田功議員と)

(本村伸子議員と)
おわりに
最後の谷間世代である70期の貸与金の返済が昨年から開始され、最初の谷間世代に当たる65期は今年7回目の返済が目前に迫っております。多くの谷間世代が、30代40代というライフイベントの多い働き盛りの世代に集中して返済を行うこととなりますので、谷間世代とそうでない世代との間の経済的格差は着実に開いている状況にあります。
現在の良い流れを止めることなく、谷間世代の救済を一刻も早く実現すべく、当対策本部はこれからも活動を行ってまいります。