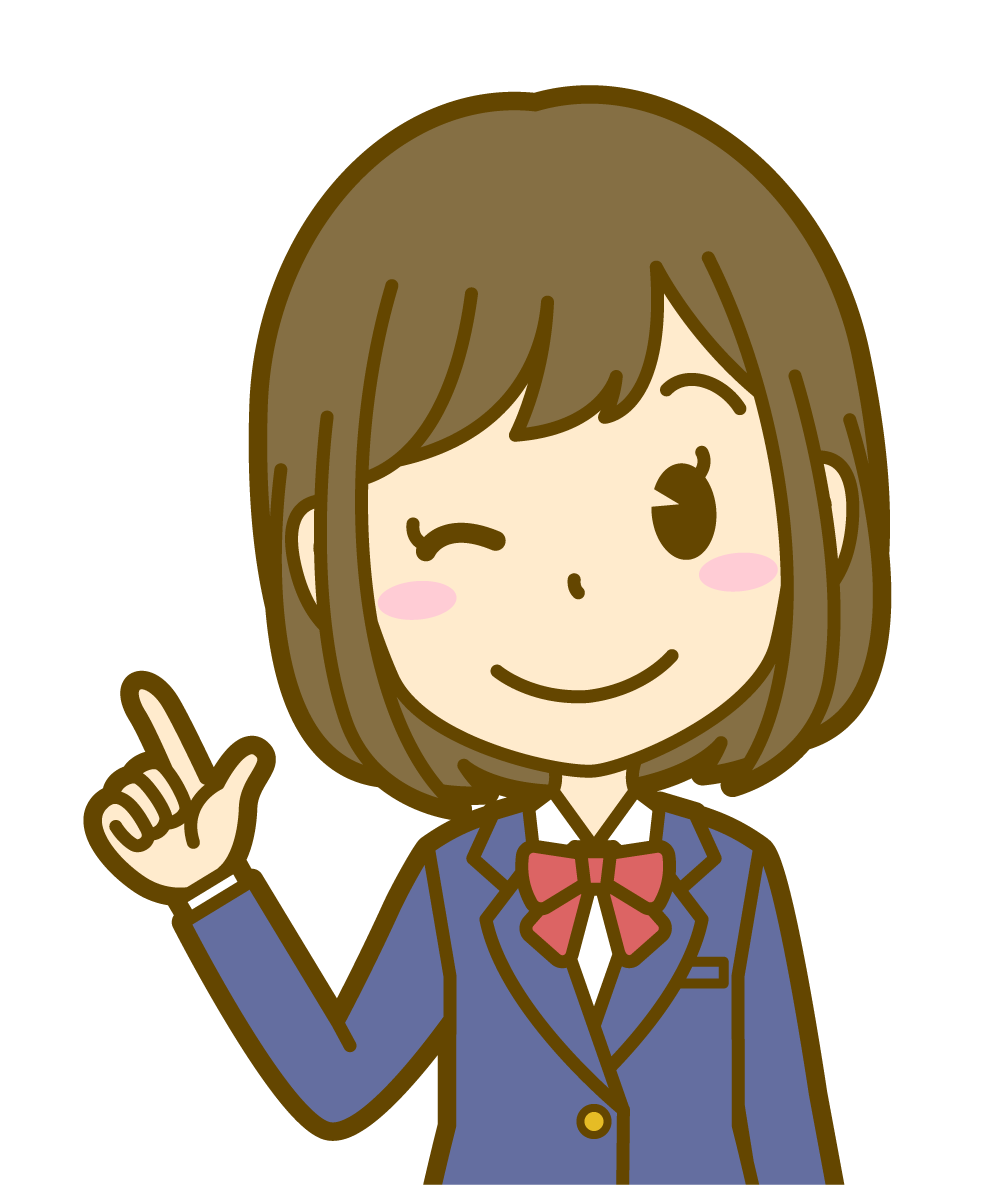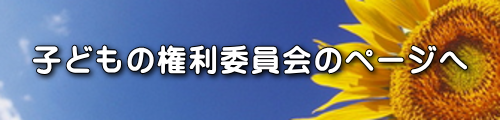「子どもの手続代理人」とは?
家庭裁判所では、離婚するときに未成年の子どもの親権者を父母のどちらかに決める、別居している親と子どもの面会に関する条件を決めるなどの手続が行われています。
これらの手続は父母の間で行われますが、そこで決まったことが子どもに与える影響は、とても大きなものです。
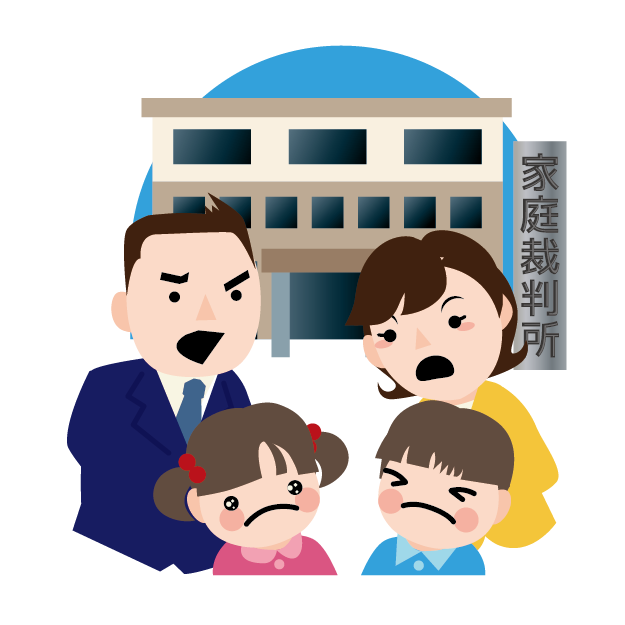
そのため、子ども自身が「自分の意見を聞いてほしい。」と思うこともあるでしょう。
また、子どもと一緒に暮らしていない親からすると、「子どもがどう思っているのか?」、「子どもの本心を知りたい。」と思うこともあるでしょう。
一方、子どもと一緒に暮らしている親からすると、「子どもが自分に気兼ねして本当の気持ちを話せていないのではないか?」、あるいは、「子どもは本心を話しているのに、相手に信じてもらえないのではないか?」など、不安に思うこともあるでしょう。
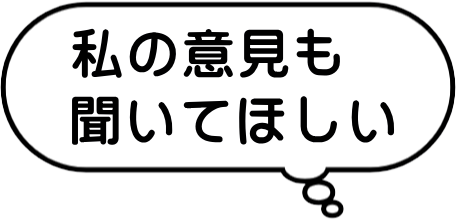 |
||
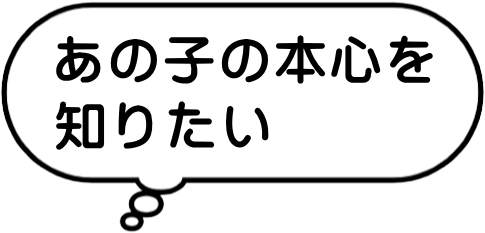 |
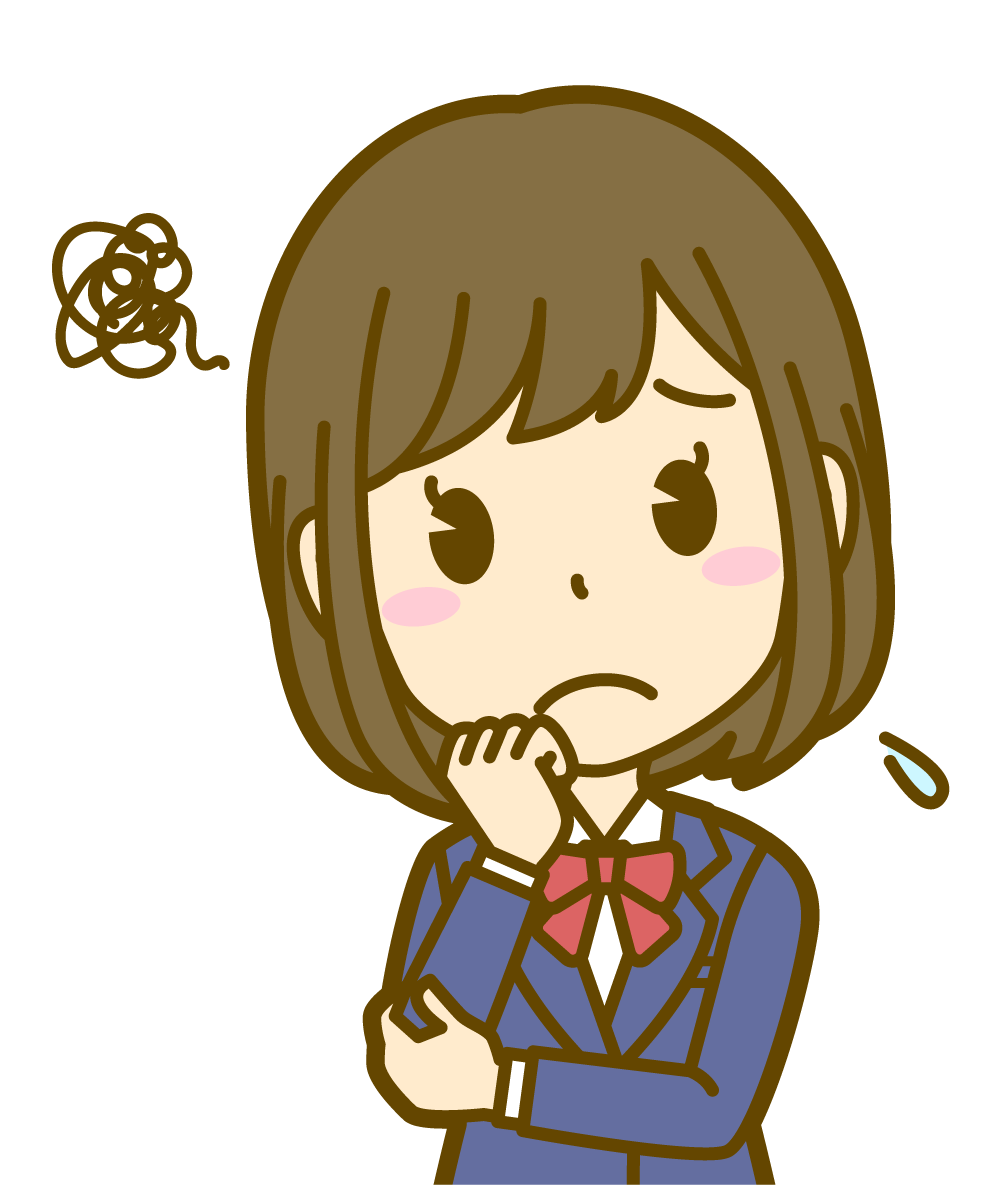 |
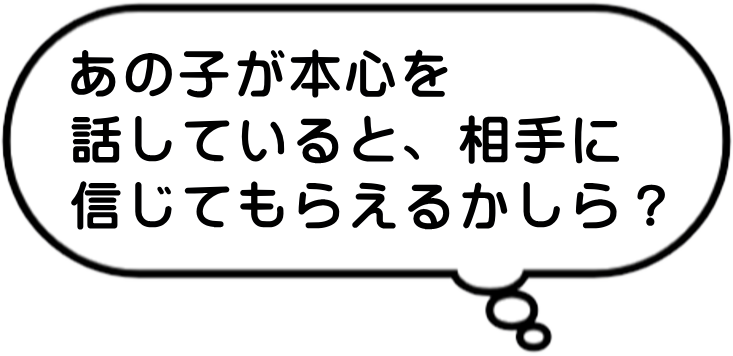 |
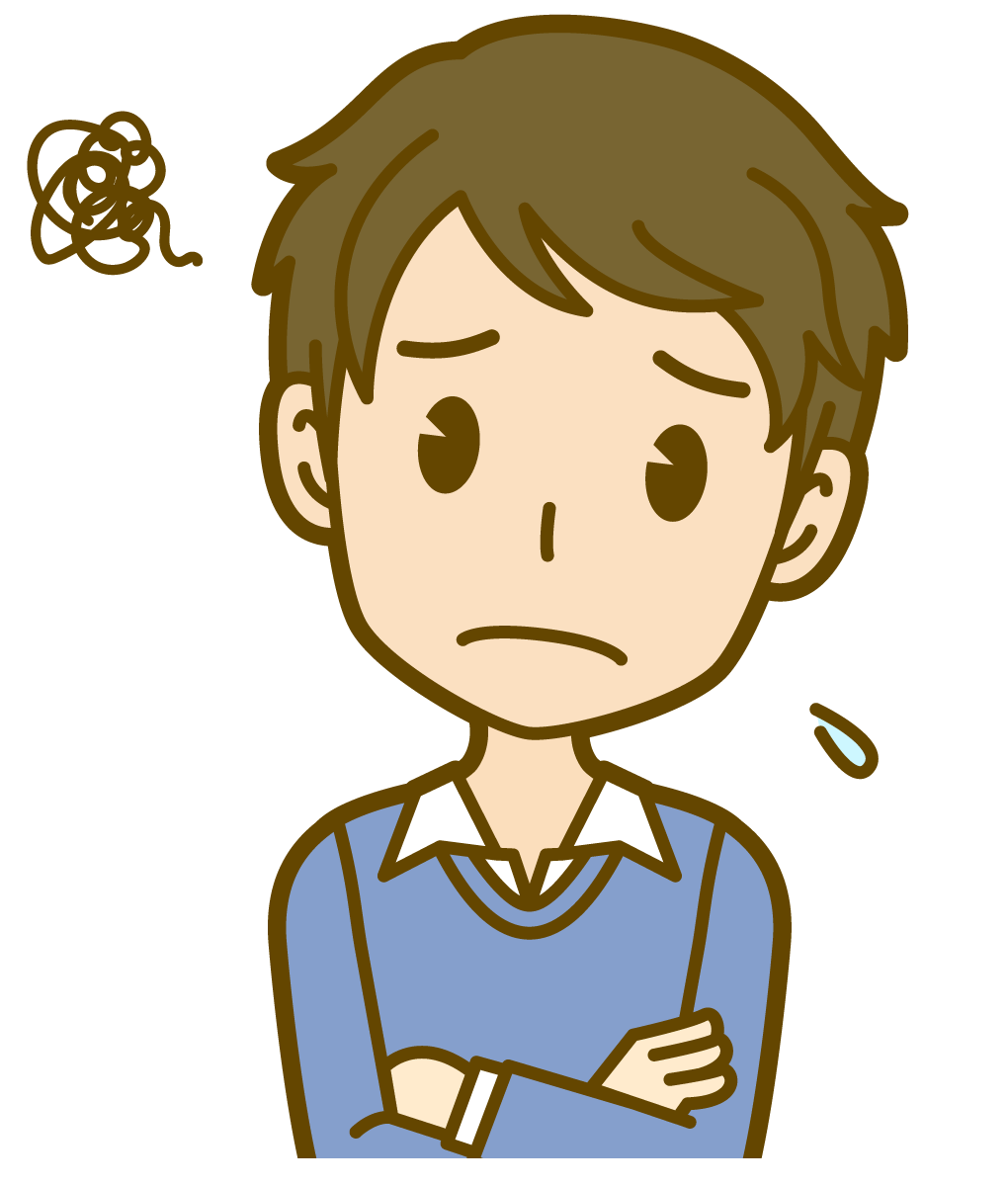 |
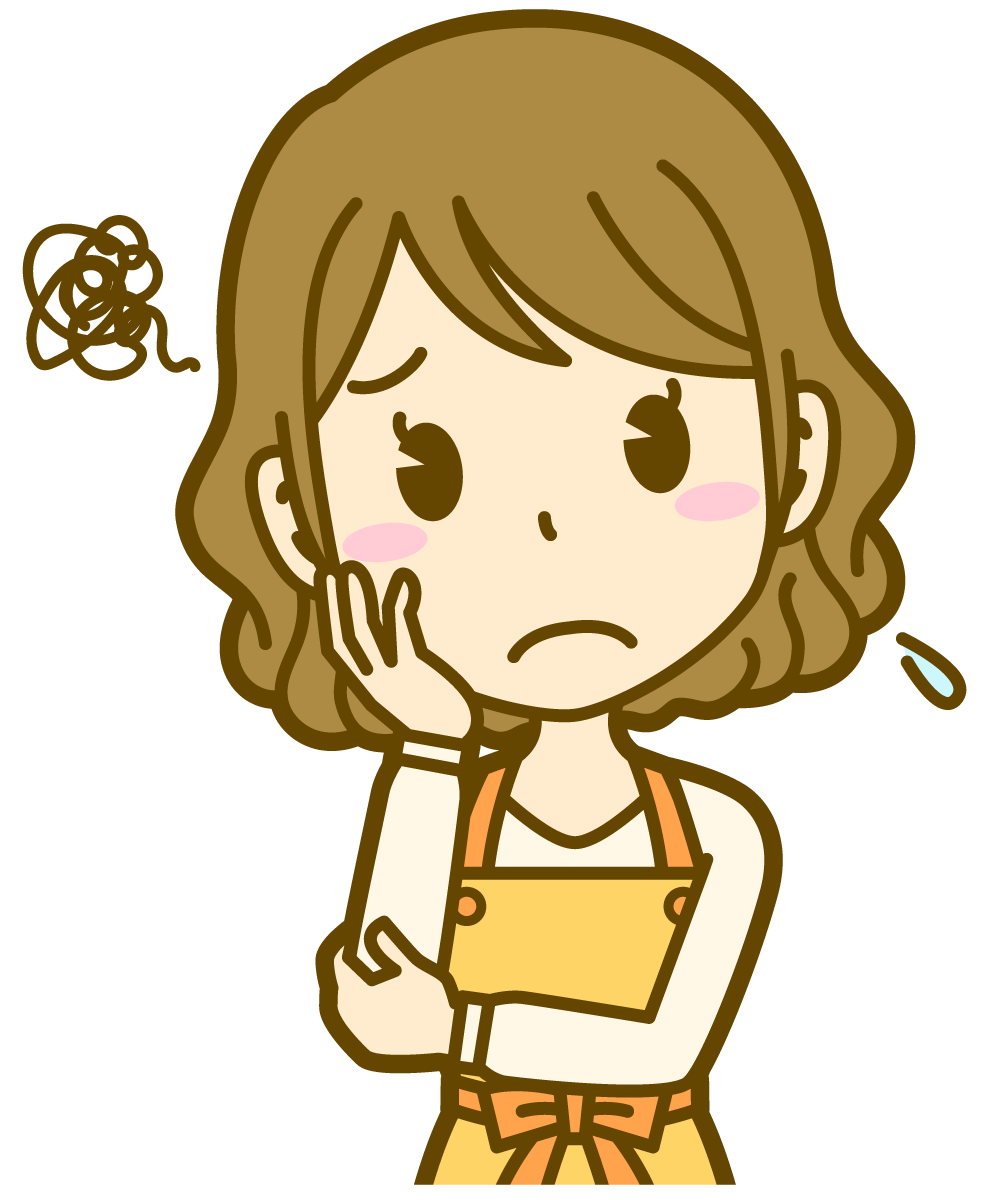 |
そのようなとき、子どもが家庭裁判所の手続に参加でき、子どものための代理人弁護士を選んでもらうことができる「子どもの手続代理人」という制度があります。
子どもの手続代理人は、父母どちらの味方でもなく、あくまでも子どもだけの代理人として、子どもに寄り添って、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で子どもの意向を聞きながら裁判所や父母へ届けます。
子どもは、父母が何についてどのような手続をしているのかよく分からないまま、不安に感じていることも多くあります。子どもの手続代理人は、父母が行っている手続の内容や、子どもが手続に参加するに当たって必要な情報、子どもの生活に関する情報を、子どもに分かりやすい言葉で説明し、子どもの相談に乗ったり、子どもに寄り添いながら一緒に考えたりします。その上で、子どもの意見や気持ちを家庭裁判所の手続の中で子どもの意向を聞きながら裁判所や父母へ届けます。
このように、子どもの手続代理人は、子どもが手続に参加して自分の意見を表明する権利(子どもの意見表明権、こども基本法3条3号、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)12条)を守り、実現するお手伝いをします。
<参考>
外務省の「児童の権利に関する条約」全文のページへのリンク
子どもの手続代理人の活動内容
子どもの手続代理人は、具体的には、次のような活動を行います。
- 子どもと面談して、子どものことをよく知り、子どもの疑問に丁寧に答えて、子どもが自分の意見を伝えやすい関係を作ります。
- 子どもが自分の意見を決めたら、書面などで裁判所に伝えるとともに、家庭裁判所の手続期日に出席して、必要に応じて子どもの意見を説明します。
- 子どもの気持ちを尊重しつつ、これまでの家庭裁判所の手続の経過を踏まえて、子どもの手続代理人から、子どもの利益を中心とした調停案を提案することもあります。
- 家庭裁判所の手続が行われた後には、子どもにその内容を分かりやすく説明し、子どもの疑問にも答えます。
こうした活動に当たっては、父母に協力をお願いする場合もあります。
子どもの手続代理人の費用について
子どもの手続代理人を担当した弁護士の費用(報酬)は、多くの場合、子どもは支払うことができないので、父母が支払うこととされています。
家庭裁判所の手続が終了したら、裁判所が子どもの手続代理人の報酬額を決定しますので、裁判所の決定に従って父母が報酬を支払うことになります。
父母が経済的理由から費用を負担することが難しい場合は、子どもが日本弁護士連合会(日弁連)の「子どもに対する法律援助」を利用することもできます。「子どもに対する法律援助」を利用した場合、子どもは費用を負担する必要がありません。
<参考>
日弁連の「法律援助事業」のページへのリンク
(「子どもに対する法律援助」は、日弁連の「法律援助事業」の一つです。)
子どもの手続代理人を希望する場合は
現在、家庭裁判所で離婚、面会交流などの手続をされていて、子どもの手続代理人が必要かもしれないとお考えの方は、手続を依頼している代理人弁護士がいれば、その弁護士にご相談ください。
依頼している代理人弁護士がいないなど、相談する弁護士がいない場合は、愛知県弁護士会 法律相談センターが実施している子どもの人権相談でご相談ください(相談料は無料です。相談方法など、詳しくは、リンク先をご覧ください。)。