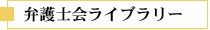| 1、 |
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察等に関する法律」
(以下「医療観察法」と略する)とは |
|
| (1) |
同法は、平成15年7月に成立し、附則で、2年以内の施行が決められていることから、遅くとも今年の7月には、施行されることになっている法律である。 |
| (2) |
平成12年に成年後見制度が全面的に改正され、ほぼ同時期に介護保険法が新設され、また各種社会福祉法が改正された時に、民法と福祉法の「混合」「連携」「架橋」が始まったと例えられた。今回の医療観察法は新たなる「刑法」と福祉法の「混合」「連携」「架橋」ともいいうるものである一方で、「強制入院」等の形で重大な権利侵害の可能性を含むものでもある。 |
|
| 2、 |
弁護士が何故関心を持つ必要がある法律なのか |
|
| (1) |
同法は、平成15年7月に成立し、附則で、2年以内の施行が決められていることから、遅くとも今年の7月には、施行されることになっている法律である。
まず、最初にその点を概観すると、
第1に、従来の刑事弁護においては、例えば、被疑者・被告人が殺人を犯した場合において、弁護人として、本人に刑事責任能力が無いと思われる場合には、無罪を主張し、それが受け入れられ確定すれば、一般にはその段階で弁護人の仕事は終了した。しかしながら、今後は、このような場合には、検察官が申立をなし、新たな法的手続きが開始され、「裁判所の決定」による「強制入院」(裁判所の決定がない限り退院できない)等が必要なのかどうかが裁判所において判断されるということになる。
第2に、この新たな手続きは、付添人という新たな弁護士の活動を予定している。
そして、被告人・被疑者(以下対象者という)が私選付添人を選任できない場合には、いわゆる国選付添人が選任されることになる(但し、国選付添人は、初回の強制入院に限定される)。
第3に、この対象者が裁判所により退院を許可され、あるいは通院に切り替わった時の弁護士としてのフォローの活動も必要となる。対象者の症状が改善されたにもかかわらず、その対象者が地域で生活していくためには、種々の障害が予想される。新たに創設された社会復帰調整官(精神保健福祉士であり各県に1人以上選任される国家公務員)と共に対象者に対する法的アドバイスも弁護士として必要となる。 |
| (2) |
「刑事弁護の延長としての位置づけ」と共に「精神障害者の治療・処遇としての位置づけ」を併せ持つ法律であり、両分野のいずれかに関わってきた弁護士は勿論のこと、それ以外の多数の弁護士も新たに関わる必要がある。 |
|
| 3、 |
医療観察法の制度概要について |
| |
| (1) |
医療観察法は、重大な他害行為(殺人・強盗・放火・強制わいせつ・強姦・傷害の中の一部)を行った者が、心神喪失又は心神耗弱を理由として、不起訴又は無罪若しくは執行猶予付の判決を受けた場合に、「行為をおこなった際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために」この法律による医療を受けさせるための法律である。 |
| (2) |
医療を受けさせる必要があるかどうかについては、鑑定人が2ケ月以内(3ケ月まで延長可能)に鑑定を行い、「裁判官」1名と「医師」1名の合計2名による合議体によって「強制入院」等の必要性が判断される(医師が裁判所の構成員として司法判断の一端を担うことになる)。 |
| (3) |
これらを制度の具体的活動で説明すると、例えば、「A」さんが「B」さんに重大な傷害を与えたとして逮捕された。ところが、「A」さんは、精神障害を患っていた。検察官は簡易鑑定の結果、責任能力があるとして起訴したが、裁判所において鑑定等がなされた結果、責任能力がないものとして無罪となった。その結果、検察官は、その無罪判決を確定させた上で、医療観察法による「強制入院」の申立をなした(検察官には、法制度上、除外事由のない限り原則申立の義務が課されている)。鑑定人が選任され、「強制入院」が相当であるとの鑑定書が出された。
「C」弁護士は、必要的国選付添人に選任されたが、「対象者」が今回このような行為をなしたのは従来から通院していた病院での治療を怠ったからであり、今後、その病院での治療が継続されれば、あえて「強制入院」までは必要が無いこと、「A」さんの両親が、監督の上きちっと従来の医療を受けさせます旨の意見を述べた。さて、裁判所の結論は?ということになる。 |
|
| 4、 |
弁護士の役割 |
|
| (1) |
被疑者が心神喪失状態であったことを理由として、不起訴になった事案の場合、「果してその被疑者が本当にその罪を犯していたのか」どうかについては不明確なままとなっていた。ところが、医療観察法の適用を求められる場合には「その罪」を犯していたことが前提となる。即ち、医療観察法は、「犯罪行為を犯した者が、責任論レベルにおいて刑事責任能力がないこと理由にして無罪等になった場合」に限り、その対象者としているからである。対象行為の存否の確定は刑事弁護と同様に弁護士の重大な活動となる。
例えば、構成要件的事実はあるものの、正当防衛等の違法性阻却事由の疑いのある場合には、対象行為の存在を争うことになる(日弁連等で問題となっているケ−スは、例えば、精神障害者援助施設内において、同室内の一方が他方をナイフで刺したというような場合、被害者の立場の人間が加害者の立場の人間に先に危害行為を行ったかもしれない、この場合は正当防衛もありうる等である)。 |
| (2) |
対象者が犯罪行為を犯したことが事実であったとしても、対象者を「強制入院」させる必要性があるかどうかの判断にも弁護士はかかわることになる。患者の意思に基づかない「強制入院」「強制治療」は対象者の人権を大きく制限するものであるから、「不必要な強制入院・医療」に対しては、チェックすることが必要となる。 |
|
| 5、 |
弁護士会の取り組み |
|
| (1) |
名古屋弁護士会としては、平成16年12月、平成17年2月の2回にわたり研修会を設け、弁護士からの法の概要説明及び医療及び福祉関係者からのシステムの説明及び問題点の指摘の機会を得た。
今後とも研修等を継続し、会員全員の理解を進めていく必要があると思われる。 |
| (2) |
厚生労働省及び法務省の試算によれば、愛知県内において、年間30名程度の対象者が予定されているとのことである。従って、当会においても、これを踏まえた付添人候補者名簿の策定が不可欠となっている。 |
| (3) |
医療観察法の下では「不当な強制入院」をチェックする活動が必要である。この活動のためには、精神科医師の協力が不可欠である。会として精神科医師の継続的な協力システムを早急に構築することが必要である。 |
| (4) |
本年3月より、医療観察法に関して名古屋地裁・名古屋地検・当会の3者間での運営協議が開始され、その中で種々の課題が検討される予定である。 |
|