|
5.毒芋で死す
第一二中隊の命令受領者はI軍曹であった。乙幹出身の気の弱い、およそ軍人らしからぬ男であった。性温厚で、私は彼の怒った顔を見たことがない。命令受領者は直接的に戦斗をしないから、その意味においては適任であったかも知れぬ。彼には分隊を指揮する能力も資質もおよそなかったからである。私はガ島作戦で彼を補佐する関係にあったので、ガ島で彼が不慮の死を遂げるまで終始行動を共にしていた。平時内地におれば立派な紳士として通用し得たかも知れぬ。しかし戦争は彼をして不遇な軍人たらしめたのである。しかも最も苛烈を極めたガ島作戦は何人をも窮乏のどん底に陥し入れ、人間の性格すら変えた非情冷酷な修羅場であったのである。
上陸半月にして既に食糧は窮迫を告げ、弾に斃れる者の外、病に斃れるもの続出し、我が中隊でも毎日数名の死者を数えていた。この頃になって、生きて再び内地に帰還できるというような考えは全然脳裡から去っていた。絶望のみが我々の頭を支配していた。朝になれば「まだ生きていたのか」、夕になれば「今日も生き延びたか」との感を深くし、一日々々が正に死との対決であったのである。
勇川の右岸の台上は砲兵台と名付けられていた。この地点に達する谷間には大きな濃緑色の葉をした一見里芋のような野生の植物が林立していたのが見られた。普通内地の里芋の葉は稍々(やや)頭を下げている格好しているのだが、この葉は直立不動の姿で恰も大蛇が鎌首をもたげたような、見るからに不気味な様相を呈していた。これが毒芋であったのだ。
空腹に堪えかねていたときであったから食べられるものならどんな物でも食べる状態であった。里芋の如きものを発見すれば我先きにと喰べることは人情であった。しかしこれは喰べられない毒芋であったのだ、これを喰べた者は可成りあるらしいが、運が悪かったのか、I軍曹はこれを喰べると間もなく、唇は紫色化し、嘔吐苦悶を始め、拳は虚空を掴みつつ、この世を去ったのである。全くあっけない最後であった。
名誉の戦死を伝えられた彼の死はかくの如きものであったのである。戦死という美名の下には、かかる真実がかくされているのである。私は戦場の実相を知って貰うべく敢えてこのことを書き記すのである。I軍曹に似たような死は他にも沢山あり、このことは随所に触れることになろう。あたら青春をこの地に散らしめた彼の遺骸を埋め、遺品として彼が愛用した図嚢(ずのう)と軍刀は私が引継いだ。毒芋による死は痛くショックを与え、軍も毒芋を喰べることを禁止する通達を出した位であった。予期もしない出来事で今だに記憶が生々しい。I軍曹の死は考えようによってはまだ幸せであったかも知れぬ。I軍曹の死はガ島上陸より比較的初期の出来事であったからである。その後撤退するまでの筆舌を絶する辛苦苛烈非情を経験しなかったからである。彼は人間の醜さ、戦斗の極限を経ず、まだ死体を埋葬し得る余裕があり、軍も狂気じみていない時に死んだからである。彼の精神は荒廃していなかったからである。
人間を人間として扱い得ない状態となると、人間であるが故に、余計に悲惨である。死体の上で小休止し、死体を暴いて遺品を漁る姿はこの世の地獄といわずして何をか云わん。噫々(ああ)人間も遂には幽鬼と化したものならん。
6.中隊長の死
我々兵隊にとっては、敵状がどうなっているのか、我が軍が如何なる戦斗配備にあるのか、全然判らず、唯命ぜられるままに進み、命ぜられるままに穴を堀り、戦場の発展と関係なき意識の下に生き、そして死んでいったのである。
その生き、死ぬことは極く身近かな所に起こる限りにおいて意識し、それが全戦斗の如何なる位置ないし価値があるのか全然判っていないのである。このことは驚くべき事である。私はI軍曹が斃れ、C軍曹が死に、その後の命令受領者となり、その為に若干ながら戦斗の概要を把握する地位になってから、初めて自己のそしてその所属する中隊ないし部隊の戦斗態勢を認識した位である。それもごく一部においてである。しかし私は中隊の戦斗詳報を纏めていたり、給与係を担当したりしていた関係上比較的中隊の事情に通じていたことは否定できない。
我が中隊長は陸士53期(と記憶する)出身のK中尉である。典型的軍人である。心身共に鍛練された帝国軍人の権化の如き男である。年は22才位、色は稍々黒く背は余り高くなく威丈夫という風態ではない。部下には無理を強いることなく、若き指揮官として十分尊敬し得る男である。勇猛にして果敢、責任観念強く、流石、陸軍の華といわれた陸士出身だけのことはある。幹候出身の将校とはその精神において格段の差がある。
或る日、K中隊長は敵状及び中隊の戦斗拠点を偵察すべく指揮班の下士官、兵6名を連れて境台土に前進した。折り柄降りそそぐ敵弾の中を勇敢にも先頭に立ち前進を続けた。1本の大きな樹陰に寄って双眼鏡を手に敵状を偵察していたとき耳をつんざく轟音と共に落ちた迫撃砲の直撃弾を受け、K中隊長は全身破片創、一諸にいた部下は全員戦死、我が中隊にとっては一大痛棒であった。K中隊長は直ちに担架に運ばれて大隊本部の位置まで後退したが、全身破片創のため至る所から血が吹き、虫の息で意識不明のまま、手の施しようもなく絶命した。全く華々しき立派な戦死であった。
我が中隊は不幸にも建制部隊である第三大隊より離れ、第一大隊では最右翼の前線を担当させられ、敵前に一番近く、危険度の最も高い地点にあった。このことは配属中隊の悲劇でもあった。しかし若き指揮者は責任感旺盛にしてよくその任務を完遂したのである。
中隊長を失った中隊が如何に悲惨であるかは経験のない方には判らないだろうが、何かにつけて他中隊より軽視され、割の悪い任務につかされることが屡々(しばしば)ある。このことは後にも触れるであろう。
中隊長を失った中隊は柱石のない家の如く、火の消えたようなものである。意気の挙らざること夥しい。代理の中隊長が着任しても以前の士気は盛り上らない。
K中隊長はかって、南支において将校斥候に赴き、(私もこれに参加したが)暁闇をついて敵陣に突入し、慌てふためいて逃げる敵兵を求めて抜刀したところ敵の銃身に当り、その反動で軍刀を敵の壕の中へ落し、これを拾いに行ったことがある。このとき私は彼を掩護していたが、全く笑いの止まらぬ一齣(ひとこま)であった。
しかし彼は敵をあなどらず、且つ恐れもせず、沈着果敢な行動によりよく味方を引きしめ、年若き指揮官として立派な軍人であったことは否定し得ない。又一般人としても恐らく人の上に立つ人物であったであろうということも疑わない。
今でも惜しい中隊長を失ったものであると思っている。
7.蟻の巣を食う
上陸後1カ月以上経た頃になると、戦況はやや膠着状態となったが、その間でも敵は間断なく執拗に銃弾を打ち込み、毎日幾人かの戦死者を出していたが、我々もガ島の戦場に慣れ、余り恐怖も感じなくなっていた。丁度我々がガ島に上陸直後敗残兵を見たときに感じたことが、今自らの身の上に同様の変化を生じていたのである。相変らず空腹であることに変りはなく、軍から支給される米は1日僅か100瓦(グラム)、副食はなく、唯少量の粉味噌が与えられるのみである。これで戦斗をせよという方がどだい無理な話である。だから暇があれば食べられるものを求めて戦場を彷徨した。水源地に内地の蕗(ふき)に似たような野生の茎があってその根元が小さな球根になっていた。これをどれ程喰べたか知らぬ。ただゆでて何も調味品がないのでそのまま喰べるのであるが、それがどれだけ救いとなっていたかは想像を絶するところである。これもなくなってしまった。又パパイヤの幹が喰べられることもこの時初めて知った。丁度味のない大根を喰べるようであった。これもなくなってしまった。喰べられるものは皆喰べた。今から考えるとあんな物が食物となるとは到底想像も及ばない。
海岸へ行くと椰子の実やエビガニ等があったらしいが、我々前線部隊は海岸ヘ行くことは全然なかったのでその恩恵には浴さなかった。しかしそれを採るにも命がけであったようだ。海岸線は敵が始終爆撃したり、砲撃したりしていたからだ。2尺位(約60センチ)のトカゲを見掛けたことがあるが、足が速くて遂に口中に入れることは出来なかった。物の本にはその肉は美味である旨記されていたが、惜しいかなその功徳には預かれなかった。昼間は火煙が出せないので、夜になって暗くなる頃、敵の銃音も止み、漸やく身体が没する程度の深さの壕の中の炊事が始まる。飯盒の底にはりつく程の少量の食事を採るのである。それが済むと壕の外に出て枯草の上に1枚の天幕を敷き、樹々の間にもう一つの天幕を張って露を防ぎ一夜の寝に就くのである。仲々寝つかれぬ。そこで自然と話は内地にいた頃の食物の話となる。クラブ亭のビフテキはうまかったとか、あそこの寿司はうまかったとか。語り合って空腹を癒やしつつ、いつとはなく眠ってしまう。
朝敵弾の挨拶で目覚める。日中は命令受領に行き、これを中隊に伝達に行く。このような日課を繰り返していた。
戦局は徐々に悪化していった。戦況がよくなる条件は何一つない。制空権は完全に失い、制海権もなく、潜水艦によって辛うじて物資を搬送しているのみであるから、凡そその状況は判る。我々は前線で敵陣と対峙した儘、一歩の前進も許されなかった。唯夜に入ると少数の兵力による夜襲を試みるのがせい一杯の抵抗という所だ。後は敵のなすが儘の状態である。1発打つと、お釣りが30発も来てはとてもお話にならぬ。なるべく消耗を少くするに限る。
このような明け暮れをしていたとき、野生の植物も喰べられるものは殆んど喰べ尽くしたころ、蟻の巣が喰べられるとは一大発見であつた。これは丁度人間の頭位の大きさがあって蟻の巣となっているのである。これは樹幹の中間のところにあるので登って採って来て、厚さ2糎(センチメートル)位に細かく切っておくと蟻が出て行ってしまう、これを洗ってゆでると内地のれんこんを思わすような味がある。しかし調味品がないのでその儘喰べるのだが、空腹の足しにはなる。何もないガ島でも捜せば何かしかの喰物はあるものだと感心した。このようなものが栄養とはならないので、徐々に肉体的に衰弱を加えて行った。唯気力のみは比較的旺盛であった。
8.好漢
ここで私はU上等兵(一等兵であったかも知れぬ)のことを書忘れてはならない。彼は無事生還して目下豊田市で電気商を営んでいる。
彼は15年兵で私の初年兵であるが、偶然ガ島では命令受領の伝令として私の指揮下にあったので、ガ島では行動を共にし上陸より撤退まで1日として別々に居たことはない。
しかし彼は無責任な奴で、支那に居た頃、私が分哨長で彼が哨兵として夜間の立哨をしていたとき、居眠りをし高さ5メートルもある望楼より落下し、下顎を負傷して幾針か縫ったことがあり、今尚その傷痕がある筈である。又香港作戦後九竜で10日間位警備についていたとき、私は分哨長で彼が哨兵として服務したときも、彼が動哨として立哨していたところ、交替時刻になっても交替地点に現われず、遂に他の哨兵をしてそのまま立哨させたが、当時歩哨が敵兵にさらわれるという情報も流れていたので、大いに心配しその付近を隈なく探したが仲々見付からず、夜明け時分にガレージの扉の蔭に隠くれて毛布を被って寝ていた彼を発見し、思わずビンタを十数打与えたことがある。
右のような前歴があるので私は彼に余り期待していなかった。しかし作戦となると彼は見違えるような機敏な行動力を発揮し、且つ生活力旺盛な点があり、他人にないよい面を持っていた。
彼は勇敢であり、冷静であり、よい判断力を身につけていた。戦場の兵としては好ましい男であったのだ。
射撃も上手の方であったし、銃剣術もかなりやれる方であった。唯惜しむらくはもう少し責任と自覚が欲しかった。
だが支那における私の彼に対する印象はガ島においては完全に払拭されていた。私が今日生命を永らえているのも彼の献身的努力によるところ大いに大である。その点私はいつも彼に感謝しているし、彼も亦私を大いに徳としている。私と彼との間には強い戦友の絆によって固く結ばれており、時偶遭うときも徹宵痛飲しかっての物語りに時の経つのも忘れしむる程である。
私はガ島では全然炊事をしたことはない、それは凡て彼がやってくれたのである。又種々の野生の植物を採って来たのも彼である。敵弾の最も烈しく落ちる水源地へ毎日水筒をぶら下げて水汲みに行ったのも彼である。しかしその反面私は彼に危険なる伝令には出さなかった。そのような時には私自ら行ったのである。
或る日、その日は丁度開戦記念日の12月8日の前日のことである。敵はラッキーセブンと称して平日とは異なり、猛烈なる砲弾を黎明から薄暮にかけて終日苛藉なく打ちまくった。大木があちらこちらに倒れ、戦死者は夥しい数字に上った。この朝8時頃に彼はそこらに倒れている負傷兵の水筒十幾箇を持って水汲みに行った。普通なら1時間乃至2時間位で帰ってくるのだが、その日に限って夕方4時になっても帰って来ない。私はてっきり彼も敵弾に当たって戦死したのではないかという予感に襲われた。ところが真暗闇になってから肩に水筒をぶら下げて、ぶらりぶらりと幽霊のような格好で戻って来たのには吃驚し、先ずはその無事を嬉んだものである。
彼は一寸落着いてから水筒に水を入れる時間が烈しく打つ敵弾のために普通なら5分位で1箇が済むのに、一寸入れては隠れ、また弾の合間を見計って出て来て入れるので30分以上もかかる。そんな状態であったのでこんなに遅くなったと語ってくれた。
彼は何が何でも水筒に水を入れて帰らなければ十数名の負傷兵が死んでしまうという自覚と責任が、かくも沈着果敢な行動を取らしめたものと思う。
私は彼の勇敢なその行動に対して心から敬服を感じたが、その時には口には出さず、後日その点に触れて彼の行動を賞したことがあるが、彼は既に忘れたものの如く唯微笑したに過ぎなかった。彼も亦好漢というべきか。
ガダルカナル(3)へつづく

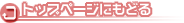
|

