|
25.死生観
伝えられるところによると、エスペランスに集結したのは、敵のルンガ飛行場に逆上陸して、最後の一戦を挑み、華々しく全員玉砕するのが目的だという。
エスペランスはガ島の西端に位し、友軍の揚陸基地となっていた。
エスペランスは敵の攻撃を殆んど受けていず、エスペランスの山は樹木が鬱蒼として繁っており、空の敵より身を遮蔽するには好適の場所となっていた。
ガ島より撤退することは軍の方針であったのだが、その事実は極く上層部の数名しか知らなかったらしい。あとの者はルンガに逆上陸して最後の一戦を交えるのだと信じていたのである。
そのような情報が流されていたが、別に命令はなかったようである。勝手に下部部隊において、そのような情報を流していたのに過ぎなかったらしい。しかし我々はそれを信じて疑わなかったのである。
死生観を何度となく朗唱させられた。
「生きて虜囚の辱しめを受けず、」
「死して罪禍の汚名を残すなかれ、」
あの荘重な名句を朝な夕なに口ずさんだ。
進むも死、退くも死、坐するも亦死。我々は既になすべきことをなしたのだ。後は死のみが待っているのだ。潔ぎよく死のう。死に対する心の整理はついている。時期こそ来たれ、もう思い残すことはない。
動けない者はここに残れ、手榴弾を持っているか、ない者には渡せ、残る者は進む者に銃を渡せ、銃のない者は竹槍を作れ、飯を炊け、急に騒々しくなる。
今夕ここを出発して敵ルンガに上陸するというのだ。我が中隊で残ることになったのはY一等兵だけだ。Yは15年兵でおとなしい奴であったが、胆力のすわっている男であった。脚気の為にもう一歩も歩けない状態になっている。愈々(いよいよ)ここを去るとき「長々お世話になりました。喜んで死んで行きます。心おきなく働いて下さい。」と悠然として顔色一つ変えず、死すること帰すがごとき立派な態度であった。我々はこの山を下って数百米(メートル)も行ったかと思うと轟音が聞こえた。Yが自決したのだなあと思い、思わず歩足を止めて彼方の山の上を見上げた。その後はもとの静寂にかえった。一路海岸に急いだ。もうあたりは暗くなっていた。海岸までは2キロ位あったろうか。ところどころに小川が流れていて転落する者もあって、そのまま帰らなかった者もあった。跨げるような川であるが急流で深かったらしい。そこへ落込んだまま追及して来なかった者があったが、そのまま前進してしまった。誰が落ちたのか判らなかったが、後で海岸で人員を調べたら1人足らない。大阪より転属して来た補充兵の男であった。彼は比較的丈夫な方で、ここまで来たのが、運悪く転落して死んでしまったものらしい。他を顧みている状況ではなかったのだ。
26.エスペランスの夜
海岸についたのは午後10時近くであったと思う。真暗なジャングルから海面を見るとキラキラと光っていて奇麗であった。今夜限りの生命だ。明日は敵陣へ突入して戦死しているであろう。真暗な海を岸辺に沿って夜の明けるまでに敵陣に辿りつかねば途中でやられてしまう。早く舟艇が来るのを待っていた。何時まで待ってもやって来ない。その内に遥か沖合で海戦が始まった様子である。
両軍の射つ弾丸が曳光を放って花火大会を見ているようだ。相当長い海戦だ。赤、青と交錯する曳光弾は全く奇麗で思わず見惚れていて時の経つのも忘れていた。
舟艇は遂に来なかった。
夜明けと共に空しく海岸より引揚げることになった。もっとも近くのシャングル内に入ったと思う。1キロに足らずの所だと思う。1日待つことになった。1日生命が延びた。グッスリ眠ろうと思っても仲々寝つかれぬ。やっぱり興奮しているのであろう。何か考えようと思っても頭が真空みたいなようになっていて、空転するばかりで何一つ纏ったものが浮かんで来ない。妙に内地のことが切れ切れに脳裏をかすめる。唯なすことなく時の経つのを待っていたに過ぎない。その内又夜になった。腹ごしらえをして昨夜の海岸まで進発することになった。こんどは8時か9時頃には現地に着いていた。
暫らくすると、又もや海戦が始まった。昨夜と全く同じだ。狐に騙されているのではないかと錯覚した位である。その内海戦が止むと、遥か3000メートルの沖合に微かに十数隻の軍艦が横に並んで浮いているのが見られた。その内に何処ともなく舟艇が海岸に向かって来た。我れ先に乗ろうとするが岸に舟がついていないので、舟は海上をふわりふわり浮いていて仲々乗り切れない。仕方がないので銃を肩から外し舟の中へ抛り込んで、先に乗っている者に手を引上げて貰って漸く乗り込めた。海水のため身体は異常な重さになっており、容易に足が上がらないのだ。こうして助け合って乗り組んだ。1隻でせいぜい20名位乗ったかと思うとすぐ出発だ、ぐずぐずしていられないのだ。
海岸線に沿って舟は進むかと思いきや、沖合に向かって進んでいるのだ。駆逐艦のいる所で止まり、駆逐艦から下げられている綱をつたって艦内に乗り込んだ。
艦内では、海軍さんが「御苦労さんでした」と鄭重なもてなしだ。ここで初めて、我々はガ島を撤退してボ島(ボーゲンビル島)へ転進することを知らせられた。ああ助ったのだ。ガ島で死なずに済んだのだ。こう思うと、先刻まで張りつめていた気持がサラサラと音を立てて一度に崩れていくのが自分でもよく判った。思えば長い苦しいガ島の戦斗であった。再び生きてガ島を去ることはあり得ないと諦らめていたのだ。夢のような気持であった。
27.艦上
漸く全員の乗り込みが了ったらしく、間もなく出艦だ。30隻以上の艦隊だ。壮観であった。まだ日本にもこんな軍艦があったのかと感心した。ガ島のボンヤリした島影が見る間に見えなくなってしまった。もう再びガ島へ来ることもあるまい。昨年の11月5日にガ島へ上陸して以来1日も気の休まったことがない。今日は既に2月1日だ。思えば長い辛い戦いであった。今日はグッスリ眠れるであろう。
ところがドッコイ仲々眠らせてはくれなかった。夜明け方敵機約30機に発見され、機銃掃射を受けることになった。入れ替り立ち替り執拗に襲いかかる荒鷲の如き、敵機は縦横無尽に銃撃し、艦内は相当な損害を受けたらしいが、幸いにも人命には損傷はなかった。約2、30分追撃されたが駆逐艦はジグザグ進行をとり、巧みに逃げ廻り、敵機も諦めて去ってしまった。爆弾を積んでいなかったらしく又逸早く航続距離を離脱したのは僥幸という外はない。一発御見舞を受ければ艦もろとも太平洋の藻屑と化したことであろう。
後は何の故障もなく、一路ボ島を指して快適に航行を続け、翌日午前中にボ島に無事着港した。
しかしボ島には1隻の船すら見当たらない。湾内のあちこちには日本の艦船が擱坐(かくざ)しているのが見られ、後方も空襲の物凄さを物語っていた。
だが一応生命の危険より脱した安堵感は隠し切れなかった。
28.ボ島(ボーゲンビル島)
ボ島へ上陸した。空気がこんなに旨いものであるかを初めて知った。ガ島のあの屍臭に満ちた呼吸のつまるような空気とは断然違う、天地の差だ。
生きていたのだ。生きていてよかった。骸骨のような姿であっても、生き続けて来たのだ。衣服はどんな染料でも染められないような色をしていた。いや色というのは当らないかも知れぬ。土と汗とがしみついてそのもの自体であったかも知れぬ。だが3ケ月肌につけて来たものだ。自分の身体を護って来てくれたものだ。自分の身体の一部となっていたのだ。
残留の者が水と杖を用意していてくれた。何事にも勝って、有難かった。
水らしい水を呑んだことがない。屍体の浮いている水を幾度か呑んだことか。脚がもう上らない状態になっていた。気力だけで歩いて来たのだ。一寸としたつる木でもあればこれに蹴躓いて転んだものだ。杖は大助りだ。上陸地点より残留の者が用意してくれた幕舎までかなりの距離があったように思う。全く葬式の行列みたいな速度だ。やっとのこと目的地に着く。思わずクタクタとくずれるが如く倒れた。
中隊編成114名の内、辛うじてボ島ヘ達したのは僅か12名であった。102名がガ島で死んだのだ。恐ろしい戦斗であった(ガ島に行ったものは10年は生命が短かいということだ。)。我々の身体は半ケ年は十分休養すべき必要があると専門家は云っていた。食事はオートミルより始め、順次常食に変えていくことである。一時に食べると死ぬと云われていた。本部の給与も身体の回復に合わせて作っていた。
ボ島には現在弁護士として活躍しているH曹長も初年兵10名位と共に来ていた。主に設営作業をしていたが、我々ガ島下番者(ガ島より帰還した者を指す)の世話を親身になってやってくれた。当然のことながら大いに感謝したものだ。各隊概ね同じ調子で設営隊が派遣されて来ていた。
ボ島よリニューブリテン島へ行くまでの2ケ月間は毎日ブラブラしていたものと思う。何も特別に記憶するようなことがない。唯入院患者が多く、12名の内半数は入院し、そのうち4名位病院で死んだように思う。
ボ島へ上陸して間もなく、陛下の勅使として待従武官が来島したことがある。炎天下に何時間も整列させ、その為に何人かが倒れたことを憶えている。いかに勅使とは云え、我々は殆んど病人なのだ。それを炎天下に数時間も整列させる神経が解せない。整列させる必要がどこにあったのか。各隊を巡回させればよい。余りにも形式主義化している。この痩せ衰えた兵隊が当分戦力とならないことは明瞭であり、内地に帰ってその旨上奏すればよい。いい所を見せる必要はない。戦争なのだ。我々は曝し者ではない筈だ。辛うじて生還したに過ぎない者だ。もっと労りがあってもよさそうだ。
本当に自分の身体になったなあと気付いたのは「ラバール」に来てからである。ガ島では軽い体操をして、あとは休んでいたと思う。時々体力作りにジャングル内に入ってバナナの葉を運んだような憶えがあるがそれも1、2回位であろう。ガ島の3ケ月間は今でも記憶に生々しく、25年経った今日でも昨日の如く思い出される。それだけ強烈なことであったからだ。ボ島の2ケ月間はそれに比べると余り記憶が残っていないところを見ると、特記すべきような事が起きていなかったのだ。
ともあれ、ガ島の撤退は敵が驚倒する程の整然とした撤退史上空前の快事であった。敵もよもや、日本軍が敵前を悠々撤退するとは気付かなかったのだ。
29.生還
4月初め、「ラバール」に上陸した。ガ島へ行く前、ラバールに3日間寄港したが、上陸はしなかったので、この時始めて上陸したことになる。通常ラバールと云っているがニューブリテン島の一港町の名称であって、今ではニューブリテン島を総称して使われている。
ラバールは美しい港町で、歌にも歌われ詩情をそそるところである。椰子の葉陰から眺める十字星の美しさは終生忘れられないであろう。ここで復員するまでの3ケ年間毎日穴を掘り、芋を作り、明けても暮れても敵機の来襲を受けたが又別の意味で忘れ得ない島である。この間にいろんなことがあったこれは亦別の機会に譲ることにしたい。今は帰還を急ぐ。
昭和21年2月28日、復員船「かつらぎ」に乗船した。濠州兵の検査があった。彼等は時計や万年筆を見るとみんな取上げてしまう。お蔭で時計も取られてしまった。時計や万年筆は彼等に取っては貴重品であったのだ。2月1日船は港から静かに離れた。2年間住みなれた島よ、さようなら。美しい島影が見えなくなった頃はもう太平洋の真只中だ。戦争中、よく敵の潜水艦にやられたところだ。何万、何十万という兵士が海の藻屑と化したことであろう。今はもうその心配もない。悠々と甲板にもおれるのだ。涼しい涼風が頬を撫でて行く。船は相当なスピードで走っている。
この艦はもと航空母艦で、終戦後復員用に改造したため船倉を幾つかに仕切っているので、船倉は暑くていられない。誰もが夜になると甲板で涼んでいる。航空母艦であったので甲板は広く、相当の人員が甲板にいられる。仰向けになって空を眺めると星が飛ぶように走って行く。赤道を過ぎてしばらく北上すると甲板には人がいなくなった。寒いのだ。夏衣で出発したが内地はまだ冬衣装支度であろう。我々は南支以来6年間雪を見たことがない。豊後水道を進んだとき、雪がチラチラしていた。思わず寒さに震えた。3月10日、夢にも見た内地に上陸した。僅かばかりの金を貰って家郷へ。内地は大半焼けてしまっていた。復員列車は仲々目的地に着かない。
名古屋へ着いたのは昭和21年3月13日早朝であった。雪が降っていた。私の家の附近は戦災によって丸焼けとのことであった。とに角もとの家の所へ行くことにした。案の定焼けてしまっていた。附近の人に尋ねて転居先も判かり、実に6年振りで我が家の敷居を跨いだ。家では永い間音信不通で、戦死したものと思っていたらしく、突然のことで口もきけない有様であった。夢のようだと喜んでくれた。かくて長い戦の旅は終わった。心ゆくまで眠りたい。復員して来た日本は闇と混乱で渦巻いていた。日本は何処ヘ行くのか。誰も判らない。あの廃虚から誰かよく今日の日本を想像し得た者があったろうか。素晴らしい巨大なるエネルギーだ。
30.終章
苛烈無残な戦争を体験した一人として我々は、我々の子孫は再び戦争をしてはならなとい心から願わずにはいられない。戦争を体験した者こそ、この願いはよけい切実であろう。
祖国と民族を防衛するため最小限度の自衛力を保持することを否定しないが、それはあくまで平和維持の目的のみに必要とされるものであり、それを一部軍国主義者によって戦争の道具とされることが決してあってはならない。
一部の者が唱える中立無防備論には俄かに賛同し難い。それが究極には望ましい理想像かも知れないが、現実の状況は自らの国は自らの手で守るべきであるということを示唆している。
しかしこの地上より戦争の惨禍は永遠に払拭すべきであり、戦争は絶対避けなければならない。
唯平和の美名の下に享楽をこととし、古来伝承の慈悲大和の精神美風まで失ってはならない。
日本が国際社会において信頼され、且つ、期待される国として、今後の発展を期するには次代を背負う若人に確固たる日本精神の基盤を植付ける必要があろう。
近時根性論が盛んであるが、唯それだけでは足らないように思われる。日本の永遠性の自覚を促すべきであろう。伝来の精神によって裏打ちされる必要がある。
私はこの手記において、ガ島戦を我が中隊を中心にして、ごく概括的に記述し、その戦争の非情性を伝えんとしたが、到底その実相の万分の一も表し切れていない。又書き残した部分もかなりあり、十分その全貌を明らかにしたとはいい難い。しかし戦争の無残、悲惨なことはお分り願えたと思う。真の平和とは何かということを理解する上において何らかの稗益するところがあると私は堅く信じている。
今この手記の筆を擱くに当たり、ひたすら祖国の加護を信じてガ島の地に散った幾多の将兵の英霊に対し、心から限りなき哀悼の意を捧ぐるものである。(了)

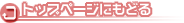
|

