|
13.上命下達せず
戦場では軍律はかなり紊れていた。上官の命令は必ずしも部下に徹底されていなかった。上官の権威は失われつつあった。これは上官の行動そのものにも問題があった。ある小隊長は部下を掌握することを放擲して、死者を暴き、その遺品を探し廻っていた。このような指揮官を信頼せよという方が無理である。部下も部下である。上官を殺して平気の顔でいる奴もいる。全く下剋上も甚しい。
1月13日早暁から敵の攻勢烈しく、私のいる処も危険に曝されんとしていたので、私の前任者の命令受領者であったC軍曹を(彼は既は1カ月以前から病に斃れ歩行すら十分ではない)早めに退らせるべくI上等兵をして付添わせた。C軍曹とI上等兵とは同じ小隊であり、C軍曹はI上等兵を信頼し、その肩により添うが如くにして大隊本部の位置から去った。
ところが数日後I上等兵に会ったとき、Cの安否を尋ねたところ「死んだ」というだけで多くを語らない。しかしその服装をみると、軍靴も軍衣も比較的上等のものを身につけている。「どうしたのか」というと、そこで死んでいた奴から失敬したのだという。しかしよくみるとC軍曹の着用していたものだ。詰問しても黙して語らない。少くとも共に退っていったのだから死んだ様子位は話せる筈だ。しかし、Cは歩行殆んど困難であったので、足手纏いとなって山中に引込み、これを殺害して、その身ぐるみ剥いで着ていたものに違いないのだ。大阪出身の補充兵で年令もその時34、5才で世故に長けた仲々の悪党だ。Cは哀れにもその部下に殺されてしまったのだ。尤もCもあの身体では生きて還れなかったであろう。それにしてもIはひどい奴だ。しかしその彼もガ島を辛うじて撤退したがボ島へ上陸してから日ならずして死んでしまったので、今更彼を非難しても始まらない。所詮は因縁という外はない。
前戦の中隊長へと部隊長より「メリークイーン」(英国製の煙草の名)1箱を渡されたことがある。私は命令を伝達するときにこれを携行して敵中を突破してK中尉に渡した。私は煙草好きであったが茲(ここ)数十日喫ったことがない。「御苦労1本喫め」といって1本位は呉れてもよさそうに思う。しかしこの指揮官は「ああそうか」といったのみで、自ら喫っただけで遂に私には喫えとは云わなかった。他を顧みる余裕がなかったと云えばそれまでかも知れないが、部下の労をねぎらう余裕がないとは情けない限りだ。「士はおのれを知る者のために死す」という。この時を境にして中隊への命令の伝達を私はしなくなった。危険を冒してまで行かなくても、中拠点より中継して貰えば事足りると考えたのである。
当時煙草は貴重品であった。それだけに1本の煙草が、どれだけ士気を鼓舞し、上下の信頼を堅くするものであるかを彼は知らなかったとは甚だ遺憾と云わざるを得ない。それは人間性に連がる問題である。煙草1本ということに止まらないのである。人間の奥底にあるヒューマニズムの欠如ということである。
私は如何に戦場が軍律のない修羅場であっても人間性だけは失いたくなかった。ただでさえ救いのない戦場が余計に悲惨になるばかりであるからである。心身共に疲労困憊し、頭も狂うばかりの死の戦場において何らかの救いがなければ余りにも虚しく余りにも哀しい。
14.迫撃中隊の最後
第一大隊に迫撃中隊が1ケ中隊配属されていた。隊員の訛りから東北方面の出身で、恐らく第二師団からの配属と思われる。彼等は我々より1ケ月以前から上陸して戦斗に参加しており、東北特有の粘りが強く、身体も頑健の者が多かった。隊員は7、80名位いたかと思われるが、毎日半数交替で後方へ迫撃砲弾を取りに行く。2日行程で帰るのであるが、背中の背負子に迫撃砲2筒をしばって搬送するのだが、重さは40キロ位あるだろうか。急な山道を谷間沿いに、喘ぎ喘ぎ前線に運んで行く。来る日も来る日も限りなく運んで行く。前線にはかなりの砲弾が積込まれたであろう。
黙々と弾丸を搬送する彼等の姿を眺めていると、つくづくその生命力の強さに圧倒される。我々より1ケ月以上も前に上陸していながら素晴らしい元気だ。
それにしても前線部隊がその兵力を割いて弾丸を搬送しなければならない作戦は余り感心したことではない。輜重部隊が当然担当すべきだ。このような非常識な作戦に勝利がある筈はない。兵力が消耗するばかりである。上層部は何を考えていたのであろうか。
非常識と云えば、第一大隊長はその最たるものだ。虎の棲むような洞窟の中で、兵が1日飯盒の底にはりつく位の食糧しか与えられていないのに、毎食飯盒に一杯の飯を喰べ、副食には我々にはありつけない海軍用の缶詰を切り、燃料に我々が食糧としていたコプラ(椰子の核実の乾燥凝固したもので、燃料ともなる)を用い、全くその傍若無人の振舞いに恐れ入っていたのである。歩兵団長の伊東少将は、副官が気をきかせて乾麺飽を間食に出すと「兵にも渡っているか」「いや閣下用です」と云うと口にはされなかったということであるが、全く雲泥の差である。伊東少将は兵と共に苦しみ、兵と共に斗った典型的武将である。これに引替え我が大隊長の行動はお話にならぬ。沢山の部下が飢死をしているのに平気で贅食していたのである。
その彼が、かつて支那作戦において、炎天下を2時間も強行軍させ、兵はバタバタ倒れた。30分間休憩してもその疲労は仲々回復しない。普通行軍は45分歩いて、15分休憩する。行軍の里程が長くなるにつれ早めに休憩するを原則とする。彼の頭脳は1時間で15分休むも、2時間で30分休むも同じだと考えていたかも知れぬ。人間の疲労度を全然考慮に入れない愚人という外はない。彼の眼には兵は奴隷の如きものであったのだ。
その彼が敵が攻勢に転じて来たときに迫撃砲が1発の弾も射たないので、中隊長を呼びつけ、「何をしているか、敵のいたい所を射て」と怒鳴りつけた。
前線の中隊長は敵の優勢なる攻撃力に対し我が迫撃砲の3つや4つでどうしょうもないことは百も承知していたのでじっと時の至るを待っていたのであるが、大隊長の手痛い叱責を受け、心ならずも全迫撃砲に砲撃を命じた。その砲撃のために敵は一時沈黙を守っていたが、この為に迫撃砲の陣地が敵に察知され今度は逆に、30倍以上の砲撃を受け、迫撃中隊は潰滅的打撃を受けた。1ケ月有余に亘って技々営々として貯えた砲弾を一挙に失い、迫撃砲は破壊され、兵員は殆んど戦死して仕舞い、中隊長以下数名のみが生存するという状態になった。完全に戦斗力を失ってしまったのである。その間実に2時間足らずである。
しかも大隊長は撤退の命令が来ても、その命令すらこの中隊長には伝えなかったのである。
我々は撤退の直前後衛尖兵を命ぜられ前線に交替させられ、再び敵中にあったとき、迫撃砲の中隊長は自らも傷つき、伝令と下士官の2名を連れて前線を悄然として立去った姿を今も忘れられない。その後の消息は判らないが、恐らく彼は大隊長を痛く恨みとしていたに違いない。配属中隊の哀れさで、いつも使われるだけ使われ、割の悪い任務を負わされ、その挙句は全滅だ。全く助らぬ話だ。
どうせ死は覚悟の前であるが、よき指揮官の下で従容として死すことができたら本望だ。
この大隊長の下ではそう簡単には死ねない。
15.自決
1月14、5日頃になると前線は殆んど全滅が伝えられ、大隊本部付近も敵が突入する気配となった。敵は一挙に攻めてくることはない。敵は前線を進めると必らず砲を据える。その音がキーン、キーンと響く。この音がやむと危険となる。烈しい砲撃が始まるからだ。丁度この頃下士候の某兵長が既に1ケ月以上も負傷が癒えず、大隊本部の位置にいたが、歩行は全然不可能の状態であった。既に自分の生命の限界を覚り、今はこれまでと思ったのか、夕暮腹部に発火させた手擲弾を当てて、壮烈なる自決を遂げた。轟音と共にかけ寄ったときには身体を「く」の字に前に倒して無惨な姿となっていた。
彼は15年兵であったし、常日頃、余り話合ったこともなかったので、よくその人柄を知らない。唯々無口な奴だったいとう記憶のみがある。
その彼が生きて虜囚の辱しめを受けまいとして自らの命を絶ったのだ。
敵は数日を出でずしてこの地点に侵入してくることは既に状況上明らかでありその時彼は歩行できないので置去りになることは必至であり、覚悟の自決に踏み切ったものと思われる。人間仲々死ねないものである。誰しも生への執着はある。前線では自ら動けない者がどれだけ置去りを受けたかは判らない。
それらは、いずれも立派な自決をしたことであろう。戦場の非情冷酷の側面というべきであろうか、唯々慟哭を禁じ得ない。
ガ島では飢えて死んだ者もある。気が狂って死んだ者もある。しかしそれはまだ死に対しては自然的なものが残っている。だが動けなくなった者が置去りにされ手擲弾を渡され、自決してその最後を全うせよという状態になった者の心境はいかばかりであったろう。苦楽を共にした数少ない戦友の姿が見えなくなってしまった。あとに残った自分は唯一人、動こうにも動けない。辛うじて呼吸しているに過ぎない己れを見つめて、自分を育んでくれた両親、縁者、平和の時における内地のことなどが、走馬燈の如く脳裏をかけ廻るであろう。ふと気がつくと敵中に唯一人いる自分を発見する。もう死より外に自分を救うものはない。生への未練はさっばりなくなってしまう。心残すものはない。戦場は静かになった。一つの轟音と共に彼の生命は消えた。
あの世は平和で静かであろう。
死せる者よ。静かに眠れ。切に冥福を祈る。
16.全滅
(一)
1月13日の早朝から異常に烈しい砲声や銃声が戦野を轟かした。大隊長は各隊の命令受領者を集め、各隊の戦況を至急報告せよとの命令を下した。私は早速、一二中隊の三小隊がいる中拠点へ急いだ。途中大きな樹木が無残にも砲撃のため、あちらこちらに倒れ、歩き難くしていた。倒木をくぐったり、跨いだりして、漸やく草原地帯の台上に出た。中拠点はこの台の下だ。この道は殆んど毎日通っている道であるが、樹木が無数に倒れていて通行を困難にしているので大変時間がかかる。通常30分位のコースであるが、この日は1時間以上もかかって中拠点に達した。この中拠点の指揮者はK曹長だ。公正な人で、尊敬できる一人だ。既に2ケ月以上の壕の生活は彼を脚気にしていた。辛うじて歩行できる状態であった。隊員は20名位生存していた。A軍曹もいた。S一等兵もいた。同年兵のK伍長もいた。N兵長もいた。皆元気な様子であったがF伍長はやや頭が変であった。早速早朝からの様子を聞くと、「烈しい銃声はしたが小隊には異常がない。一中隊の方が危ない」とのことであった。「中隊の拠点へ行けるか」と尋ねると、「この状況では一中隊が危ない。その左翼の一二中隊へはとても昼間は行けまい」と。同行して来た一中隊の命令受領者は拳銃を手に、鉄帽をしっかりかぶり直し、「是非中隊の拠点へ行く」と云って出掛けていったが、間もなく真青の顔をして飛帰って来た。「とても中隊の位置まで行けぬ、敵が中隊拠点になだれ込んでいる。一二中隊拠点まではとても行けまい。俺は夜になるのを待って様子を見に行く」と。
私は一二中隊の拠点に行くことを断念した。そして中拠点でしばし雑談していると、午前9時頃敵はまたも烈しく射ち始めた。
中拠点は大隊本部に最も近接しているので、この状況を報告すべく飛んで戻った。大隊長に本未明からの敵の攻撃は異常な位烈しいこと。中拠点は異常なかったが、一中隊はかなり危険であること。一二中隊の状況は一中隊拠点が散中になっているので行けない旨を報告した。
大隊本部は極度な緊張に包まれた。一線が突破される危険が迫って来たのだ。私が中拠点より戻ったときが三小隊の最後であった。その夜小隊長以下全員敵に突入してその儘消息を絶ってしまった。K伍長も傷つき、草原までたどりついたときN兵長と共に敵弾を受け、折り重るように倒れ、絶命した。
確か2、3日経ってからUとIがふらふらと戻って来た。状況を尋ねても恐怖と戦慄に口も聞けないのか、K伍長の戦死を伝えたのみで、三小隊がどうなったか語らなかった。その内2人とも日ならずして死んでしまった。
UとIが戻ってから2日位置いてA軍曹とS一等兵が帰って来た。彼等も多くを語らない。小隊長は敵陣へ突入して行ったので、これに従っていったが途中夜間のことでもあり、見失ってしまい、自分達は二師団のいた海岸道を迂回して戻ったということである。しかし妙な話である。中拠点より左に一中隊、一二中隊、第二師団となっていたのであり、一中隊が全滅して敵兵が侵入していたので、この地点を経て海岸道へ出ることは不可能である。恐らくジャングルを迂回して海岸道へ出たものの如くであるが、その真相を語らないので中拠点全滅の模様は明確ではない。合計4名のみが生還したことだけは確かである。
一方一中隊の命令受領者とは、夜になってから中隊拠点に行くといって中拠点で別れたのだが、その彼はどうなったのか。
その夜、中拠点は全滅してしまったがその隙に彼は一中隊拠点に行ったものらしい。2、3日経って戻った彼の伝える所によると、中隊長以下枕を並べて全員壮烈なる戦死をしていたとのことであった。これで一中隊が全滅したことが判明した。そこで左翼陣地で残るのは一二中隊拠点の状況である。
(二)
中隊拠点の正面も、1月13、14日の両日烈しく敵弾に見舞われ、この両日だけでも30名以上が戦死したのだ。
敵はガス弾を射ち込み、防毒面をつけても吸収罐(缶)が砲撃のためにやられているので、その効果なくそのままガスを吸って死んだ者もあり、或いは火炎放射器で焼かれ、真黒焼けで死んだ者もあり、壕の上から手擲弾を投げられて死んだ者もあり、非力な日本軍を完膚なきまでに叩いたのだ。
中隊拠点の指揮官はK中尉とK見習士官である。この時の中隊兵力は凡そ40名位であろう。この両日で殆んど全滅してしまったが、指揮官がもっと明確な指揮をしておれば戦死者の数をもっと少くしていたかも知れない。
13日の烈しい攻撃に中隊は危殆に瀕した。両将校は退却すべきかどうかを議論した。「命令がないのに退却はできぬ」、「いや戦況の判断は一線指揮官がすればよい」と論争は平行線をたどり、その日はその儘死守することになった。翌日又同じ論争を繰返すことになった。前日と意見が入れ替っての論争である。こうしている中にも戦死者の数は増えて行く。13日に退却を断行していたら半数の戦死者で済んでいたかも知れぬ。結局15日の夜に入ってから、第二師団の方へ移動して逃げ帰ったのだ。既に遅い、その時は中隊兵力は7名に激減してしまっていたのだ。
躊躇逡巡は指揮官の最も戒むべきところである。これは作戦行動の鉄則である。ここに至っては、一つの拠点の成否は問題ではない。既に第一線は敵の巨大な攻撃の前にズタズタに切り裂かれていたのだ。
戦況の判断と行動の果断は指揮官の最も必要とされる資質である。ここに指揮官の良否が問題とされる。どうにもならなかったという言葉は受取り難い。どうにもならなかったのではなく、どうもしなかったのだ。我々人間の行動には最善の道はあり得ない、唯最善を尽くすだけだ。戦場の愚論が多数の戦死者を出したことだけは確かである。
第一線は敵の鉄蹄に蹂躙された。各部隊は潰滅的打撃を受けた。1月15日を境いにガ島戦は大きく模様を替えた。撤退の序曲がそこにあった。後で聞くところによると、大本営の撤退命令が現地の第一七軍司令部に届いたのが1月15日、翌16日第二八師団に伝達され、この命令が傘下の部隊へ伝えられたのはその翌17日頃である。我々の所へは18日の夕方撤退の命令が伝えられた。
撤退の命令を受取っていない部隊もある。右翼の第二大隊だ。アウステン山(高さ1500米)の中腹にいた部隊だ。既に連絡は不可能であったらしい。この部隊は全員帰還しなかった。この部隊の二機隊長はかって一二中隊長であったS大尉である。立派な武人であった。恐らく縦容として死についたものと思われる。
ガダルカナル(5)へつづく

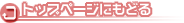
|

