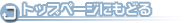子どもの事件の現場から(117)
「私が、いなくなったらどうしますか」
会員 間 宮 静 香
「間宮さんは、私がいなくなったらどうしますか」
「とある日曜日の午後10時過ぎ、ある女の子からメールが来た。里親宅で生活をしている子だ。
キャプナ弁護団に所属し、児童相談所の担当となっている私は、児童相談所経由で知り合った虐待を受けた子どもたちと関わることが多く、メールのやりとりや、会って一緒に食事して、グチを聞いたり、相談に乗ったりすることが少なくない。
しかし、彼女は、児童相談所とは異なるルートで相談に乗った少女だった。児童養護施設に入所した経緯も、彼女の抱える生育歴等の問題も明確に知らぬまま、一度だけ面接をし、その後、メールでやりとりをしていた。
彼女は、あることで県の代表に決まったときにも、すぐに私にメールをしてきた。そのメールを受け取って、うれしさを感じるとともに、たった一度しか会っていない私が、うれしさをすぐに分かち合いたい相手なのかと思うとやりきれなさを感じた。
彼女と出会って数週間後のその日も、夕方からメールのやりとりをしていた。たわいのないメールのやりとりだった。しかし、突然、メールの最後に冒頭の文字が並んでいた。
試し行動かとも思った。しかし、なにぶん、彼女の生育歴や性格を理解しておらず、私の対応如何によっては本当に自殺するかもしれない。明確に覚えてはいないが「そんな悲しいこと言わないで。私を含め、悲しむ人がたくさんいるよ」というような当たり障りのないメールを送ったのだと思う。しかし、そのメールは彼女の地雷を踏んでしまったようだった。
彼女から「大人はみんな嘘つきだ!!」「大人なんて信用できない!」等これまで隠していた感情が一気に爆発したかのような怒りに満ちたメールが続けて届いた。そして、ついに「○○○○(彼女の名前)は、平成○年○月○日、人生の幕を下ろすことにしました。ありがとうございました。さようなら」というメールが来て、返答がなくなってしまった。
一刻を争う事態かもしれない。自分の対応に自信が持てない中、試し行動であることを祈りつつ、震えながら電話した。長らくコールをしたあと、彼女は電話に出てくれた。しかし、その声は、冷たく、暗く、明らかに心が閉ざされていた。
それでも、彼女が電話に出たことに安堵し、会う約束を取り付けようとした。彼女は「会わなくていい」と言いながら、1時間近く話をしてくれた。やはり寂しかったのだろう。最後は一方的に電話を切られてしまったけれど、話すうちに少し落ち着いたようだった。
子どもたちと法律問題と関係なく関わることは「弁護士」の本来の仕事ではないかもしれない。ただ、「弁護士」だからこそ、子どもたちと関わることができるのも事実である。
彼女のことも含め、中途半端な関わりになってしまい、自分が情けなくなることも多いけれど、私には信じられないような重い運命を背負ってけなげに歩いている子どもたちを、関わった大人のひとりとして「仕事じゃない」と放置することもできず、失敗を繰り返しながら、今日もメールをする。