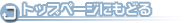シンポジウム
災害時における個人情報の適切な取扱い
〜高齢者・障がい者等の安否確認、支援情報伝達のために〜
開催される
高齢者・障害者総合支援センター
運営委員会 委員
長 澤 幸 祐
1月28日、東建ホール・丸の内において、標記のシンポジウムが、当会、中弁連、日弁連の共催で開催されました。
東日本大震災発生後、個人情報保護関係の法令が障壁となり、高齢者・障がい者の安否情報が、それを必要とする関係諸団体に伝えられなかったことにより、多数の犠牲者を出すこととなりました。
今後、緊急時に高齢者・障がい者の安否確認、支援、情報伝達を円滑に行うことができるようにするため、個人情報の適切な取扱いを考えるとの趣旨から、東京、大阪に次いで、本シンポジウムは開催されました。
- 1 基調報告
-
(1) 最初に、障がい者施設を運営するNPO法人の代表者青田由幸氏により、震災当初の南相馬市における障がい者の現状が報告されました。南相馬市に残った障がい者を支援するため、障がい者の居住地等の個人情報の開示を求めたものの、当初、個人情報保護条例が障壁となり開示を受けられなかったこと、その後、市幹部の決断により個人情報の開示を受けたことにより、障がい者とつながり、支援を行い、命を救えたことなどを報告して頂きました。
(2) 次に、震災時、東京都から仙台市職員に派遣された経験のある鳥井静夫氏から、生活再建段階におけるみなし仮設住宅支援の実態が報告されました。
みなし仮設住宅とは、仮設住宅として供給された民間賃貸住宅のことをいい、仮設住宅と比べてコストが安く、全国で活用できるなどのメリットがあります。
しかし、みなし仮設住宅は、被災地から離れて生活することができるため、避難先自治体と避難元自治体間における被災者情報の共有が困難となり、被災者の実態を把握するのが遅れたり、行政機関から支援団体等への被災者個人情報提供ができず被災者間の支援格差が生じるなどの問題が発生したとの報告をして頂きました。(3) 岩手県職員の山本和広氏から、同県での被災者情報提供スキームの構築の実情についての報告もありました。
- 2 パネルディスカッション
-
八杖友一弁護士(第二東京)の司会のもと、山崎栄一大分大学准教授、岡本正弁護士(第一東京)も加わり、行政、情報提供を受ける側、法律家の各立場から様々な意見が出されました。
行政機関における個人情報利用の原則は、本人同意と目的外利用の禁止にあります。
しかし、個人情報保護法は、個人の権利利益の保護と個人情報の有用性のバランスを図ることを目的とした法令であり、保護だけを目的としてはいません。
例外規定も存在しており、「緊急かつやむを得ない」場合、「相当の理由」「公益上の理由」「特別の理由」のある場合、「法令に定めのあるとき」、目的外利用、外部提供が認められています。
自治体の中には、岩手県のように個人情報保護条例の解釈により個人情報の提供を可能としたり、渋谷区のように災害対策条例を新たに制定したり、また南相馬市のように個人情報保護条例を改正し、災害時における個人情報提供を明記するなどして対応するところも出ています。
- 3 まとめ
-
災害時に何が出来るかは、災害前にどれだけ準備していたかにより決まります。
行政が個人情報提供のシステムを構築するだけでなく、支援団体は利用目的から廃棄に至るまでの情報管理を十分できるようにし、つながり、信頼関係を平時から築き上げておく必要があります。