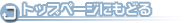子どもの事件の現場から(106)
発達障害の精神鑑定から司法福祉へ
岐阜大学准教授・精神科医
高 岡 健
- 発達障害の過剰診断
-
日本の司法領域において、自閉症スペクトラム障害(広汎性発達障害)をはじめとする発達障害に関し注目が集まるようになったのは、2000年以降だ。当初は、これらの障害の見落としが問題だった。ところが、わずか10年あまりの間に事態は急転回を示した。自閉症やAD/HD(注意欠如/多動性障害)の過剰診断と言いうるような状況が、生まれはじめたのである。
観護措置の段階で、あるいは送致先の少年院で、単にコミュニケーションが上手でないという理由から、発達歴を十分に確認しないまま発達障害を有すると決めつけられた少なくない数の事例を、私は知っている。その結果、少年が有している精神疾患が見落とされたり、狭義の児童虐待やマルトリートメント(不適切養育)の結果としての言動を、障害のせいだと誤解してしまう事態が生じている。
たとえば、躁うつ病の躁状態による落ち着きのなさを、自閉症スペクトラム障害ないしAD/HDに伴う多動だと誤診された事例がある。また、児童虐待を被って育った少年の示す注意集中の困難を、発達障害に基づく特徴だと誤ってとらえた事例もある。そうなってしまえば、少年の処遇もまた、誤った指針のもとに置かれてしまうことは論を待たない。
- 情状の等閑視
加えて、もう1つ問題がある。少年が自閉症スペクトラム障害を有している場合でも、障害自体が直接的に非行をもたらすわけでは、もちろんない。にもかかわらず、関係者のまなざしが障害にのみ向けられると、少年をとりまく環境の影響その他の情状が等閑視されがちになる。
同僚たちとともに私は、加害少年が自閉症スペクトラム障害を有していると診断された、いくつかの事件について検討したことがある。そのうちの1つである教職員殺傷事件では、いじめを回避するために不登校を選択した少年に対して、教師や母親は不登校の意義を理解しようする姿勢を欠いていた。
同様に、「理科実験型」などと呼ばれる、毒物による殺人未遂事件でも、いじめの事実に周囲の大人たちは気づいていなかった。また、ある放火事件では、少年への暴力を伴う勉強の強要が、父親によって日常的に繰り返されていた。
このように、自閉症スペクトラム障害を有する少年が惹起した事件であっても、その背景には、いじめや不登校に対する無理解や、教育の名のもとに行われる虐待ないしマルトリートメントが介在しているのである。
しかし、障害以外の重要な背景が等閑視されると、いきおい少年の責任能力の有無にのみ関心が集中し、情状の検討を通じた少年への理解がおろそかになる。すると、少年の更生に向けた道筋は、せいぜい障害特性を訓練によって軽減するといった発想にとどまってしまい、少年の自己尊重感は回復しない。
- 司法福祉
-
このような現状を改善するためには、児童精神科医による精神鑑定の実施はもとより、精神鑑定書の内容を含む少年審判で得られた所見を、終局決定後の処遇過程に活用することが重要になる。このことは、発達障害及びその他の要因がどのように絡み合って非行への道筋を形成したのかを明らかにし、その道筋をいかに修整すれば、少年の自己尊重感の回復を通じて更生へと至ることができるかを解明する作業であるから、司法福祉そのものに他ならない。換言するなら、精神鑑定もまた、司法福祉の一翼を担うものとして位置づけることができるのである。