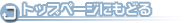子供の事件の現場から(98)
「ぼさぼさ眉とおかっぱ頭」
初めて会ったとき、彼女は坊主に近い頭をしていました。対立するグループの女の子にやられた、どこ行くにも帽子かぶらないかん、と笑う彼女は、でも坊主になるの初めてじゃないんだよね、オヤにもやられてるから、と軽く言いました。
彼女は父親の顔を知りません。彼女の母親も、誰が父親なのかわからないようでした。精神的な病気を抱えた母親は、調子が悪くなると、ただひとりの家族である彼女に当たり散らしました。病気のせいで、彼女の食事の支度や日常の世話をすることもできませんでした。坊主にされたり、「おまえさえいなければ」という言葉を投げつけられたりしても、彼女は母親を求め続けました。常に愛情飢餓感を抱えていた彼女は、心の拠り所を不良交友に見いだし、いわゆる「横着い」グループの代表的存在として警察にもマークされるようになりました。「好きな遊びはパー鬼(パトカーとの鬼ごっこ)」と言う彼女に、どうしてそんな遊びが好きなの?と聞くと、警察は必ず追いかけてくる、大人に相手にしてもらえるのって何かいいじゃん、という答が返ってきました。
審判で、彼女は、お母さんを支えられるのは自分しかいない、自分がいなければお母さんが発作を起こしたとき救急車を呼ぶ人間がいない、だから家に帰してほしい、と訴えました。母も、この子が私の世話をしてくれないと生活できない、生活保護も減らされてしまう、他にやんちゃをしている子はたくさんいるのに、うちの子だけ家に帰してもらえないのはおかしい、と訴えました。けれども、裁判所は、彼女を少年院送致にしました。
付添人として彼女の今後を考えたとき、私は、このまま家に帰って母親の精神疾患をフォローし、時にはストレスのはけ口になりつつ、居場所を求めて悪友たちと遊び回る生活を続けることは好ましくない、と思っていました。事件を起こして逮捕勾留され、鑑別所に行くことになった事実を「なかったこと」にすべきではない、このことをむしろ彼女の人生を変えるきっかけにできれば、と。これは、担当の調査官や鑑別所の技官、おそらく裁判官にも共通した思いでした。このように、今後の生活の場が少年院であるべきかどうかは別として、事件をきっかけに、悪友たちや母親と距離を取ることが必要であり、また可能となるのではないか、と考えていましたので、私としては、裁判所の判断には素直に納得できました(この時点で、社会の中に居場所を見つけることができればベストだったとは思いますが、現実にはなかなか見つかりませんでした)。ただこの時点では、彼女は家に戻りたいばかり。毎週のように「お母さんが心配」「帰りたい」という手紙が私のもとに送られてきていました。
数ヶ月後、少年院で久しぶりに面会した彼女は、私に対して敬語を使うようになったことなどの変化とは別に、髪が伸び、逮捕直後はきれいに整えられていた細眉がぼさぼさになっていました。手入れしていないぼさぼさ眉と短めのおかっぱ頭で以前よりずっと幼く見える彼女は「ここに来て、決まった時間に起きたり寝たり、3食ちゃんと食べたり、っていうのができるようになった。来て良かった」と、笑顔で話してくれました。
生まれ落ちる環境は選べない。その中で、懸命に、前向きに生きようとする彼女の今後に、幸多かれと願うばかりです。