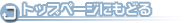子どもの事件の現場から(96)
親子のスタートライン会 員
濱 嶌 将 周
濱 嶌 将 周
- その少年審判の席にいた全員が悲しい涙を流していた。みんなの気持ちがひとつの方向に向かい、少年の更生と親子の幸せを願っていた。
- 少年の両親は十代で親となったが、少年が小学校に上がる前に離婚した。少年の親権者は母親となったが、父親に引き取られた。父方の祖父母が手放さなかったからである。
父親は刑務所を往復するような人で、少年はほとんど父方の祖父母に育てられた。「お前は母親に捨てられたんだ」と言われながら。
その祖父母が、少年が小学5年生の頃に相次いで病死。養育者がいなくなった少年は、児童養護施設に送られた。そこで少年は壮絶なイジメに遭った。しかし、施設はそれを把握せず、かえってイジメが原因で暴れる少年を問題児扱いしていた。力で支配されていて、でも大人は助けてくれなくて、少年は「力が強くなれば、いじめられない」と思うようになった。
少年は助けを求めて母親に連絡し、母親は父親に育てられているはずの少年が施設にいることを知った。しかし、母親には再婚相手がおり、その間に子どももできていて、少年の存在を明かすことができなかった。このため、少年は母親の姉に引き取られた。
が、その姉もしばらくして、自分に子どもができて少年を預かれなくなり、さらに別の姉に引き取られた。
このようにたらい回しにされてきた少年は当然ながら、どこにいても安心感を得られず、不良グループに入って、非行を繰り返すようになった。
ここに来てようやく、母親は少年と暮らす決意をし、再婚相手に事情を明かした。少年が母親と暮らせるようになったのは、事件のわずか2か月前のことだった。 - 少年は私との面談当初、母親と暮らせるようになったことについて、「どっちでもいい」と言った。
しかし、少年と何度か会ううちに少しずつ、「ずっとお母さんと暮らしたかった」「自分はこんなにお母さんと暮らしたいのに、どうして妹(母親の再婚相手との間の異父妹)だけお母さんと暮らせるんだろうとショックだった」「お母さんと一緒にいられるようになって嬉しかった」「今一番の願いは、お母さんと一緒に暮らすこと」と話してくれるようになった。面接の間ずっとうつむいて指をいじっている少年が、母親のことを話すときだけは、はにかんだようなかわいらしい笑顔を見せてくれた。
ただ、審判が近づくにつれ、少年は「もう二度とお母さんと暮らせない」との不安に駆られ、指をつねったり引っ掻いたりするようになっていた。 - 審判当日、それまで悲しさという感情をけっして表すことがなく、泣くことを忘れていた少年が、初めて涙を流した。母親が「この子を誰にも渡したくなかった」と話したその瞬間に。
母親も涙を流した。決定言渡後には、少年の腕を握って、いろいろな思いが込められた「ゴメンね」という言葉を繰り返して泣き崩れた。
私もやっと親子になれた2人のことを思い、涙を止めることができなかった。
調査官の目にも涙が浮かんでいた。
裁判官も涙を堪えるのに必死で言葉を詰まらせ、最後には涙を流しながら、少年に児童自立支援施設送致を言い渡した。「一緒に住まわせてあげたいけど、これがベストだと私は思う」と。 - 全員が、少年の問題性は少年の責任ではないと思っていた。しかし、事件の悪質性もさることながら(少年が同級生数人とともに、特殊学級に通う高校生を殴る蹴るツバを吐きかけるなどした上で、財布の中身を奪った強盗致傷事件である)、年齢相応の社会常識も基礎学力も備わっておらず(中学2年生にもかかわらず、漢字はほとんど書けず、九九も満足に言えない)、自分自身の気持ちもよく分からずに暴力でしか表現できない、そんなあまりに幼く、暴力に支配されている少年を、そのまま家に戻すことは難しかった。
ようやく求め続けていた母親と暮らせるようになった少年を、しかし少年のために児自施設に送るという、苦く悲しい決断だった。
母親と離れ離れになってしまったときから時間が止まったままだった少年が、成長した姿で、帰りを待っている母親のもとに戻ってきてくれることを信じている。 - 児自施設に送られて10日ほど経った少年と会ってきた。「お母さんに会いに来てほしくない。やっとここで頑張ろうと思えるようになってきたのに、会うと帰りたくなっちゃうから」。
そっか…。県外の児自施設で、ちょっと遠いけれど、母親にはできるだけ会いに行ってもらおう。