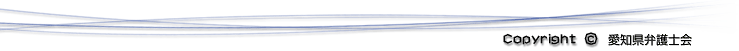|
裁判所から見た裁判員裁判大いに語られる
裁判員制度実施本部 委員
岩井 羊一
- 6月8日、名古屋地方裁判所から伊藤納上席裁判官を迎えて「裁判所から見た裁判員裁判」と題して研修会が開かれた。当日参加者はおよそ150名。事前申し込みで5階ホールでは入りきらないことがわかったので、急遽会場はKKRに変更になる盛況であった。
-
■刑事訴訟は挫折の歴史・裁判員は歴史の必然
伊藤裁判官は、はじめに、裁判員裁判について、自分自身がどのように考えているかをお話ししたいとして話を始められた。この前半の話は、刑事裁判官としての刑事訴訟に対する思いが語られ、大変興味深い話であった。
伊藤裁判官からみた「刑事訴訟法の歴史」の概要は以下のとおり。
新刑訴法が施行された昭和20年代、旧刑訴法を運用してきた裁判官もおり、結局調書裁判が残ってしまった。昭和30年代には、これに疑問を唱え集中審理を実践した裁判官がいて、刑訴規則が整備されたが、消極的な裁判官もいて実務には定着しなかった。弁護士も、連日開廷、口頭主義には積極的でなかった。昭和44年の最高裁の証拠開示の決定があるが、この事例は主尋問の後なら開示できるとしており、検察官は、直前まで証拠を開示せず、結局訴訟運営がやりにくかった。
昭和40年代は、60年安保の時代で、社会問題に若者が敏感で、そのうち先鋭的な人たちが事件を起こし、学生公安事件となった。こうして社会のぶつかりあいが法廷にも入ったが、法廷秩序の維持の立場から結果として被告人に不利益となる裁判例が出た。また、退廷や辞任を繰り返すような弁護活動をする弁護人がおり、そのような刑事裁判が問題になった。そして、ついに「弁抜き法案」(弁護人なしで公判手続を進めることができるように刑訴法に特例を設ける法案)が国会に上程されるまでになった。昭和54年、弁護士会(日弁連)のぎりぎりの決断で、弁護士会が責任を持って国選弁護人を推薦するとの三者協議が成立し、法案は廃案になった。この法案が通っていれば、法曹三者には大きなしこりが残ったまま今日まできたかもしれない。
昭和50年代には、再審により無罪になる事件があった。それを機に、犯人識別供述などの事実認定の司法研究がなされ、自白の任意性については刑事裁判官の協議会でも検討された。そのなかで、裁判所は取調べ経過一覧表を出してもらい、それを把握した上で、取調べ状況の証拠調べをするということを提案したが、検察庁の理解は得られず、自白を証拠として採用し、あとは信用性の検討という実務はあまり変わらなかった。
昭和63年から最高裁判所は、裁判官を海外に派遣して陪審、参審について研究をした。最高裁判所がこのような研究をしていなかったら、司法改革の際の議論も今とは異なり、裁判員制度も成立しなかったかもしれない。
平成2年、当番弁護士制度が大分県で始まり、さらに福岡県で始まって全国に広がったと聞いている。それ以前、勾留質問で、弁護人選任権があると説明しても、費用がかかると説明するとがっかりしてあきらめる被疑者の姿を見て、弁護人選任権の告知にむなしさを感じていた。それが、当番弁護士制度がありますと説明できたのはうれしい体験だった。被疑者国選制度は当番弁護士制度がなかったら絶対にできなかったと思う。
わかりやすい裁判のために判決書を工夫する取組みもあった。しかし、公訴事実の書き方は変わらず、また、控訴審から不正確との指摘もあり、大胆には書き直せなかった。
このように刑事訴訟の歴史はある意味で挫折の歴史である。
しかし、先人が積み重ねてきた改革の芽は生きており、時代を得て、制度的補強も加えられて裁判員裁判となった。裁判員裁判には歴史上の必然性があり、非常にやりがいのある大変革であると思う。
■3人の文殊様
伊藤裁判官は、今までの裁判官像から、裁判員裁判に期待することを述べられた。
合議制の根拠は、3人寄れば文殊の知恵ということわざのとおり。しかし、裁判官は、同じような教育を受け、大きくは違わない裁判所の文化の中で仕事をしており、問題を見る視点の多角性には制約がある。裁判員裁判では判断者が9人になるから、文殊様が3人。裁判官は、国民の常識を間接的に推測して判断をしてきたが、国民6人が直接加わることで、より血の通った、生活に根ざした意見が出され、より多角的な検討を経た裁判をすることになる。また、長期的には、手続的正義の考え方を通して、より成熟した社会の実現につながる。
■「はじめて」「この事件で」
裁判員は、はじめて刑事裁判に接するし、この事件だけを判断する。そういう裁判員にとって判断するよりどころは、自分の人生、人格そのもの。公判審理や評議という体験をとおして、その人のいいところが引き出されるだろうと思っている。
■裁判官から見た弁護人の活動
伊藤裁判官は、裁判員裁判について、市民の参加した模擬裁判の経験も踏まえられて、裁判官の立場から以下の指摘をされた。
■「わかりやすい」とは?
わかりやすい言葉で話したということと、判断するためになぜ必要かがわかることは別のこと。法廷でやっていることが、判断するためにどのように必要があるかが裁判員に伝わらないと意味がない。
■評議からさかのぼる
評議がどうなるかを念頭に、弁護人はどう説得して、納得できる人を増やすかを考えるべき。納得した人は評議で意見を言ってくれる人になる。判断に影響がある法廷になる。
■「ぼうちん」
うっかり「ぼうちん(冒陳)」と法律用語、しかも略語を使ってしまうと、「われわれの世界に入ってこい。」という暗黙のメッセージになってしまう。どういう言葉に裁判員は納得するのか、よく検討する必要がある。
■裁判員は敵ではない
裁判員は、弁護人の、立場を踏まえて真剣に全力でやっている態度、言動を信頼する。逆に、裁判員が違和感を持つことがあれば、ちょっと待てよ、ということになる。闘う刑事弁護といっても、裁判員を敵にして闘うのではないはず。裁判員が判断するときに問題となる点について助力になるような、的確な説明をすることが期待される。
■公判中心主義
今まで当事者は、書証を後で読んでくださいというつもりで提出していた。尋問も調書に残るように意識して尋問していた。しかし、これからは通用しない。裁判員裁判の法廷では、その場で裁判員にわかってもらわなければならない。また、法と規則に従った法廷での証人尋問等のルールが大切になる。
■「頭の固い裁判官」とは言えなくなる!
弁護活動が判断に反映するため、裁判員の説得に、弁護人の真価が問われることになる。裁判結果が思いどおりでないときも、「頭の固い裁判官」と言って済ませられなくなる。
■紙面が尽きた。「らせん階段」「研修店員さんの話」をはじめ、多くの貴重なコメントがあったが、参加した会員に聞いていただきたい。判断する立場の発想を知ることは、被疑者、被告人の権利のためにも必要だと感じた。周到な準備をされ、弁護士のために思いを語ってくださった伊藤裁判官に感謝したい。
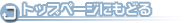
|