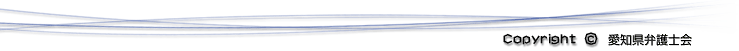|
里見達彦事件模擬裁判の報告と課題
模擬裁判弁護団・裁判員制度実施本部
委員 舟橋直昭 金岡繁裕 川口洋平
《公判を最後一枚のピースにしない》
去る2月17日から20日にかけて「里見達彦」事件の模擬裁判が行われた。この模擬裁判は、当初、法曹三者間で、本年5月実施前の最後の模擬裁判という共通認識があった。
公判では、検察官からビジュアル資料(パワーポイント画像)を駆使した「わかり易い」冒頭陳述や証拠調べが披瀝された。
弁護人からは、近年頓に議論が進んでいる「法廷弁護技術」の成果を示す場となった。
ただ、三者のスタンスの違いから、特に公判前整理手続の段階では、後述のように、「争点整理」を巡って、激しく対立する場面があった。裁判員はどの論点に食いつくか、予測が難しい。公判審理が裁判の中心であるべきであり、法曹三者が整理手続段階で事件の枠組みを設定してしまい、公判をジグソーパズルの最後一枚のピースにするようなことがあってはならない。論点多数・時間不足を理由に証拠評価を疎かにした評議が進められてはならない。
改めて本模擬裁判を振り返ってみる。(舟橋直昭)
《模擬裁判の概要:冒頭報告》
1 里見達彦事件
被告人里見氏と一緒に居酒屋を梯子していた知人Fが、何者かによって暴行され死亡したという事件で、目撃者はなく、里見氏も捜査段階から一貫して否認。いわゆる「間接事実積み上げ型」の否認事件である。
F氏の着衣に里見氏着用のサンダルと考えて「矛盾しない」つま先の潜在痕跡が残されていたことや、里見氏がF氏の容態急変後も少なくとも1時間以上に亘り救急車を呼ぶ等していないこと、事件に関し事実関係を歪曲する口裏合わせをしたこと(和田証人、大山証人。とりわけ和田証人が重要で、この点は川口弁護人の反対尋問体験記をお読み頂きたい。)が不利な間接事実として挙げられ、他方で、F氏は暴行を受けたと見られる前後25分間、被告人と一緒におらず行動が不明であること、被告人とF氏が親しいことなどが有利な間接事実として挙げられた。
2 弁護団の構成
弁護団は、舟橋直昭、金岡繁裕、川口洋平の3名で構成した。
全国で多くの無罪が出されている事案だけに(なお、2月21日の中日新聞報道によれば、有罪17・無罪12だそうである)必勝を期し、当会で裁判員裁判研修を担う裁判員制度実施本部研修部会から部会長・副部会長がそろい踏みする布陣である。また、川口弁護人には、裁判官としての経験・視角が期待された。
3 実際の裁判に近い想定
この模擬裁判は、弁護士会側の強い希望で、出来るだけ実際の裁判に近い想定で行う方向が採用された。
勿論、模擬裁判記録の制約はあり、双方立証を補う余地も小さいし、被害者参加については時間不足から議論が足りないまま中途半端な形で取り入れるなど(否認事件なのに冒頭から被害者参加人が法廷内に着席することは些か現実離れした想定である)、不十分な点は多い。しかし、従来の模擬裁判より、それなりの緊張感を持って実施されたのではないかと思う。
4 判決
結論は、5対4の僅差で無罪となった。裁判員限りで比較すれば有罪無罪が同数で拮抗したため、弁護団として、やや残念ではある。
好評連載中の「改正刑事訴訟法・裁判員法講座」を休載にする代わりに、読み物的な報告記事から堅めのものまで3本の原稿を取り揃えたので、是非お読み頂きたい。(金岡繁裕)
《公判前整理手続への実務的対応》
実際の裁判を想定して対応した本模擬裁判では、弁護人として、実務的な対応を考え、理解しておくべき様々な課題が認識された。
本稿では、裁判員裁判では必要的な公判前整理手続について、2点に亘り、報告したい。
1 公判前整理手続において間接事実の推認力を議論すべきか
(1)裁判所の姿勢
裁判員裁判において計画審理を徹底するためには、特に争いある事件では双方の立証計画を具体的見通しを持って明らかにさせる必要があると、裁判所側では考えているようである。平成18年度司法研究「重大否認事件の審理の在り方」においても、公判前整理手続で間接事実の推認力(必要性)を議論し、共通認識を形成すべきこと等が言われている。
(2)裁判員裁判の本旨との齟齬
しかし、このような考え方は疑問である。
刑訴法上、公判前整理手続で、公判で予定する事実上の主張及び法律上の主張を明らかにする義務(予定主張明示義務)は規定されたが、それを越えて、間接事実の推認力(必要性)を明らかにする義務など、何処にも書かれていない。事実が立証されるかどうかも不分明な公判前整理手続段階で、裁判所が事実評価にまで立ち入るなど、法の許容しないところと言うべきである。
また、間接事実の推認力は、推認過程で適用される経験則の存否や強度によって左右される。例えば里見達彦事件で言えば「F氏の容態急変後も少なくとも1時間以上に亘り救急車を呼ぶ等していないこと」が犯人性を推認させるものかどうか(そのような経験則があるか、どの程度強い経験則なのか)は、職業裁判官だけでなく、裁判員も一緒になって議論し、心証形成すべき事柄である。
職業裁判官限りで間接事実の立証の要否を云々し、職業裁判官の「常識」にかなう事実しか立証を認めないということは、裁判員が実社会での経験によって感得した経験則を排除するもので、裁判員裁判の本旨に悖るものである。職業裁判官が事実認定を左右しないとして独断で却下した証拠が、後に裁判員にとって重要な関心の対象となったとしても、証拠請求の事実すら覚知しないだろう裁判員にはどうしようもなく、取り返しがつかない。
そして、そもそも当事者が無意味な間接事実を立証しようとするはずがない。当事者の主張構造の中で意味があるからこそ、立証しようとするのであり、公判前整理手続で証拠の推認力(必要性)について弁論を行い、これを裁判所が認めなければ立証させないというのは当事者主義にも悖る。
(3)現に必要な証拠が却下された
本模擬裁判で、正にこの問題が顕在化した。
弁護団は、里見氏やF氏が何れも酩酊しており、通常の経験則では、その行動や記憶の合理性をはかれないことを立証しようとしたが、裁判所においては酩酊度合に関する間接事実の必要性を疑問視し、これを具体的・詳細には明らかにしなかった(抽象的に、適用すべき経験則が変わることは指摘した)弁護団の請求していた、酩酊度合に関する証拠は不必要として却下された。
弁護団は、裁判員が加わった以降の手続、具体的には冒頭陳述段階で推認力(必要性)を明らかにすれば足りると指摘し、せめて証拠の採否を留保すべきと主張したが、裁判所は頑なにも証拠を却下した。
ところが、評議では、里見氏やF氏の酩酊度合は間接事実として重要な位置づけを与えられ、議論の土台となっていた。議論の材料となる証拠を裁判所が葬り去ったことを裁判員が知ったら、それでも適正な裁判だと言うだろうかと、傍聴しながら思ったものである。
結果から見ても、裁判所の証拠却下の判断が早計であったことは、火を見るよりも明らかだった。
(4)小括
裁判員制度は、職業裁判官が重要だと思う証拠が市民にとって意味がなく、あるいはその逆がありうることを前提としたものである。公判前整理手続の段階で、裁判官の「常識」による証拠の選別が横行すれば、裁判員はお飾りとなってしまう。
刑事弁護人は、裁判員がお飾りにならないよう、公判前整理手続が肥大化することを防止する役割を負う。裁判員抜きに事実評価の議論を行うことに応じてはならないし、それが制度の本質に悖ることを良く理解し、裁判員裁判に関わっていく必要があるだろう。
2 検察官の証明予定事実を認否する必要はない
刑訴法改正により公判前整理手続の立法がされ、弁護人に予定主張明示義務が課される議論の経過の中で、予定主張明示義務が黙秘権侵害に繋がるおそれや、検察官の証明予定事実に逐一認否することを迫られることへの懸念が叫ばれた。
その後、実務の中で、弁護人に認否義務がないことは、都度都度、確認されてきたが、裁判員裁判との関係では、計画審理の名の下で認否を迫られるような事態が起きかねない。
(1)検察官・裁判所の姿勢
例えば里見達彦事件では、「F氏の着衣に里見氏着用のサンダルと考えて矛盾しない、つま先の潜在痕跡が残されていたこと」が検察官の立証の柱の一つであった。
そして検察官は、公判前整理手続において、「里見氏が、事件当時、当該サンダルを着用していた事実」を争うのかどうか明らかにするよう求めてきた。これを明らかにしなければサンダル着用の事実に関する追加立証が必要かが判断できないと言い、裁判所も、「できれば」認否して欲しいという立場だった。
しかし、このような要求等は、無意味であること明白であり、それ以上に有害である。
第一に、弁護人が争わないと述べても、民事訴訟と違い真実擬制のない刑事裁判では、立証責任は減免されない。従って、検察官は、証明しようとする事実全てについて、立証責任を果たせるだけの証拠を出す必要があり、そのことは弁護人が何を言おうと不変である。恰も、弁護人が「サンダル着用の事実は争わない」と述べた場合は手薄な証拠で足りると言わんばかりの検察官の要求は前提理解が誤りであり、訴訟上、無意味である。
第二に、仮に弁護人が「争わない」と述べる場合、被告人質問で被告人がそのように答えると宣言したに等しい。被告人が争わないと言っているからこそ、弁護人もそのように述べることが出来るのであり、弁護人が書面に「争わない」と書けば、裁判所は法316条の10に基づき被告人に「質問」し「連署」を求めうる。そうすると、このような認否は、被告人質問の前倒しであり、黙秘権侵害に繋がる危険をはらむため、有害である。
(2)弁護団の対応
弁護団は、このような無意味かつ有害な要求・要望には当然、応じなかった(事案として着用を争うものではないが、一事が万事の例えもあり、要するに一つとして答えてはならないのである)し、それがために審理計画が頓挫したような事情はなかった。
よしんば頓挫したとしても、それは、現行法の枠内では無理からぬことであり異とするに足りないものであることは言うまでもない。
(3)小括
刑事弁護人には、計画審理や裁判員の負担軽減の名の下に刑事訴訟の大原則が歪められることを防止すべき職責がある。
弁護人が認否しなければ審理計画が定まらないと非難されたり、時に「期日間整理手続に回すことが必至だ」と恫喝されるかも知れないが、その時は毅然として、検察官が立証責任を果たせば足りること、被告人質問の前倒しには応じられない等と対応できる心構えが必要である。(金岡繁裕)
《裁判官、反対尋問に挑む》
私を含め、裁判官は敵性証人に対する尋問が下手です。その理由は、単純に、裁判官に対して敵意を見せる証人がほぼいない、その経験がないことに起因しています。
本稿は、そんな私の反対尋問体験記です。
1 今回私が担当したのは、和田啓一証人。被告人から犯行後、犯行を告白された上で、口止めされ、それをメモに残したとされる重要証人です。
そもそも、私がなぜ今回の弁護団に参加したか。たまたま1度だけ参加した裁判員制度実施本部の研修部会で金岡会員の目にとまり、「裁判官の尋問も見てみたい」と言われたからです。
実際の和田さんは大工さんです。ですが今回は模擬裁判。和田証人は多分検察官。主尋問でがちがちに検察有利な証言をしています。聞いていると、その供述は、原記録を材料に、微妙に検察有利に変容していました。小面憎さを覚えつつ、反対尋問に臨みました。
2 ご承知のとおり、最近弁護士会ではNITA研修が盛んです。私も、主任弁護人の舟橋会員の指導の下、ほぼ全て誘導尋問で固め、証人の弾劾に努めました。
「あなたは〜ですね。」「はい。」「〜でしたね。」「はい。」というやりとりを続けます。「はい。」としか言わされない証人のいらだちが伝わってきます。特に、原記録を知っているだけに、私が何を聞こうとしているかも分かるのがもどかしいところなのでしょう。時々、「その点は覚えていません」などとも答えます。
おいおい、原記録だとそこはハイだろ?それは掟破りじゃないの?などと思いつつ、尋問を続行します。
3 検察官のいら立ちも伝わってきます。私も内心は結構どきどきしています。「異議があります!」検察官が立ち上がります。
やっぱり来たか!
「質問の仕方を変えます。」日和って異議を回避します。
ものの本によれば、異議を言われたら、意見を言っている間に証人が立ち直ることを防ぐため、すぐに質問を撤回して、他の方法で尋ね、実質的に同じ答えを得るのがよいとするものもあります。ところが、私は、質問の仕方を変えたことによって、予期していたものと違う答えも得てしまいました。この辺りは経験不足を露呈したツメの甘さ。失敗です。
ちなみに、今回の法廷で一番異議を言われたのは、残念ながら私です。
4 質問を変えます変えますで逃れ続け、最後は重複尋問の異議を気持ちよく(?)撃退し、無事に尋問を終えました。
私が反対尋問で獲得した証言は、残念ながら評議ではガン無視されてしまい、切ない思いをしました。
弁論では和田証人の弾劾部分で使っていただいたので、一応の仕事はしたのかなと自らを慰めています。
そんな私の反対尋問は、金岡会員によれば48点だったそうです。これを高いと見るか低いとみるかは会員各位にお任せして、私の反対尋問レポートを終えることにします。(川口洋平)
《評議室》
「第三者の犯行の可能性を否定できない。」。それが本件模擬裁判で無罪を得た主たる理由である。
前提事実が正確に認定されている限り、特別の訓練を経ていない「市民の感覚」でも十分に判断可能である争点といえる。
問題は、前提事実がどれくらい正確に認定されていたかである。特に掘り下げが浅いと思われた証拠評価について指摘しようと思う。
1 供述証拠の信用性の認定
本件では、「嘘を言う理由がない。」という供述動機が、裁判員に特に重視されていたように思う。やや乱暴にまとめれば、法曹以外の人間は、物事を考えるときに、原因から解き起こす「原因からのアプローチ」を取ることが多いといえる。
これに対して、我々法曹は、「結果からのアプローチ」に慣れている。
動機等の内心を、他者が「証明」することはほぼ不可能であり、知覚条件や供述の変遷等の客観的事実を、素人からみればやや神経質なまでに指摘・弾劾しなければならない。特に反対尋問は、尋問の意図を証人に気づかせないため、婉曲に外堀を埋めるという作業が多くなり、弁論に至ってようやく意図が分かるということもある。
そうすると、信用性認定にあたっては、主尋問と反対尋問を通じた供述の全内容を、どれだけ正確に把握できるかが重要になる。裁判官としても、判決を起案する段になって、速記録を読み込み、細部の変遷等にようやく気付くということことがないではない。
本件では、6人の裁判員が、2人の証人の供述を正確に全て記憶していたとは思われず、印象(特に主尋問の)に頼った心証形成に偏した感があった。評議を傍聴した限りでも、証言場面の録画再生は主尋問部分に限られており、「嘘を言う動機はない」から出発するため、とにかく掘り下げが浅い。「結果として捜査段階との変遷が認められる」だけでは殆ど無条件に公判証言が信用されると言っても良いほどであった。
2 書証の証拠評価
同じことが書証の証拠評価についても言える。
本件では、例えばサンダルによるTシャツの潜在痕跡について、それが「潜在」痕跡であることを理解している裁判員が少なかったし、前提事実として争いがないはずの医師の供述についても、その理解に個人差があることが窺われた。
本来、裁判員裁判は、「法廷での心証形成」を旨とする裁判である。
ところが、現実には、時に驚くほど正確に記憶されている方もいるものの、大方は法廷で行われたことを正確に理解・記憶している裁判員は少ないといえる。
「評議室で書証を見ない」ことが、大前提のように言われることもあるが、私は見ても構わないと思う。むしろ、証拠に基づかない議論をされるよりよほど安心である。
今回の評議室でも、折りにふれて画像データで書証、証言内容を確認していたが、どうしてもつまみ食い的になってしまい、正確性を欠いた憾みがあった。そもそも、裁判官は証拠を手元に置いているが、裁判員は証拠を手元に置いていないようであり、しばしば、裁判官の事実認定教室と化すこと、これに対し裁判員が異を唱えようにも肝心の証拠が手元にないという構造的問題は指摘せざるを得ないが、それを措いても、印象的な記憶に頼り進められる評議は心許なく、被告人にとって納得いくようなものではなかろう。
3 各当事者の主張を参照させる
証拠の内容を確認する際も、手がかりになるのは、やはり各当事者の主張である。
事実認定においては検察官の立証責任が果たされたかが主要命題になるので、論告を軸に議論を進めていくという過程は正当である。
問題は、これに対置される存在としての弁論が、どれほど評議で活用されたかだが、個々の裁判員が個人的に参照するのはともかく、評議の中で参照される機会は少なかった。
短期間で充実した評議を行うためには、証拠評価のレベルでも、当事者の主張に公平に立脚し、顕在化した論点は全て議論することを原則とした評議をすべきである。これについては、評議の在り方だけにとどまらず、公判前整理の在り方等、裁判員裁判全体の制度設計に関わる問題であり、今後なお検討が必要であろう。
弁護団として、今にして思えば、舟橋主任弁護人のNITA風プレゼンテーションや、金岡弁護人の理屈っぽい弁論、川口弁護人の訴えかける語り口に加え、弁護人の主張が総覧できるような見取図を用意し、そこに表した問題点は全て解決してから判決に至るよう裁判員に釘を刺すべきだったとも思われる。そうでもしなければ、印象に残らなかった主張部分は評議で顧みられることもなく素通りされていく危険性が飛躍的に増すと思われる。最初から最後まで印象に残るはずもなく、そうであれば、このような工夫を余儀なくされよう。
4 裁判官の説示不足
最後に、説示不足について取り上げる。
裁判員は初めて裁判に関わり、一回的に判断するのみである。当然、裁判の基本原則さえ十分には押さえていない。そこで、適切な説示を折に触れて繰り返すことが重要になる。
本模擬裁判では、圧倒的時間不足からそこまで至らなかったが、本来であれば、間接事実積み上げ方の否認事件に相応しい説示内容を三者で事前に協議・合意し、最低でも何度くらい説明するかの合意形成にまで達しておくべきであろう(この合意違反が発覚すれば、訴訟手続の法令違反として控訴理由となると考えて良い)。
里見達彦事件の評議では、例えば「里見氏がF氏に暴行を加えたとされる後、F氏の依頼でポカリスエットを購入したか」という論点があり、これが事実なら、犯人性を消極に導くだろう。
この点、和田証人が上記事実を里見氏から聴かされたと証言し、里見氏自身は既に記憶がないと公判で供述したが、このような証拠関係からは、弁護人の主張する依頼の事実を退けることは難しいはずである。しかし実際の評議では、「里見氏が気を利かせたかも知れない(頼まれずとも購入した可能性)ですね」といった裁判員の意見が飛び出し、結局、認定されなかった。合理的疑いを越える立証とは何か、弁護人の立証程度、証拠裁判主義、といった基本原則を弁えると、このあたりで適切な説示をし、上記裁判員の推理を軌道修正させるべきところ、そのような裁判所の動きは見られなかった。
このような説示不足は随所に見られ、裁判員裁判の行く先の危うさを痛感した。裁判員は一般的に、検察官と弁護人の主張の、どちらを採用するかという意識で裁判に臨むと思われ、表面的に利益原則を教えたところで、直ちに心証形成が利益原則に忠実なものになるわけではない。
従って、評議では、基本原則に対する理解不足が現れる都度、それを適切に糺す必要があり、それができるのは職業裁判官しかいない。職業裁判官には、裁判員をして基本原則に忠実になれるよう導く職責があり、これを疎かにしてはならない。
5 まとめ
評議を傍聴し、被告人も弁護団も非常にもどかしく、腹立たしい思いもした。結果として無罪となったのは僥倖だが、このような評議が繰り返されるのであれば、裁判員裁判は被告人の権利を後退させるものに堕する危険すらあると思われた。(里見達彦弁護団)
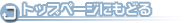
|