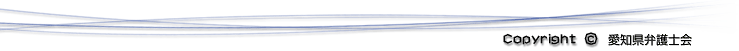11月26~28日の3日間、名古屋地裁としては初めての「被害者参加」型の模擬裁判が開催された。国選の被害者参加弁護士として当委員会から私と加藤正巳会員が参加した。
被害者参加人は検察官を通じて裁判所に申出をし、許可を得て初めて訴訟上の行為を行える。そのため、被害者参加人としては、検察官と十分に打ち合わせを行い、意思疎通を図ることが重要となる。被害者参加人は検察官の権限行使に意見を述べたり説明を聞くこともできるため、この点からも被害者参加人側から積極的に検察官にアプローチすることが必要となる。
今回の模擬裁判でも、公判期日前の活動として、公判前整理手続の前から検察官と打ち合わせを行った。①起訴状の写しの交付(実務での運用は未定とのこと)、検察官の提出予定証拠の閲覧謄写、弁護側から開示を受けた証拠の開示(被害者手持ちの文書であった)、公判前整理手続の内容の説明を受けたり、②検察官の尋問事項、論告(求刑部分除く)についての意見交換、③被害者参加人としての尋問事項、意見陳述、予定時間について意見交換、④被害者遺族の証人テストの立会い、⑤遺影の持込についての協議などを行った(裁判所の結論は傍聴席であれば可)。裁判所は公判前整理段階から被害者参加に対して制限的な姿勢が見られたため、検察官に要請し、随分と粘っていただいた。これまでに被害者支援弁護士として鑑定内容や不起訴の理由などの説明を受けたりしたことはあったが、弁護士と検察官との協働という新しい弁護士活動のあり方であると感じた。
裁判所との間での事前の準備としては、被害者参加人の着席位置について事前に法廷で協議を行ったり、当日被害者参加人の控室を用意していただいたり、傍聴席に被害者遺族席を用意していただいたりした。
公判期日においては、被害者参加人が行える全ての権限を行使した。即ち、①情状証人への尋問、②被告人質問、③心情その他についての(従来型)の意見陳述、④弁論としての(新設の)意見陳述である。被害者遺族の調書が不同意となり、⑤被害者参加人の証人尋問も行ったため、2日目は被害者参加人デーといった面持ちとなった。
①、②については、事前に検察官と十分意思疎通をし、検察官の尋問事項に意見を反映させれば敢えて被害者参加人が質問するまでもないケースもあろうというのが実際に行ってみた感想である。模擬裁判のため被害者参加人自身に実体験がなく、本人でなければ質問できないような事項というのが想定しにくかったという点もあるかも知れない。今振り返れば被告人質問については従前の検察官による被告人質問に囚われていたように感じる。証人尋問と違って尋問事項に制約はなく、③、④の意見陳述のために必要な事項であれば何でも質問できるのであるから、発想を柔軟にすれば様々なありようが生まれるように思う。本人と弁護士のいずれが行うかというのも今後悩むところである。今回①は本人、②は本人、途中から弁護士で行った。被害者当事者団体等からの強い要請で本制度が導入されたことに鑑みると法廷で自分で質問したいというニーズも高いと思われるが、様々な制約があり訴訟指揮もシビアな中で、被害者参加人自身が行うのは中々大変であると思われた。
③、⑤については、内容が重複し、裁判員に退屈な印象を与えたのではないかと思う。証人尋問が被害感情や情状に尽きる場合には、いずれかに絞る、内容を振り分けるなどして効果的な運用を図る必要があると感じた。
③と④は共に「意見陳述」とされているが、性質上の違いから③は本人が、④は弁護士で分担した。本件は情状が争点であったため、④では情状のポイント(示談を有利な情状にすることの可否、反省、謝罪がその名に値するか、前科の意味等)について被害者参加人からの評価を主張し、懲役10年を求めた。また、裁判員へ裁判員制度の意義、量刑データは今までの裁判の集積であることを訴え、自分の考え方に自信をもって評議して欲しいと結んだ。③で本人の口から最高刑を望むと言わせた上で、④では心情は最高刑だが法適用の意見としては10年であると主張した点は賛否両論あるかと思う。
被害者参加制度否定論のキャッチフレーズに「法廷が復讐の場になる」というものがあった。出演者の一人であったため舞台を客観視できないのであるが、法廷の雰囲気は確かに一変したのではないかと思う。被害者参加人の横でその各訴訟行為を見聞きしていてもそのことを肌で感じた(被害者参加人役の刑事2部月原書記官の名演技によるところも大きい)。被害者参加弁護士としてあの弁論をする直前には、弁護士として未踏の荒地に踏み込む気がして緊張が走ったのも事実である。
しかし、今回の模擬裁判は「復讐の場」という評価にはならないと考える。
被害者参加弁護士の立場に立ってまず考えたのは、被害者・遺族の生の声や意見を刑事裁判の場に提示し、判断の材料にしてもらうことである。ただ法廷の場で被告人を攻め立てるのが目的ではない。裁判員の方々にも汲み取って貰える活動でなければ意味がないと考えた。弁論の内容は感情論ではなく被害者遺族の視点からみた事実の評価であったつもりである。実際の評議の場では被害者参加人意見は求刑ばかりが取り上げられ、情状の評価についてはほとんど参照してもらえなかった。この点今後の工夫が必要であると感じた。