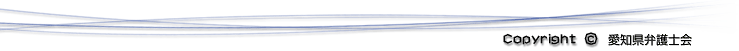- ��P�@�͂��߂�
-
�Q���Q�T������Q�V���ɂ����Ė@���O�Җ͋[�ٔ����s��ꂽ�B���É��n�ٌY���T���ٔ����R���A���É��n���Y�������@���R���y�щ�X�R�����e������S�������B
����
������^�N�V�[�������Ăł���A�N�i�ߖ��͋����v���ߋy�яe�C�����ޓ�����������@�ᔽ�ł���B
��̓I�ɂ́A�퍐�l�i�Q�O�Βj���j���A�^�N�V�[�ԓ��ɂ����āA�i�C�t�i�h���C�o�[���������������\�i�C�t�j��p���ĉ^�]��������ċ�����D����낤�Ƃ������A�^�]�肪��R���Ė\��N���N�V������炷���������߁A�퍐�l���i�C�t�ʼn^�]����h���A�������D���ē��������Ƃ���A��Q�҂�����̎����ɂ�莀�S�����Ƃ������Ăł���B
�Ȃ��A����̎����́A�퍐�l�̖��O���Ƃ��āu��ؑ��N�����v�Ƃ��āA�S���Ŗ͋[�ٔ��̑�ނƂȂ��Ă���B
�ٌ���j
�葱�ɐ旧���A�S�Ă̏؋��y�ь����������ٌ�l�E���@���o���ɊJ�����ꂽ���A�L�^��ǂٌ�l��̍ŏ��̊��z�́A�u�L���ȏ�قƂ�ǂȂ��v�ł������B
���Ȃ킿�A�ƍs���@�́A�u����ō��z�𗎂Ƃ������߁A��������Ȃ���N���������ɐ����|���ď����Ă����̂�҂��Ă������A�N�����������Ă���Ȃ������B��h���������Ȃ����߃z�e���オ�~���������Ƃ���A�́A�e���r�ŁA�^�N�V�[�����̃V�[���������̂��v���o���A�^�N�V�[�������v�������B�v�Ƃ����g����Ȃ��̂ł���B�ƍs�ԗl�́A���O�ɐl�C���Ȃ��Â��ƍs�ꏊ���߁A�N�z�̉^�]�肪�^�]����^�N�V�[��I��ŏ�Ԃ��Ă���A�v�搫�������Ƃ͌�����B�����́A�i�C�t�̐n�n��Ƃقړ����[���̏����ɐ����Ă���A�����E�l�ŋN�i����Ă����������Ȃ��ԗl�ł���B�����̋���́A��Q�҂��h������ɂ��̎�i�C�t���āA�ēx�A�猌�o�����Ă����Q�҂Ƀi�C�t��˂����ċ������Ƃɂ����������悵�Ă���ƈӂ��ア�Ƃ͌�����B�ƍs��̔��Ȃɂ��āA�퍐�l�͈⑰�Ɏ莆���o���Ă��邪�A�莆�̓��e���x���ŗ�ŎӍ߂̈ӎv������̂����炩�łȂ��B�Ƒ��̋��͂ɂ��ẮA�퍐�l�̕��e�́u���q���o�������Ƃ��ɂ͎����͐����ĂȂ����E�E�E�v�Ɩ��ӔC�ȑԓx�ɏI�n���Ă���B��Q�ُ��́A�{�l�E���e�o���Ɏ��͂��Ȃ����ʂ��������Ȃ��A�Ƃ����ł���B
���̂悤�Ȏ���Ɣ퍐�l�̌����̕s���������炷��A��ʓI�E�펯�I�ȍٔ����̊��o���炷��ƁA�u�퍐�l�ɂ͓���̗]�n���X���̉\�����Ȃ��B�v�Ɣ��f�����댯���������B���̂悤�Ȓ��A�ٌ�c�͎v�Ă̖��A�퍐�l�̕s��������퍐�l�́u�c�t���v�Ƒ����A�{���ƍs�́A�@�c�t���䂦�̎v�����̔ƍs�ł����Ĕƍs�ԗl�͌����Ĉ����c�E�ł͂Ȃ��A�܂��ނ͔ƍs���ʂ̏d�含�ɔ�ׂ�u�����l�v�ł͂Ȃ��A�A�ƍs��̔퍐�l�̍s���͒t�قł͂��邪�A�c�t�ȔނȂ�Ɍ����ɔ��Ȃ����Ă���A�X���̉\���͏\������A�Ƃ������Ƃ��ٔ����ɑi���悤�ƍl�����B�ȒP�ɂ����ƁA�u���Ȃ��i�ٔ����j�̊��o����́A�ǂ����悤���Ȃ��l�ɂ��A�ǂ����悤���Ȃ��ƍ߂�������Ȃ����A��،N�i�퍐�l�j�̃��x���܂Ŏ����𗎂Ƃ��Ď������݂�A�ނȂ�ɗ��R�������Ď~�ޖ����ƍs�ɋy�̂ł���A�ނȂ�ɔ��Ȃ��āA�ǂ���������������ɔY��ōl���Ă���B�v�Ƃ������Ƃ��ٔ����ɗ������Ă��炨���Ƃ������Ƃł���B
- ��Q�@�����O�����葱
- �@
��ؑ��N�����́A�͋[�ٔ��p�Ɂu�����W�ɂ��đ����̖������āv�Ƃ��Đݒ肳�ꂽ���Ăł��邪�A�����O�����葱�łٌ͕�l�E���@�����������Η������B
- �@�P�@�咣����
-
�����O�����葱�ł́A�܂��A���@��������u�ؖ��\�莖���L�ڏ��ʁv�ɂ��A�퍐�l�̐g��E�o���A�ƍs�Ɏ���o�܁A�ƍs�A�ƍs��̏����ڗ��ĂĒ��ꂽ�i�`���q�̂悤�Ȃ��́j�B�����āA�ٔ����́A���̏��ʂɊւ��A�ٌ�l�ɑ��āA�ڍׂȔF�۔��_�����߁A���@����o���ʂ���b�Ƃ��đ��_�������s�����Ǝ��݂��B
�Ƃ���ŁA�\���v�����������݂��邱�Ƃ̌��ʂ͍\���v���Y�����̔F��Ɠ��`�I�Ȃ��̂ł��邪�A����̑��ۂ̌��ʂ́A�]�������߁A���̑��ۂƕK���������`�I�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�{���ŕٌ�l���咣���悤�Ǝ��݂��u�퍐�l�̗c�t���v�́A�퍐�l�̔N��i�Q�O�j�ƕ����čl������A�@���W�҂ł���A�Y���ɕx�ݍX���\��������ƕ]�����Č��Y����ƍl����ł��낤�B�������A��������ł��A�ٔ����ɂ���ẮA�u�Q�O�ɂ��Ȃ��āA���Ղɏd�厖�����N�����悤�Ȑl�Ԃ́A�X���Ȃǂł���킯���Ȃ��B����Ȋ댯�Ȑl�Ԃ͌Y��������o���Ă͂����Ȃ��B�v�ƍl����l������̂ł���B
���Ȃ킿�A�\���v���Y�������ł���A���̑��ۂ𑈓_�Ƃ���悢���A����ɂ��ẮA�����̗L�����������ƂȂ�̂ł͂Ȃ��A�����̑g�����i�X�g�[���[�j�ɑ���]�������ƂȂ邽�߁A�ǂ̂悤�ȃX�g�[���[��ݒ肵�A���̃X�g�[���[�ɂǂ̂悤�ɏ������荞�ނ����d�v�ƂȂ�B�Ƃ��낪�A���@����o���ʂɂ́A�i�NJ��̗��ꂩ��\�������ƍs�Ɏ���X�g�[���[�Ɣ퍐�l�̐l�������W�J����Ă��邽�߁A���̒��̎������ʂɎ��o���ĔF�ۂ��s���đ��_����������ł́A�ٌ�l�̍l����퍐�l�����ٔ����ɓ`���Ȃ��������B
���̂��߁A�ٌ�l�͌��@����o���ʂ̔F�ہE���_����b�Ƃ��鑈�_�����ɔ��������A���ǁA�u���_�����Ȃ��ƍٔ����ɂ킩��Ȃ�����v�u���̎����́A�����ɑ����͂Ȃ����Ƃ��O��ƂȂ��Ă���͂��v�u�͋[�ٔ��̐�����܂��̂Łv���̏��ʂ̗��R�i�@�ߏ�v������Ă�����j�ɂ��A���@���쐬���ʂɑ���F�ۂ�����������Ȃ����ƂƂȂ����B�����ŁA�ٌ�l�͎d���Ȃ��F�ۂ��s���ƂƂ��ɁA�퍐�l�̐l�i�`�����s�\���ł��������Ɠ��̎咣�𒊏ۓI�ɋL�ڂ������ʂ��o�����B
- �@�Q�@�؋��ɂ��āi���ӏ��ʁj
-
�ٌ�c�̊�{���j�́A�@�����̉y�I�r������ь������q�ɂ�鎖���F��ƇA�q�ϓI�����̍��ӏ��ʂɂ��F��ł���B
�@�̕��j�́A�ٔ����ɂ́u�����v�Ɓu���q�v�̈Ⴂ�͗����ł��Ȃ��ł��낤�Ƃ������f�Ɋ�Â��i�ꌩ���H���R�Ƃ����q�����o�����ؐl���A�q��ł͑S�����H���R�Ƙb�����邱�Ƃ��ł����A���������،������邱�Ƃ��������Ē��������Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��ٔ����ɗ�������Ƃ����͍̂��ł���j�B�܂��A�A�̕��j�́A�ٔ����ɁA�c��ȑ{������Ӓ菑��ǂ�Ŏ����F��������Ԃ����������Ȃ����߂ł���B�Ȃ��A�I�ɂ́A������Ȃ����̉�U�ʐ^���������ٔ������A����I�ɏd������]�ފ댯�ɂ��z���������̂ł���i���ɁA�ٔ������҂̒��ɂ́A���̂̎ʐ^�����Ă���Âɔ��f�ł��邩�s���ł���Ɠ������l�������j�B
�����ŁA�ٌ�c�́A�@���@�������؋��̂����A�S�Ă̋��q�����Ƃ��̑��̂قƂ�ǂ̏؋��i�ːГ��{���ȊO�j��s���ӂƂ��A�A�ƍs�����A�ꏊ�A��Q�҂̎��S�����A�������̑���[�I�ɋL�ڂ������ӏ��ʈĂ��o�����B
�ٌ�c�쐬�̍��ӏ��ʈĂɊւ��āA�ٔ����́A�ٔ����ɕ�����₷���ł��낤�Ƃ̗��R����̗p�ɍD�ӓI�ł��������A���@������͌�������R�ɂ������B���@���́A���̗��R�Ƃ��āA���ӏ��ʂ͏؋��ł͂Ȃ����ӏ��ʂɂ�鎖���F��͋�����Ȃ��Ƃ������_�I�ȗ��R�̂ق��A�ٔ����Ɏ��́i�ʐ^�j���������ɕ]�c��������킯�ɂ͂����Ȃ����̗��R���q�ׂĂ����B���ǁA����́A�ٌ�c�쐬�̍��ӏ��ʈĂɑ��铯�ӂ͓���ꂸ�A�X�̏؋����ɁA���̓��e�����@�����v�����ʂɂ��č��ӂ�����`���̍��ӏ��ʂ��쐬���邱�Ƃɗ����������B
�ٌ�l���s���ӂƂ����؋��ɂ��ẮA���@�������{���o�����؋������������A�ٌ�l�Ƃ��Ă͋��q�����ł������ӂł��Ȃ��̂ł��邩��A�܂��Ă⏴�{������ĉv�X�j���A���X���قȂ鏴�{�ɓ��ӂ͂ł��Ȃ����߁A�Ō�܂Œ����ɂ͓��ӂ��Ȃ������B�������A�u�͋[�ٔ��Ȃ̂Łv�Ƃ����ٔ����̓V�̐��ɂ��A���@�������̂����P�ʂ��Y�i�@�R�Q�Q���P���ɂ��̗p����邱�ƂƂȂ����B
����ɁA���̋��q�����̎撲�ׂƔ퍐�l����̂ǂ�����ɍs�����ŁA�ٌ�l�ƌ��@�����Η������B�ٌ�l�͌������S��`�𗝗R�ɔ퍐�l������ɂ��ׂ��Ǝ咣���A���@���͌��@���ɗ��ؐӔC�����邱�Ƃ𗝗R�ɒ����̏؋����ׂ��ɍs���ׂ��Ƃ��ď���Ȃ��������A�����铌���n�قɂ�����͋[�ٔ����̗�ɕ킢�A����͔퍐�l������ɍs�����ƂƂȂ����B
- �@�R�@���z
-
�u�����ɑ����̖����v���Ăł��������A�葱�͑傢�ɕ������A�����O�����葱�͂Q��̗\�肪�S��ɂȂ����B�����̑��������ٌ�l�ƌ��@���őS���قȂ�ȏ�A���@�����]���̒����ٔ��Ɠ��l�̎�舵�����ٔ����ٔ��ɂ����߂�̂ł���A���Ăɑ������Ȃ��Ƃ��A�����̈����������Ď葱���������邱�Ƃ͔������Ȃ��Ǝv����B
- ��R�@�ٔ����I�C�葱
-
����́A�S�O�l��̍ٔ������҂��ٔ����ɏ����ꂽ�B�܂��A���ґS���ɑ��ď��ʂɂ��S�̎��₪�s���A�S�̎���̉����āA�ꕔ�̌��҂ɑ��Čʎ���i�ʎ��Ō��@���E�ٌ�l����̉��A�ٔ����������Ŏ��₷��j���s��ꂽ�B���̌�A���@���A�ٌ�l�����R�����s�I�C���s���Č��҂̈ꕔ�����O���A�c�����l����N�W�����ōٔ����U�����I�ꂽ�B
�S�̎���̉[�ƌʎ���̌��ʂ܂��ė��R�Ȃ��s�I�C���s�������A���₾���ōٔ������������͎̂���̋Ƃł���B�Ⴆ�A�ٌ�c�́A�ʎ���Łu�����̂悤�Ȗ��n�Ȑl�Ԃ����Y��I�����邱�Ƃ��S�O�����v�Ɠ������l���A�u���Y�p�~�_�҂��낤�v�ƍl���ė��R�����s�I�C����O�������A���̐l���A�ٔ����Ƃ��ĎQ�������]�c�ɂ����āA�u�l���E�����l�́A����̎��������ď���Ȃ�������Ȃ��B�����͎q���ɂ��������炵�Ă���B�v�ƔM�ق�U����Ă����Ƃ�����ł���B
- ��S�@����
-
- �@�P�@�`���q
���@���`���q�̓p���[�|�C���g��p���čs��ꂽ�B�X���C�h�̍\���́A���؎������ɕ������A�e�X���C�h�ɂ��Ă��A���������Ȃ����ăJ���[������𑽗p���铙���o�I�z�����Ȃ���Ă���A�ٔ����ɍD�]�ł������B
�����A�ٌ�l�́A���ʓ��Ŋȗ��ɏ��𗅗邱�Ƃ͔����A�u�퍐�l����Ŕނ̐l�Ԑ��ƍ���̔ƍs�Ɏ���o�܂𖾂炩�ɂ���̂ŁA�퍐�l������悭�����ė~�����B�v�Ɛ������A�`�S�łP���̗v�ʂ�z�z�����B
�`���q�ɑ���ٔ����̕]���̒��ɂ́A�@�ٌ�l�̎咣���A���@���̎咣�̂ǂ��ɑΉ�����̂��������A�A�ٌ�l���ŏ�����X�g�[���[�W�J���������������A�B���@�����P�Q�y�[�W�̏��ʂ�z�����̂ɁA�ٌ�l�z�z���ʂ��P���������̂ŁA�ٌ�l���蔲�������Ă���悤�Ɋ������A���̔ᔻ�I�ȕ]�����������B
�Ƃ͂����A�`�Œ��X����������A�퍐�l����Ŕ퍐�l�̌��������Ă��炤�����悢�̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���́A�����_�ł��̂Ă���Ȃ����̂�����B����ٌ̕���j�́A�u�퍐�l�̗c�t���v����Ղɐ��������̂ł��邪�A�u�퍐�l�̗c�t���v�𗠕t���鎖��͔퍐�l�̕s�����������������ł�����A���ړI�ɗ���ƁA�u����ȕs�����ȍs�����ޗʂ��ׂ��łȂ��v�Ǝv����댯�����������A�܂��A�퍐�l�����Ă��炤�O�ɍŏ�����u�c�t�Ȑl�Ԃ̂�������Ƃł����āA�X���͉\������A�y���Y�ɂ��ĉ������v�Ƃ܂Ƃ߂�ƁA�u���l�̂�������ƂȂ���w�c�t�x�ł͍ς܂���Ȃ��v�Ƌp���Ĕ������댯������������ł���B�܂��A�z�z���ʂ̖����ɂ��ẮA�����̑��ǂ����@���ƒ��荇���Ă��d�����Ȃ��悤�Ɏv���B�����A�ٔ����͂悭�������Ƃ��Ă���̂ŁA���@���̖`�Ŕz�z���ꂽ�y�[�W�����w�E���A�ٌ�l�̎咣���������Ă��炤�Ƃ����H�v�����Ă��悩�������Ǝv���B
- �@�Q�@���ؐl�q��
�퍐�l�ȊO�̒������S�ĕs���ӂɂ������߁A��Q�҉Ƒ��̏ؐl�q�₪���{���ꂽ�B��Q�����@��œf�I�����邱�Ƃ̉e���ɋ��������������A���قǕ]�c�ł͘b��ɏ���Ă��Ȃ������B
�ٌ�l�͔퍐�l�̕��e�̂ݏؐl�\���������A���̕��e�́A���q�̂��Ƃ������킩���Ă��Ȃ��_���e���ŁA�ē̐������Ȃ��������A�u���̕��e���Ƃ��̑��q�ɂȂ�̂������͂Ȃ��v�Ƃ�����ۂ�^����Ƃ������x�̌��ʂ͂������悤�ł���B
���ؐl���ǂ�قǍٔ����ɉe����^����̂��̓P�[�X���ƂɈႤ���낤���A����̎��Ăł́A�]�c���������ǂ���̏ؐl�����܂���ʂ��������悤�Ɏv���Ȃ��̂ŁA���ʂ̖R�������ؐl�̐q��Ɏ��Ԃ��������A���̕��A�퍐�l����Ɏ��Ԃ������ׂ��ł͂Ȃ��������Ƃ��v����B
- �@�R�@�퍐�l����
-
�ٌ�l�县��ł́A�Ə���ɂP���Ԓ��x�A��ʏ��ɂR�O�����x������U�����B
�퍐�l�̔ƍs�����̍s�����s�������������ł���A�v�����Ŕƍs�Ɏ������Ƃ����u�c�t���v��\�����߁A�ƍs�Ɏ���܂ł̌o�܂��ׂ��������A���₪�ƍs�Ɏ���܂łɂ��Ȃ�̎��Ԃ�v�����B���@���̕`���悤�ȁu�����Ȕ퍐�l���v��ے肷�邽�߂ɂ��̂悤�ȍ\���ɂ������A�Ă̒�A�ٔ����̂P�l����A�u�ǂ����ĊW�̔����ƍs�O�̌o�߂��ׂ��������̂��킩��Ȃ������v�Ƃ̎w�E�����B�����Ƃ��A������̑_���ǂ���A�u�c�t�ȍs���������Ƃ��Č���Ă��ďd�������Ȃ��Ă��悢�Ƃ��������̐S�ɂȂ������v�Əq�ׂ��ٔ����������B�ٔ������S���Ƃ�|�C���g�͌X�ɈႤ���߁A���l�Ɍ������@�Ƃ����͓̂���Ɗ������B
�܂��A�]�c���ɁA�퍐�l�����Ƃ߂��X�c�ˌ�����������Z�҂��������߂ɊÂ��ʌY�������ٔ���������A�퍐�l�̌������⋟�q�ԓx���ٔ����ɂ͉e����^������̂ł���Ǝv�����B
- �@�S�@�_���E�٘_
-
�_���͂`�R�p���P���ɍ��ڂ̂݉ӏ������ɂ������̂ł������B�ٔ����ɂ́A�_�����Ȃ��烁�������y��Ƃ��ė��p���Ղ������ƍD�]�ł������B
����ɑ��A�٘_�́A�Y�������I�Ȉ�ʘ_����A�����F��Ɋւ���咣�A����ɂ͔F�莖����ʌY�ア���ɕ]�����ׂ������A�����̎咣�荞�B���ʂƂ��ẮA�t�@�N�^�[���ƂɎ��`�}�ɂ܂Ƃ߂�`���Ƃ����B���ꂪ�ʏ�̍ٔ��ł���u�퍐�l�͎Ⴂ�A�Ӎߕ����o�����A�O�Ȃ������v�Ɨ��邾���ł�����邩������Ȃ����A�ٔ����ɂ���ẮA��������ł����Y���R�Ƒ����邩�ۂ��͐l�ɂ��قȂ�̂ŁA���̓_�܂Ŕz���������߁A���e���c��ɂȂ����B�܂��A�`���Ƃ��āA�ʂ̏��ʂ̂ق��ɁA�S�Ă̏��荞�ꗗ�\�ȏ��ʁi�`�R�j���쐬�����Ƃ���A���ʂ̑������玚���������Ȃ�ǂނ̂ɋ�J�����Ƃ̎w�E���������B�����ŁA����ɂ킽�����咣���̂ɂ��ẮA�u��������Ƃ͊����Ȃ������v�Ƃ����]��������A�ʌY�Ƃ����l�̉��l�ς����f����鎖���ɂ��āA�S�Ă̍ٔ������J�o�[���邱�Ƃ̓����Ɋ������B
- ��T�@�]�c
-
����̖͋[�ٔ��ł́A�ٔ����̕]�c���ɃJ������ݒu���A���̗l�q��@��̃��j�^�[�Ō��J�����i�����̍ٔ��ł͔���J�j�B
�ٌ�l�B�́A�]�c�̓����܂ł́u�٘_�܂ł������B�̎d���ł���A��̓I�}�P�v�Ƃ������o�ł��������A���ۂɂ́A�]�c�̖T�����ł��ʔ��������ɂȂ����B�Ⴆ�A��قǂ́u���ɂ͎����v�̘b���o�����ŁA�n�N�̍ٔ�������́A�٘_�Ŏ咣�������Ă��Ȃ��ٌ�l���̏؋��]��������������āA���j�^�[�߂Ȃ���u�Ȃ�قǁA�����]������悩�������v�u����ȑ�����������̂��v�ƚX�炳��A�܂��A��������邱�Ƃ����������B
�����āA�Ⴂ�ٔ����̕��͎����̍l�����i������`�j�ɌŎ�����X���������A�Љ�o���L�x�ȍٔ����́A�����𑽖ʓI�ɕ]�����Ĕ퍐�l�̎���ɂ��z������Ă���悤�Ɋ��������A������ɂ���A�ǂ̍ٔ��������ɐ^���Ɏ�����]�����Ă���A�����F��ɂ��ẮA�C�K���̃O���[�v�]�c�������x���̍����c�_���Ȃ���Ă����Ɗ������B
�����Ƃ��A�����啶�����߂�i�K�ɂȂ�ƁA�ǂ̍ٔ������S�O���Ă��܂��A���ǁA�ٔ���������ꂽ�ʌY���������Ă���̗ʌY�̌��ƂȂ����B���̂������A�ŏI�I�ɂ͂��܂�o�����̂Ȃ��ʌY�ɂȂ�A�����啶�͒����Q�O�N�ƂȂ����B
- ��U�@�Ō��
-
����̖͋[�ٔ���ʂ��āA���܂ł̍ٔ��������Ɂu�@���O�҂̈Öق̍��Ӂv�̏�ɐ��藧���Ă������Ƃ������Ƃ�Ɋ������B�ٔ����ٔ��̓����́A���܂œ�����O�Ƃ��čs���Ă������Ɓi�����ٔ����j���A�u�ٔ����̖ځv���ӎ����čĊm�F�E�č\������Ƃ����_�����ł��A�\���ɈӋ`�̂��邱�Ƃł���Ǝv����B
�����Ƃ��A����̖͋[�ٔ��́A�����̊��o�ł����A�u�٘_�����R�`�S��A�ؐl�E�{�l�q��Q�����A��@�����i�҂��ǂނ��߂̍ŏI�������ʂ̍쐬�v��v����葱���P�����ōs�����Ƃ��������A���A�u�ۂR���ԘA�����Ē�����[���܂ōٔ����ɏo�삵�čS�������v�Ƃ������ԓI�S���܂ŋ���������̂ł���B���̂��߁A���悻�P�����P�ʂʼn���Ă���ʏ펖���̃X�P�W���[���̒��ŏ�������ɂٌ͕�l�ɕ��S��������߂�����̂ł���A���̓_�ւ̔z�����Ȃ���Ȃ���Ό��S�Ȑ��x�^�c�͓���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���B