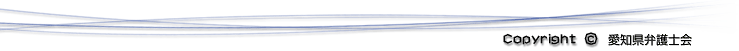- 1 はじめに
去る9月3日、光市母子殺害事件の弁護人である当会の小林修会員及び村上満宏会員による報告集会が開催された。当日の出席者は70名を超え、一事件の報告集会としては、異例なほどの関心の高さであった。
- 2 少年の生い立ちと精神年齢
まず、村上会員が、少年の経歴と精神年齢について、次のような説明をし、本件の本質を見誤らないためには、少年の生い立ちと精神年齢を正確に把握することが出発点であると強調した。
本件の少年は、小さい頃、たびたび実父から激しい暴力(虐待)を受け、鼓膜を破られたこともあった。また、少年は、母親が自殺未遂をする場面も見ており、母親は、少年が12歳のとき、遂に自殺した。このように、少年は、家族に守られて安心した生活を過ごした経験がなく、学校生活においても他人との信頼関係を築くことができなかった。少年の精神年齢は12歳のまま止まってしまった。
少年は、高校を卒業後、就職した。少年の就職先は家庭的な雰囲気があり、職場の人達は少年を温かく迎えてくれた。しかし、少年は、それまで家庭的な雰囲気に接した経験がなかったため、かえって職場になじめず、ずる休みをするようになってしまった。本件は、少年が就職してからわずか2週間後に発生した。
- 3 事実誤認の主張
-
次に、村上会員は、本件がなぜ事実誤認の事件といえるのか、弁護人が事実誤認の主張に全力を傾けるのか、詳しい説明をした。残念ながら、ここで詳細に解説することは不可能である。興味のある方は、ぜひ報告集会で配布された冊子を入手してお読みいただきたい(なお、その後、インターネットで検索すると、冊子と同様の内容を紹介するページを見つけられるようになった)。
合理的に物事を考える大人の目から見れば、本件で少年の取った行動は不可解であり、少年と弁護人の事実誤認の主張は、理解しがたいものかも知れない。しかし、前述のような少年の生い立ちや精神年齢を前提とすれば、全く別の事実関係が浮かび上がってくる可能性もある。
また、法医学鑑定によれば、被害者である母親の頚部を両手で強く締め付けて殺害したという点や、幼児を持ち上げて床に叩き付けたという点についても、原審が認定した事実に対する重大な疑問が浮かび上がってくる。
このように、弁護人の主張は、最高裁が死刑相当と判断した原審の事実関係を根本的に争うものであり、極めて真っ当な刑事弁護である。
- 4 マスコミや世論の反応
しかし、マスコミや世論は、今さらなぜ事実誤認の主張をするのか、なぜ原審で争わなかったのかなどと弁護人を強く非難する声が大勢を占めている。非難だけでなく、某弁護士の呼び掛けに呼応して、一般市民から弁護人に対する大量の懲戒請求がなされ、事務所への悪質な嫌がらせも多いそうである。一部では、本件で弁護団が結成されると、少年が原審で述べていなかった事実を突如主張するようになったのだから、弁護団は自分達の都合の良いように少年を操っているに違いないなどという誤った報道までなされている。
しかし、小林・村上両会員の報告によく耳を傾ければ、本件の弁護人の活動が、実は否認事件におけるオーソドックスな刑事弁護であり、マスコミの非難等は的外れであることが分かるであろう。
- 5 批判に応えるには
小林・村上両会員の報告に対し、会場からはいくつかの建設的な質問があった。マスコミ・世論の批判に応えていくためには、もっと弁護人の主張を広く知らしめる必要があるのではないか等々。
報告集会で配布された冊子は、かなり分厚いが、少年と弁護人の主張を正確に伝えるためには、どうしても、このくらいの厚さが必要になってくるようである。
しかし、このような冊子を大量に配布するには、相当の手間と費用がかかるだけでなく、そもそもどの程度の資料を公表してよいものかという難しい問題に直面する。弁護団は、慎重な検討の結果、今回の冊子を配布することにしたそうである。
- 6 死刑事件としての側面
本件の被害者遺族は、少年に対して死刑を望んでいる。現時点において、日本に死刑制度が存置されている以上、遺族が死刑を望む
ことは自然な感情であろう。
しかし、近代国家において、人を殺したら必ず死刑とすることはできない以上、そこにはどうしても死刑適用事案とそれ以外の事案との分かれ目ができる。
本件が、従前の死刑適用事案と比較して、果たして死刑にすべき事案なのか、弁護団は強い疑問を投げかけている。この点も、弁護人の職責からすれば当然のことである。
- 7 最後に
本件のマスコミ報道や懲戒請求騒動は、世間の人々に刑事弁護を理解してもらうことの難しさを浮き彫りにした。この点、小林・村上両会員の今回の報告は、丁寧で分かりやすく、熱意溢れるものであり、頭の下がる思いであった。結局、このような報告を地道に続けていくことが、刑事弁護に対する理解を得る唯一の手段ではないかと思われる。
今後も、本件の成り行きを冷静に見守っていきたい。