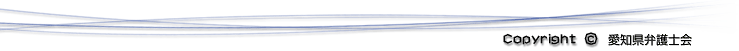シンポジウム後半では姜尚中先生、佐伯啓思先生、お二人による対論が行われた。
角谷会員の貫禄を感じさせる司会進行のもと、対論の予定時間50分はあっという間に経ち、「もう少しじっくり聞きたい」という思いが残るうちに終了時間を迎えた。お二人の発言の一言一言に多くの内容が凝縮され、大変充実した対論であった。
対論では主に3つの点について意見交換が行われた。筆者には先生方の意見を十分読み解くことができていないのでは、という不安もあるが、以下、対論の様子をご紹介したい。
- 1 理念と現実のはざまでもがく「権利」
-
一点目は「日本国憲法では国民の権利ばかりが強調されている」という批判をどう考えるか、という点についての対論であった。
佐伯先生は権利偏重型であり義務が疎かになっているというご意見、姜先生は年間自殺者の数等を挙げながら、憲法で明文化されてはいても、実態論的に権利が保障されている状態とは言えないというご意見であった。その上で、姜先生は「立憲主義」とは国家権力を付託された者が権力を縛る論理であり批判はそもそもあたらない旨、述べられた。
お二人の意見を受け、司会の角谷会員から「立憲主義は人間の本性に反し、民主主義をも制限する」という議論があるがどうお考えになるか、とさらなる問題提起がなされた。
この点、佐伯先生はそもそも明文化された法社会では調整できないことがある、と根源的批判を述べられた上で、従来の日本型雇用の例を挙げ「明文化されないルール」(慣行)によってこそ調整されすくい取られるものがあるのではないか、との意見を述べられた。
これに対し、姜先生は自明の伝統や文化はなく、何が「慣行」かということは現代の私たち自身が選択しなければならないのではないか、と述べられた。続けて、日本型雇用を産んだ背景に存在していた企業という社会的権力がすくい取ったものだけではなく、その一方で切り捨て続けてきたもの−1956年以降現在まで半世紀にわたり放置され続けてきた水俣病の例−もまた少なくないと述べられ、政治の貧困の責任を日本国憲法に押しつける(立憲主義ではすくい取れない問題とする)のはやめるべきではないか、と応酬された。
佐伯先生はこれに対し、政治の貧困という状況はよくわかる、しかしなぜ政治が貧困になったのか、それは戦後においても価値・思想を真剣に議論してこなかったからではないか、それは一部保守派政治家だけではなく、国としても個人としても選び取るべき価値に直面してこなかったのではないか、と述べられた。その上で、地方も開発主義的社会経済システムの恩恵を受けてきたという現実をどう見るのか、との問題提起をされた。
姜先生からは、韓国の朴政権、仏のド・ゴール政権に対する評価が二分されていることを例に挙げつつ、矛盾があることを認識した上で今をどう生きるかが課題ではないか、という展望が語られた。さらに「今を生きる」ことに触れ、先生は、日本では戦争をしないことは一つの歴史と言えるところまで時を重ねてきている、70年代韓国のように日本が「痛めつけられる」国に戻る必要はないのではないか、との意見を述べられた。
- 2 「立憲主義」に伴う緊張
-
対論の二点目は、第一点目とも関わり憲法「改正」論議の中で言われている「憲法で国民を縛るべき」議論の当否であった。
まず姜先生からは「立憲主義」と「民主主義」は相反する、世論による支配は時としてポピュリズムに陥ることがある、と明確な指摘がなされ、徹底した少数者の保護という視点から、憲法20条1〜3項と靖国神社の問題について言及がなされた。
これに対し、佐伯先生は近代市民革命を経ていない国である日本が「立憲主義」を擁することは可能か、という問題意識を示された。その上で、先生は平和愛好的、自然愛好的、公に対する責任、世間体といった諸意識は日本の人々の間に浸透していると評価され、日本の場合にはこれらの諸意識も憲法に盛り込むべきではないか、という意見を述べられた。
この論点については進行の関係上、これ以上の議論がなされなかった。佐伯先生のこのご意見には、引き続いての大会で採択された宣言(立憲主義と基本的人権尊重原則の堅持を求める宣言)とは異なる意見が含まれており、異論もあるところと思われるが、「立憲主義」を掲げていくことの困難さについての先生の問題意識や「我々は憲法を果たして本当に理解しているのだろうか」という問いかけには考えさせられるものがあった。
- 3 多数派世論にも「抗う」という「愛国」
-
対論の三点目は、教育基本法「改正」問題等において法制化されようとしている「国を愛する心」というものについて、それが果たして必要か、という点についてであった。
姜先生は丸山眞男氏の著作『忠誠と反逆』を挙げながら、国家は無謬ではない、国が過つことをただしていく抵抗こそが求められているとされ、「反逆できないでどうやって忠誠できるのか」、今こそ「愛国」を国から奪還しなければならないのではないか、と問題提起された。
これに対し、佐伯先生は同じく『忠誠と反逆』に触れ、同著では戦後の「反逆」には言及されていないが、果たして戦後民主主義において「反逆」はあり得るのか、国家を超える絶対的倫理(“God”)なき社会である日本では「反逆」はあり得ないのではないか、と応酬された。さらに、民主主義の名において国家を批判することには、ごまかしがあるのではないか(天に唾することではないか)、との問題意識を述べられた。
この問題意識については姜先生も同意されつつ、それでも、民主主義は絶えざる永久革命である、何がより民主主義に近いのかは人類史が続く限り終わらないとして、その民主主義を探究する民主化こそが重要ではないか、と応じられた。
その上で、姜先生が語られたのは「抵抗」する場合の相手は国家だけではなく、多数派「世論」もまた、その「抵抗」の対象であるという覚悟であった。その「抵抗」にあたっては「それでもやはり言葉を信じなければならない」とされ「言葉を通じて自分も変わるが相手も変わる」、そのことを信じて世論に対して「抵抗」できるのが民主主義である、と、情熱をもって対論を締めくくられた。
- 4 シンポジウムには会員以外の市民も多数参加され、
参加者であふれんばかりの会場で熱心にお二人のお話に聞き入った。
-
基本的人権の尊重ということを考えるとき、立憲主義と民主主義との緊張関係、司法の役割、そして「世論」に対して抗うという、この対論でお二人の先生方によって語られた事柄の意味は極めて大きい。今回のシンポジウムによって受けた得難い知的刺激を生かし、大いに考え、語りあっていきたいと思う。