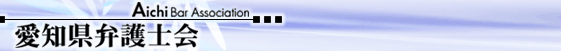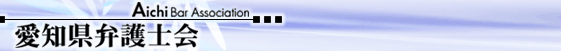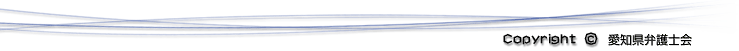|
改正刑訴法・裁判員法講座(17)
弁護人役を務めて
−三庁合同裁判員模擬裁判(公判期日・評議編)−
刑事弁護委員会 副委員長
裁判員制度に関する特別委員会 委員
園 田 理
1.
去る7月3日から5日にかけて実施された裁判員模擬裁判の公判期日と評議につき、弁護人役を務めた個人的な感想等を報告する。
2.
裁判員裁判における任意性・特信性に関する審理
- 被告人の検面調書の任意性や共犯者の検面調書の特信性を巡る審理につき、弁護人役として特に裁判員裁判を意識した運用を求めなかった。そのためか、特信性・任意性はあっさり肯定された。裁判所は従来の調書裁判を今後も継続していくつもりか…。
裁判員役の方々(調停委員や検察庁、弁護士会の職員)は、証拠採用された調書の信用性を安易に肯定せず、公判供述中心に評議を行った。ただ、実際の裁判員裁判ではどうか。検察庁や裁判所の今回の対応からすると、弁護人は、裁判員に、密室で作成された調書に依拠する危険性を訴えたり、裁判所に、特信性や任意性の判断に当たり裁判員の意見を聴取するよう求めていく(裁判員法68条3項)など、従前の実務が安易に踏襲されないよう絶えず注意を払う必要がある。
- 裁判員役の方々には、取調担当検察官の証言内容はわかりにくかったようだ。確かにわれわれも証言の不審点は取調経過や供述変遷経過を一覧表化しじっくり眺めなければ理解できない。まして一般の方には難しかっただろう。裁判員にもわかりやすい任意性立証、とりわけ取調べの可視化を一層強く求めていく必要がある。
3.
裁判員に対する法令等の説明
裁判長は、評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うものとされているが(裁判員法66条5項)、当てにできない。
裁判長から、検察官の立証が証拠の優越の程度では足りず合理的な疑いを超える程度までなされる必要がある旨明確な説明がなされた様子はなく、また本件では、事後強盗の暴行の程度や、共同正犯と幇助犯との区別についても説明がなされる必要があったが、なされた様子がなかった。
前者につき弁護人らが冒頭陳述で説明しようとしたが、検察官から冒頭陳述の範囲を越えるとの異議が出、裁判所は異議を認めた。仮に冒頭陳述を制限するなら、米国と同様、裁判長自らが公判廷で(弁護人が確認できる場で)説明すべきではないか。
なお、評議を傍聴し、適切な説明がなされていれば、被告人は暴行罪に止まったのではないかと感じた。
4.
裁判員に対する配慮
- 弁護人は、被告人の権利を守るのが第一で、裁判員に配慮しすぎる余り弁護活動を萎縮させてはならない。
- ただ、全く無配慮でもいけない。
裁判所策定の公判進行予定で、各証人尋問ごとに20分程度休廷が入れられた。中間評議を行うのではとの疑念があったが、実際はそれどころではなかったようだ。一般の方にはこの程度休憩を挟まないと、集中力が続かず体力的にも大変だという。
また、裁判員役の方々から、われわれ弁護人役に対する指摘は厳しかった。「冒頭陳述が長い」「尋問が回りくどい」「同じことを何度も聞く」などなど。
- 検察庁の組織的取組みに比べ、弁護士、弁護士会の取組みは、私自身も含め、大きく遅れている。このことを弁護人役を務めて、肌で実感した。
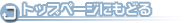
|