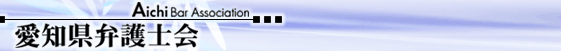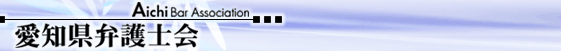| 全体会−21世紀の裁判所のあり方
第21回日弁連司法シンポジウムの全体会は、6月24日(金)午後1時から大阪市中央公会堂で開催された。三つの分科会から報告がなされた後、ハワイ州のサブリナ・マッケナー巡回裁判所判事の講演が、京都弁護士会の中村和雄氏との間の対話形式で行われた。
(サブリナ判事の講演)
サブリナ判事は流暢な日本語でハワイ州の法律制度等を紹介した後、ハワイ州の裁判官の選任方法について説明した。
米国の裁判官は、過半の州においていまだに選挙によって選任されているが、選挙に金がかかることは洋の東西を問わず同じであるらしく、金権選挙の弊害がいつも指摘されるという。この弊害を克服するため、各州で裁判官選任方法の改革が始まった。ハワイ州では1978年の憲法改正によって、いわゆるメリットシステムを採用することになった。この制度は、民主的に選ばれた裁判官選任委員会が裁判官を様々な角度から検討して選考する。ハワイ州では、州知事、上院議長、下院議長、州弁護士会が各2名、最高裁長官が1名、の合計9名の委員を選出する。
この9名のうち弁護士資格を有する者は4名を超えてはならない。すなわち、いわゆる市民委員が過半数を占めることになる。委員の仕事はハードであるが、無給である。それでも委員に選ばれること自身が大変名誉なことらしく、不満はないようだ。
裁判官の新任は、退官等ポストが空いたときに発生する。裁判官選任委員会は、新聞等で広く裁判官を募集する。委員会は、応募者を様々な角度から検討し、かつ全員と面接する。選考の結果、4名ないし6名を選び出し、これを州知事に推薦する。州知事は内1名を選び、上院の承認を得て、裁判官が誕生する(巡回裁判所以上の裁判官)。一方、裁判官の再任は、裁判官選任委員会のみがその適否を決める。最高裁長官でも例外ではない。すなわち、裁判所の組織の外にある裁判官選任委員会が、最高裁判事を含む裁判官の再任の是非を決するのである。
再任の是非について、委員会は様々な情報収集をするが、一番基礎となるのはその裁判官の事件を数多く体験した弁護士150名からの匿名の段階式アンケート結果である。段階式アンケートは、1993年から最高裁が弁護士会の協力を得て実施しているもので、3年目、6年目、9年目の裁判官に対して実施される。
このアンケート結果は、裁判官選任委員会、最高裁長官に送付される他、裁判官本人にも送付される。裁判官の自己改善に資するためである。2000年から裁判官評価レビューパネルという退役した弁護士、裁判官、および市民の3人1組がアンケート結果をもとに、裁判官の自己改善を優しく促す。もちろん、改善の跡が見られない裁判官は、最終的に再任されない結果となる。
法曹一元の米国と我が国では土台が異なるが、ハワイ州の裁判官選任方法は色々な面で参考にできると思った。
(パネルディスカッション)
続いて「みんなの裁判所」と題して、作家の夏樹静子、落語家の桂文珍、最高裁総務局長の園尾隆司、弁護士任官者の工藤涼二、前日弁連事務総長の大川真郎、サブリナ判事の各パネリストを迎え、大阪弁護士会の明賀英樹弁護士がコーディネーターを務め、パネルディスカッションが開かれた。
夏樹静子氏や桂文珍氏から裁判官は異星人のように思っていた、という裁判官に対する印象の話から始まり、裁判官の人事評価の話に入った。文珍氏や大川氏は大学教員もやっているが、大学では学生の教員に対する評価は当然のこととなっており、自分の改善のためにも必要なもの、と述べ、夏樹氏は、色々な角度、例えば書記官とか事務官などの目から見た評価も必要ではないか、と述べた。
地・家裁委員会の話題。夏樹氏は、福岡の地裁委員会の委員をしているが、2年間で9回の会合を持った、裁判所の言葉は難しい、例えばパンフレットでも市民から見ると大変分かり辛い、特定調停と聞いても分からない、裁判所関係者はそれを知って驚く。そんな中で、次回の委員会に行くと議論が反映されたパンフレットになっていた。試行錯誤を繰り返し、最終的に市民の感覚を取り入れたパンフレットが完成した時には、充実感を味わうことができた、と述べた。各地で停滞気味の地裁委員会や家裁委員会には大変参考になる話ではなかったか。
最後に弁護士任官の話。弁護士任官の数は残念ながら増えていない。園尾氏から「弁護士と裁判所の間には深くて暗い川があったのだから、そう簡単に溝は埋まらない。少しずつ改善されれば良い。裁判所は受け入れ態勢を続けます。」 という慰めの言葉をいただいた。弁護士任官については、市民はもとより、弁護士会も裁判所も増加を期待している。色々工夫を重ねながら弁護士任官を増やしていこう、というところでパネルディスカッションは大団円を迎えることになった。午後1時から5時30分まで、1000名を超える参加者を数え、大変充実したパネルディスカッションであった。
第1分科会−裁判官の任用と人事評価
第1分科会「裁判官の任用と人事評価」は、全体会に先立って午前10時30分から12時まで大阪全日空ホテルで開催された。
パネリストは大阪地裁判事の小西義博、下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員の堀野紀、同大阪地域委員会の水野武夫、早稲田大学助手の飯考行、コーディネーターは奈良弁護士会の本多久美子の各氏が務めた。
東京弁護士会の中尾正信氏が、裁判官の新しい人事評価制度の概要、下級裁判所裁判官指名諮問委員会創設の概要を説明した後、制度の意義および問題点を指摘した。
パネルディスカッションでは、堀野氏から指名諮問委員会の現状、水野氏からは地域委員会の現状が語られた。小西氏からは指名諮問委員会制度の現場裁判官に対する周知状況が、飯氏からは旧制度と比較した新制度の特徴が語られた。規則からいっても、地域委員会はもっと積極的に情報収集活動をすべき、との指摘があった。
続いて新しい裁判官人事評価について議論された。小西氏は評価書の開示請求をしたとのことであり、自身の体験を語られた。評価書で指摘された点は自分でも納得がいったし、勉強にもなった、とのことである。
一方、外部情報については、例えば裁判で敗訴した当事者から不適切な情報が寄せられるのではないか、それに対して反論の機会がないことは不安である、裁判官独立の原則との関係でも問題ではないか、との話があったが、堀野氏からは、適正な批判は裁判官独立の原則と目的は同じである、との反論があった。要は適正さの担保と思われた。
外部情報についてはハワイ州の調査が大変参考になった。我が国でも福岡県弁護士会の取組みや裁判官評価ネット関西の取組みがあり、その代表者から会場発言があったが、今後の適正な裁判官評価にあたり、匿名による段階式評価は注目に値する。
|