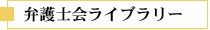| 平成17年1月15日、名弁ホールにおいて、「新しい労働法研修会〜労働審判制度を中心として」が開催された。まず、菅野和夫東京大学名誉教授の講演が、続いて定塚誠前最高裁判所事務総局行政局長第一課長(現東京高等裁判所判事)の講演が行われ、昼休みをはさんで、鵜飼良昭弁護士及び石嵜信憲弁護士が、それぞれ労働者側代理人、使用者側代理人からみた労働審判制度の意義と利用の仕方について講演され、最後に座談会が開かれた。講師をされた4名の先生方は、いずれも司法制度改革推進本部労働検討会において労働審判制度の立案に携わってきた方々であり、質量ともに充実した内容の研修であった。 |
| 1、 |
労働審判制度誕生の意義 |
|
バブル崩壊後のリストラ等に伴う企業共同体の変化により、個別労働関係紛争が増加しており、労働審判制度は、その解決の中心的制度として、労働関係における司法の役割をより大きくし、法の支配をより実質化するために誕生した。 |
| 2、 |
労働審判手続とは |
|
①個別労働関係民事紛争を対象とし、②地方裁判所(管轄)における、調停手続を包み込んだ(調停による解決見込みがあれば調停を行う)、争訟的非訟事件手続としての審判手続であり、③手続は、裁判官と労使実務家で構成される労働審判委員会が行う。④原則として3回以内の期日で審理し、⑤審判に異議があれば、民事訴訟手続に移行する(労働審判法24)。 |
| 3、 |
労働審判制度の特色は「SSS」 |
| |
①Speedy(素早く)
労働審判手続は、原則として、3回以内の期日で決着する(法15Ⅱ)。この3回の期日制限は、労働審判制度の生命線であり、厳格な運用が予定されているとのことであった。
そして、3回以内の決着を可能にするために、申立書・答弁書以外の主張には口頭主義が採用され(規則17Ⅰ)、関係者の迅速手続義務(法15Ⅰ、規則2、21)、弁護士代理の原則(法4)、調書と審判書の簡略化(法20、規則25、28)が定められている。他方、当事者が複数いたり、争点が複数あるなど、複雑な事件等は、審判によらず終了する(法24。訴訟提起が擬制され、民事訴訟に移行する)。
②Specialized(専門的で)
労働審判は、労使の労働審判員各1名と労働審判官(裁判官。将来的には弁護士任官も)による「労働審判委員会」が審理し(法7)、労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者の中から任命する(法9Ⅱ)。
また、労働審判事件は地方裁判所の管轄とされる(法2)。なお、当分の間は、本庁のみで行う考えとのことであった。
③Suitable(事案に即した解決)
労働審判委員会は、権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した審判を行うものとされ(法1、20Ⅰ)、また、和解的発想も取り込み、紛争解決のため、相当と認める事項を定めることができる(法20Ⅱ)。
|
| 4、 |
労働審判の対象 |
|
労働審判の対象は個別労働関係民事紛争である(法1)。集団的労使紛争、公務員の紛争、賃上げ等の利益紛争は対象外とされる。
他方、個別労働関係民事紛争であっても、制度的労働条件の変更や、人事評価・査定の問題など、3回以内の期日で審判することが困難な紛争は、労働審判にはなじまない。
労働審判になじむ紛争としては、賃金未払等の金銭トラブル、解雇等が典型である。なお、使用者から労働審判を申立てる場合としては、セクハラ等による退職者から損害賠償請求があった場合や、配転拒否の場合(解雇による紛争を避けるための方法として)などが考えられるとのことであった。 |
| 5、 |
労働審判手続の流れ |
|
(1)申立てから第1回期日まで(原則として申立てから40日以内(規則13))。
①申立て
迅速な審判を可能とするために、申立書には、充実した記載と証拠の添付が要求されている(規則9)。
②答弁書の提出
相手方は、労働審判官が定めた期限までに答弁書を提出しなければならない(規則14〜16)。答弁書についても充実した記載と証拠の添付が要求されている(規則16)。
③準備の重要性
両当事者は、第1回期日までの限られた時間の中で、申立書・答弁書を作成し、さらに、争点表や時系列表、基本的な書証のチェックリスト、陳述書などを作成する必要がある。また、解雇理由書や就業規則類、タイムカードなどの書証の収集や、当事者等の出席の確保とリハーサル(口頭主義に対応するため)も行わなければならない。鵜飼弁護士、石嵜弁護士ともに、第1回期日までのこれらの準備が最も重要であるとのことであった。
(2)第1回期日(2時間程度確保される予定)
口頭主義(規則17Ⅰ)、非公開原則(法16)が採用され、当事者は、審尋等による主張・立証を行い(法15、17、規則21)、労働審判委員会は、当事者の陳述を聴いて迅速に争点・証拠整理(法15Ⅰ)をする。
なお、当事者としては、口頭主義の下、重要な事項の記録化(テープ録音等)を図るべきである。
事案により第1回期日において、調停(法1、規則22)、終結(法19)、終了(法24)する場合もある。
(3)第1回期日〜第2回期日まで(約1か月)
当事者は、主張・立証の最終期限とされる第2回期日に向けた準備をし、(規則27)、必要に応じて補充書面を作成する(規則17)。
(4)2回期日
主張・立証を終了し(規則27)、調停の試みがなされる(法1、規則22)。
(5)第2回期日〜第3回期日まで(調停案の成熟度に応じて、1週間〜1か月)
紛争解決に向けて代理人と当事者本人の十分な打合せを行い、労働審判委員会から調停案が出されていれば、その検討をする。
(6)第3回期日
調停の試みがなされ(法1、規則22)、不調に終われば審理が終結し(法19)、労働審判が行われる(法20、規則28〜30)。もっとも、審判の内容を踏まえた調停案が呈示されるため、調停による終結が多くなるのではないかとのことであった。また、石嵜弁護士からは、労使間の信頼関係形成のために、調停成立に全力を尽くすべきとの話があった。
(7)訴訟への移行
当事者から、2週間以内に適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は効力を失い(法21)、訴えの提起があったものと擬制される(法22Ⅱ)。なお、審判の過程での主張・立証は審判の申立書(訴状とみなされる(法22Ⅲ))以外は訴訟には引き継がれない。 |
| 6、 |
最後に |
|
菅野教授、定塚裁判官からは、労働審判制度の成功のためには、弁護士の役割が重要であり、また、代理人の供給や代理人へのアクセスのための弁護士会の体制づくりが必要であることが繰り返し強調された。また、労働審判制度の定着を通じて、民事裁判全般においても、第1回期日から充実した審理がなされることを期待しているとのことであった。 |