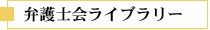2002年10月初旬の愛知学園職員殺害事件はもちろん、2004年初夏の佐世保の小学生刺殺事件や新宿幼児突き落とし事件についても、大騒ぎした割には、事件の本質がきちんと確認されたとは言い難い。その一方、必ずしも十分な議論が行われないままに、少年法改正の流れを加速するかのように、触法少年の扱いが変えられようとしている。改正の趣旨に賛成とか反対とか言う前に、問題の所在をはっきりさせることが求められていると思う。
|
| 1 |
愛知学園事件の本質 |
|
事件発生から他の自立支援施設から異口同音に聞かされたのは、「うちでなかっただけのこと」という言葉であった。問題の所在は、被虐待を中心とする「愛着障害」児童への対応が十分できなくて、管理的な対応に向かうという悪循環のくりかえしである。一見厳しい規律的な対応が、子どもたちには虐待(暴力)の再現に映り、不安と攻撃性を高めてしまっているのである。大切なことは、表面の行動の荒々しさへの対応ではなく、彼らの寂しい気持に寄りそえる職員集団の形成である。内面に注目が高まる思春期の属性に注目しつつ、自己肯定と信頼関係を取り戻す後押しをどうするかが主要なテーマとなる。
|
| 2 |
佐世保事件から見えること |
|
触法事件やその年代での殺人事件が増えているわけではないから、一事が万事の発想は避けなければならない。そのうえで、主張したい第一のことは、12歳の加害者は特別な子ではないという確認である。私は、事件の本質は、「よい子」の仮面をかぶった子ども同士が、親友と錯覚していたところ、不条理や二律背反がわかりはじめる思春期の入口に、他の子よりは少し早めに到着したことで、短絡的な不安解消に向かったと考えている。彼らをとりまく世界には、「つながる」という言葉が希薄になっている。支えあって何かを成し遂げる体験の衰退により、自分の弱みを相手に投影していじめるという方法で自己確認をするようになった時代の趨勢が垣間見られる。
|
| 3 |
新宿の事件が教えてくれること |
|
この事件での私の第一印象は、「難民」である。日本の戦後の混乱期にも「多動性行為障害」とラベリングができる子は多くいた。国際化の暗部に、アイデンティファイする対象を失った者が漂流しているのだ。少女は行為を否認している。それにしても、夜中のゲームセンターで幼い被害者と加害者が、あたかも大人同士のようにふるまう現実をどのように見立てればよいのか。子どもの安全神話はとうに失われている。しかも、不安は加速されている。それは、親や教師など大人が、手を携える人間関係の形成よりも、対症療法的な排除型安全に依拠していることと比例する。
|
| 4 |
考えてほしい現実 |
|
三つの事件を荒っぽく解剖した。見えてきたのは、「支えあい」「つながり」「連帯」といった民主主義の土台となるキーワードの喪失ないしは衰退である。子育てのつながりの衰退は孤立した子育て、つまり「孤育て」による虐待を生む。学校でのつながりの衰退は「いじめ」の発生土壌となっている。不登校やひきこもりという孤城をつくりたがる人は増えつづけている。1日90人も、中年を中心に自殺しなければならない社会は重苦しい。相手からの「見られ意識」に強迫的となり、過剰に適応する結果、「うつ」という孤独が待っている。わが胸にも恐る恐る手を当ててみたい。同時に、ささやかにつながりを模索したい。
|