|
会 員 多 田 元
今年1月の成人式の日、少したどたどしい口調で「今日成人式でした」と電話があった。以前附添人をした「少年」だ。その後、晴れ姿の写真を貼りつけ「僕も子どもを守る大人になるよ」と書いた年賀状が届いた。読んで思わず涙がこぼれた。彼は障害があり、小さいころからいじめられ、学校では教師を含め誰も守ってくれず、むしろ、教師からはひどい体罰を受けた体験をしている。筆者が附添人を担当したとき、彼は14歳、教師に対する傷害事件で初等少年院に送致された。筆者は、彼のいじめや暴力による心の外傷を回復することが、まず必要であると主張し、家庭的な雰囲気の委託先への補導委託を裁判所に提案したが、裁判官はほとんど共感を示してくれなかった。少年院への訪問や仮退院後も手紙や電話などで彼や親と交流を継続して約5年、彼は無事にたくましく成人し、朝は5時、6時に起きて凍りつくような現場に出て働いている。筆者などとても真似のできない厳しい生活だ。きっと地域で小さい子どもを守る大人として、頼れる存在になってくれるだろう。彼も、小さい頃守ってくれる人がいたら、非行などしなかっただろう。彼が少年院からくれた手紙に「ぼくは人のやさしさを求めていたのです。」と書いていた。
この「もと少年」の葉書が届いた数日後、別の少年のために、関西地方の少年院の成人式に「保護者」として出席した。院長から附添人を担当した筆者に「ご子息の成人式にご参加ください」と招待状をもらったのだ。社会復帰後の援助をどうしたものかと思案していたところだった。彼は、乳児の頃に施設に預けられ、15歳まで児童養護施設で育った。親とは全く交流がない。審判では、筆者は、昨年3月に子どもの権利特別委員会の講演会で話していただいた市川太郎さん(児童養護施設出身で、施設職員養成の教員をしている)の言葉を引用して、施設出身者がいかに社会への適応に苦労するかという問題を意見書に書き、社会内で支えることによって少年の成長を援助すべきであると主張したが、裁判官は、少年に対して「家庭に恵まれないことは同情できるが、施設で育った人が皆非行をするわけではない」と説諭した。審判後、少年は、筆者に「裁判官は機嫌が悪かったのですか。別に同情してほしくない。」と言った。
彼の成人式には、彼が育った施設の園長と筆者が二人そろって、お互いに「あやしい保護者だ」と言い合いながら参列した。型どおりの祝辞の後、新成人37人が舞台に上がり、ひとりひとり本名で誓いの言葉を述べる。「僕は20年前母のおなかをいためて生まれ、これまで母に心配をかけ通しで、苦しめてきました。これからは大人として母を支えたい」、「親に心配をかけた僕がここに入ってから子どもが生まれ、自分が『親』になりました。」等々さまざまな思いを込めた力一杯の言葉が続く。「わが息子」から聞いたところでは、誓いの言葉は、自分で考え、少ない余暇時間に暗記し、本番直前に声出しの練習をしたそうだ。新成人も、保護者たちも、この場が少年院でなければとの思いがよぎるだろう。そちこちで涙をぬぐう保護者たちを見て胸が痛む思いがした。「わが息子」には心配をかけるべき親はない。彼の順番になった。「なりゆきに流されず、自分で自分の行動を決めて、生きていく」と力強く宣言した。園長さんの目が潤んでいた。筆者は、「なりゆきに流されているのは大人の方だなぁ」と自省した。

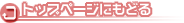
|

