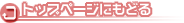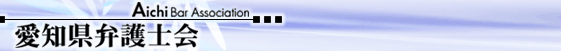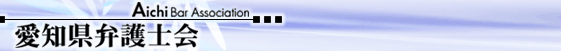1,設置認可申請出そろう
来年(2004年)4月に愛知県下で開校予定の法科大学院の、文科省への設置認可申請が出そろった。
大学名と1学年の学生数は以下のとおり。
愛知大学 40名
愛知学院大学 35名
中京大学 30名
名古屋大学 80名
南山大学 50名
名城大学 50名
合計 285名
平成14年度の司法試験(定員1200名)の合格者数は、愛知県全体で17名(名大15名、南山1名、名城1名)にすぎない。新司法試験の定員は未定だが、法科大学院の卒業生が受験する2006年度においては、現行の司法試験も併存するため、新司法試験の定員もかなり抑えられることになる。仮に、新司法試験の定員を1000名にしても、各校ともかなりの底上げと努力が必要となろう。
2,実務家教員候補者出そろう
各校の専任教員、みなし専任教員候補者も全て出そろった。
現在は、文科省の大学設置・学校法人審議会の法科大学院専門委員会でなされた各教員候補者の審査結果が、各校に通知されたところだ。文科省は、その担当科目の教員にふさわしい実績や経験があるかを、厳しく審査したようで、愛知県下の法科大学院でも、かなりの数の不適格者、保留者が出ている。不適格とされた場合は、その教員候補者に代わる新しい候補者を探して、「補正」しなければならない。今年の10月までに補正できなければ、来春の開校は断念せざるをえない。最終局面を迎え、教員候補者のリクルート合戦も、一層激しさを増すのではないだろうか。
今年の11月初には、各校の実務家教員が確定するので、どの法科大学院で、誰が、どの科目を担当するかを具体的にご紹介したいと思う。若手・中堅から、かなりのベテラン弁護士まで、バラエティーに富んでいる。
今秋の会報をご期待頂きたい。
3,弁護士会の取り組み状況と課題
(1)意見交換会の開催
7月7日、名古屋弁護士会の実務家教員候補者を対象に、意見交換会を開催した。実務家教員はどのように関わるべきか、教材はどのようなものがふさわしいかなど、活発な議論が展開した。
今後も、各大学の利害や思惑にとらわれず、あるべき法曹養成制度を自由に議論したい。
(2)教材開発
ロイヤリング、法曹倫理、民事実務などの分野で、法科大学院で使われる教材の検討が進んでいる。ロイヤリング、法曹倫理については、近々出版の予定である。
(3)弁護士会の役割
各大学の法科大学院が、それぞれの理念にもとづいて法曹養成に取り組むものであるだけに、弁護士会の関与の仕方は難しい。大学の自治を侵してはいけないし、各法科大学院の自主性を損なうものであってはならない。
しかし、あるべき法曹養成の姿、あるべき法科大学院の姿、実務家教員の関わり方などについて、弁護士会は各大学に遠慮することなく、積極的に発言し、時には批判し、時には提言していくことが必要である。