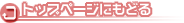最近、月に1回、ある大学の法科大学院に出かけて行く。民法という科目の演習(ゼミナール、略してゼミ)にオブザーバーとして出席するためである。
法科大学院は、平成16年度から開設された法律家養成のための専門大学院で、現在、全国に74校設置されており、来年からは法科大学院の修了者を対象とした新しい司法試験が始まることになっている。また、ゼミというのは、多人数の学生が大きな教室で教員の話を一方的に聴く講義形式とは異なって、比較的少人数の学生が、教員の指導の下、個別のテーマを巡る討論を通じて、法律的な知識を深め、議論を構成する力を涵養することを目指す講座の形式である。
ゼミへの出席と併せて学生が作成する答案の添削も引き受けていて、添削は本来の執務時間からは必ずはみ出すので(つまり夜更かしを強いられるので)時間的労力的に結構な負担にはなるが、束の間、実務を離れ、懐かしい大学の空気を吸い、学生たちの議論に参加するのは、ちょっとした気分転換ではある。
このゼミ担当の教授は、議論の素材として実際の裁判例を事案として与え、「登場人物が頭の中で個性を持って動き出すまで事案を読め」と学生たちに指示なさっている。そこで、学生たちは、裁判例に登場するAやらBやらになりきって、「こういう背景や裏事情があるはずだ」などと事案を深読みして見せたりするのであるが、総じて年齢が若く社会経験にも乏しい学生のことであるから、時としてありそうもない想像に走ってしまうこともよくある(そういうときに想像の暴走を制止するのは私の役目)。そして、事案の分析を踏まえて、「これこれこういう理論の構成によって、Aの請求は認められるべきだ」とか「Bの抗弁を認めて請求を棄却すべきだ」とかいった議論が、A派とB派に分かれて熱く交わされることになる。
ところで、弁護士の実務では、もちろん、勝ち目が大きいと予想される当事者ばかりが自分の依頼者になるわけではない。Aさんからの依頼を引き受けたならばこれはもう絶対にA派である。だから、主張を裏付ける証拠に乏しい事案や、そもそも主張自体がなかなか認められ難いと予想される事案に取り組む場合も少なくない。しかし、そうかといって、そのような事案の依頼者が箸にも棒にも掛からない独善的な主張に凝り固まっているのかというとそうではなく、それなりに切実な事情や思いがあって弁護士のところに来ている方々がほとんどで、そうした事情や思いを直接じっくりうかがうと、弁護士としても、何とかして差し上げたいと思われる事案も多いのである。そして、ここからが弁護士の頑張りどころ。勝つべき事件はしっかりと勝ち、どうしても負けが避けられない事件はせめて「きれいに」負けるように(「あっさりと」負けるという意味ではなく「美しく」負けるという感じ)、力を尽くすことになる。
法科大学院の学生たちは、今は、連日の課題提出の締め切りに追われながら、また、近づく司法試験への緊張と不安のうちに毎日を過ごしているのであろう。しかし、やがて実務に就いた時には、特に、裁判官などと比べて当事者との距離が圧倒的に近いところにある弁護士になった時には、別の苦労が待っている。依頼者となった当事者の切実な事情や思いを誠実に受け止めた上で専門家として適切な手続きを遂行するという、時として重く、辛い役割を引き受けるという苦労である。
学生たちと接するようになって、いつの間にやら自分が学生や受験生として法律を学んでいたころから随分と遠いところ、実務家の領域の住人になっていたことに気づかされている。