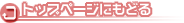「人の話を信用しないのか!」
これは、相手方からではなく依頼者から私に投げつけられた言葉である。
その依頼者は、勤務していた会社の社長から経営が大変だと相談され会社に数百万円を融通したが、いつまで経っても返してくれないので返還を求めたいと相談にきた。ところが、聞いてみると、借用証はなく、手渡しのため振込証もない上、他にこのことを知っている人もいないという。だが、数百万円もの大金を貸すのに借用証ももらわないなんてこと、あるんだろうか? 素朴な疑問のつもりでつぶやいたところ、依頼者の怒りを買って、冒頭の言葉がぶつけられたわけである。
因果な仕事である。裁判では、起こった出来事をいくら主張しても、証明できなければ事実として認めてもらえない。裁判において如何に証明できるかが、勝負の分かれ目になる。そのため、依頼者から話を聞くとき、弁護士は常にその言い分を裏付ける証拠の有無を確認する。信用しないわけではなく、裁判で認めてもらうためである。
依頼者の記憶以外に証拠がない場合には、依頼者の供述が裁判所に信用してもらえるかが重要になる。その信用性は供述が社会常識に照らして合理的かどうかによって決まってくる。例えば、冒頭の例で言えば、「お金を貸したときに会社の帳簿に借入金として記載してくれたのであえて借用証はもらわなかった」という事情があり、なるほどそれなら借用証をもらわずとも貸すことがあるか、と思わせることができれば、勝算ありである。
こうして、弁護士は、「証拠はあるのか」、「どうしてそんな非常識なことをしたのか」、等々意地の悪いことを口にすることになる。仕事とはいえ、人の話を疑ってかかるのは嫌なものである。
しかし、ここでどこまで意地悪になってしつこく聞き取れるかがこの先を左右する分岐点となる。夫から浮気をしていると疑われ離婚を求められた依頼者の女性は、私に涙ながらに浮気はしていないと訴えた。涙にほだされたわけではないが、いつもの意地悪を発揮できないままこの女性を信用した私は、後日、その女性が男性とホテルに入っていく写真を突きつけられ、愕然とすることになる。また、セクハラの被害を訴えた別の女性は、密室でのことなので記憶以外に証拠は何もないと言った。だが、その女性の記憶は詳細で、私の意地悪な質問にもなるほどと思わせるものであった。当初セクハラを否定していた男性も揺るぎない記憶という証拠の前に結局は認めざるを得なくなった。
真実は一つである。しかし、裁判となると、立証できる事実とそうでない事実が生まれる。その溝を埋めるために意地悪になるのが私の仕事だ。性格がひねくれないか、本当に心配である。