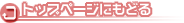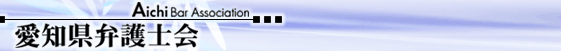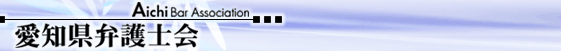検察官が大変不足している
1 検察官の役割
検察官はどんな仕事をする人たちかについて、一般の人たちにはあまり知られていません。
みなさんは「赤かぶ検事」シリーズをご存知かと思います。舞台は岐阜地検高山支部。フランキー堺が演じる庶民派の赤かぶ検事が、捜査と刑事裁判を通じて難事件を解決していく筋立てです。
実際の事件で検察官の活躍が注目を集めたのはロッキード事件でしょう。時の政界の実力者田中角栄氏が受託収賄罪で逮捕・起訴されたのは二十数年前です。この事件の捜査、公判(刑事裁判の訴追側)を担当したのは東京地検の検事でした。
窃盗、傷害、殺人などの刑事事件は、通常は警察が捜査をして、その上で事件を検察庁に送ります(送検)。これを受けて検察官は、被疑者等の取り調べをして、その被疑者を起訴するかどうかを決めます。
刑事訴追(公判請求)する権限は検察官の専権事項です。このことを検察官による「起訴独占主義」といいます。この点が捜査だけを担当する警察と捜査をふまえて起訴する権限を有する検察とが違う最も重大な点です。 また、起訴してその被疑者に刑事裁判を受けさせるか否かは検察官の裁量に委ねられています。これを「起訴便宜主義」といいます。
検察官が不起訴処分にする場合はいろいろあります。捜査の結果被疑事実が認められない無実の場合、被疑事実は存するがそれを裏付ける証拠がない場合、被疑事実が存するが違法性が軽微である場合、被疑事実が存するが被害者との示談が成立し被害者が許している場合などです。
起訴後は、刑事裁判手続きの中で、立証活動、求刑意見を述べるなどのことをします。
このように、検察官には刑事手続きでかなり強大な権限が付与されています。
2 どのようにして検察官になれるか
(1)正検事
司法試験に合格し、司法修習を経て、検察庁に検事として採用された者(以下、説明の便宜上「正検事」と呼びます。因みに地検のトップは「検事正」と呼ばれています)。 全国で一三六五名
(2)副検事
検察事務官(検事の職務を補佐する事務官)を一定期間勤め、検察庁内部試験で昇格した者。 全国で八二六名
(3)特任検事
副検事の職務を相当期間経験した者が検察庁の内部試験で昇格した者。 全国で四四名
3 検察庁内部での役割分担
本来は全刑事事件について正検事が捜査・公判を担当するのであり、例外的に、区検察庁で取り扱う軽微な事件(道路交通法違反、傷害、窃盗)を副検事が担当することが予定されています。
特任検事は、正検事の数が少ないものですから、副検事から内部昇格させ、正検事と同じ職務を行うことができるようにしたものといえます。実は赤かぶ検事はこの特任検事なのです。
4 検事の少ない実状
検事に付与された強大な権限からすれば、司法試験という国家試験に合格して、一定期間、裁判、弁護などの研修を受けた者が検事の地位につくということを、検察官制度は予定しているのです。
しかし、正検事の数が少ないため、本来、正検事がなすべき事柄を副検事が行っているのが実状です。
平成一二年四月一七日に行われた司法制度改革審議会の第一七回会合で、当時の法務大臣官房長は「現在では(地検の事件の)二五%程度しか検事はやれない。あと七五%は副検事に地方事件を委ねているという状態です、また、副検事が本来取り扱う区の事件というのは検察事務官が扱っている。こういうように少しずつずれてやっています」と発言しています。
別表は、東海北陸六県の検察官の配置状況です。名古屋を除く各地検の本庁には正検事は五~六名、支部に至っては、正検事が常駐していないところの方が多いのです。右の法務大臣官房長の発言と各地検の実状が一致しているわけです。
因みに赤かぶ検事がドラマの中での活躍している岐阜地検高山支部には正検事、特任検事はゼロで、副検事さん一名がいるだけです。
5 弊害
日弁連が平成一四年一一月に実施したアンケート調査結果によれば、①地検の事件を副検事が処理する問題としては、「法律の知識や理解不足」を指摘する意見が多く、②区検察庁の事件を検察事務官が処理する問題としては、「法律の知識や理解不足」に加えて「被害者への配慮不足」といった指摘が多くありました。 被疑者、被害者ともに我々国民です。検察の職務が適正に行われることは、我々国民にとって重要なことです。
別の機会に、検事の数をどれだけ増員すべきか、検事の研修として何が必要か等について紹介したいと思います