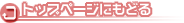法務大臣の諮問機関として「法制審議会」という組織がある。
この法制審が先般、わが国の刑事裁判に大変革を加える制度の導入を打ち出した。
犯罪被害者やその遺族(犯罪被害者等)に、①被告人質問権・証人尋問権・論告求刑後の意見陳述権を認める、②刑事裁判の有罪判決後、民事上の損害賠償請求の審理を行い、決定を出す(付帯私訴)などがその内容だ。
これまで、犯罪被害者等は、刑事裁判の手続においては、「証人」として、被害感情の一端を法廷で訴えるのがせいぜいであった。平成一二年には「意見陳述制度」が新設されたが、これは犯罪被害者等が公判で事件や被告人に対する意見や心情を述べる機会を与えるだけに過ぎなかった。
今回の制度案は、犯罪被害者等に、訴訟の実質的な「当事者」的地位を与えるものである。
犯罪被害者等は、法廷内で、訴追者である検察官側の席に座る。単に意見を陳述するだけでなく、直接、被告人や証人に対して質問や尋問ができ、求刑意見も陳述できる。
平成21年には「裁判員制度」がスタートする。 一般市民から無作為抽出された6名の裁判員は、被害者らの生の感情の爆発に直面する可能性がある。
確かに、犯罪被害者等は、予め、検察官に質問・尋問事項を申し出て、事前の準備が行われることになるし、裁判官の適切な訴訟指揮があれば、現実の公判廷に一定の秩序が保たれることにはなろう。
しかしながら、事実を否認し、無罪を主張する被告人に対する被害者側からの質問は、おのずと被告人の有罪を前提とした峻烈なものになることも予想される。
片や被告人は、その場で質問に反論することはできず、黙秘権を行使することができるだけだ。それは、被害者等には「無反省」の態度としか映らず、弁護人がどれほど無罪主張を繰り返してもただの「悪あがき」にしか見えないかも知れない。 犯罪被害者の怒りや悲しみは癒やされることなく、逆に増幅されることにはならないだろうか。
そして、被害者のみではなく、裁判員がその場の感情に左右され、判断の冷静さを欠いたとしたらどうなるか?
そのときには、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の大原則が大きく揺らぐ危険性も否定できない。
真実の発見と適正な処罰の実現を目的とする刑事裁判を、犯罪被害者の「報復」の場にしてしまってはならない。何も得るところがないどころか、それぞれが失うものが大きすぎるからだ。
〈刑事弁護〉と〈犯罪被害者救済〉は、決して、相反するものではない。制度のあり方としてこの視点を忘れてはならない。
それとともに、国や地方公共団体は、犯罪被害者への支援政策をより充実させることが急務だ。
現在、「犯罪被害者給付金制度」があるが、これに代わる新たな補償の制度を設けることで、より抜本的な拡充を図ることが不可欠ではないか。
同時に、各都道府県警や弁護士会、民間支援団体などの組織による支援体制が、行政とうまくリンクした形で機能していくことを望みたい。